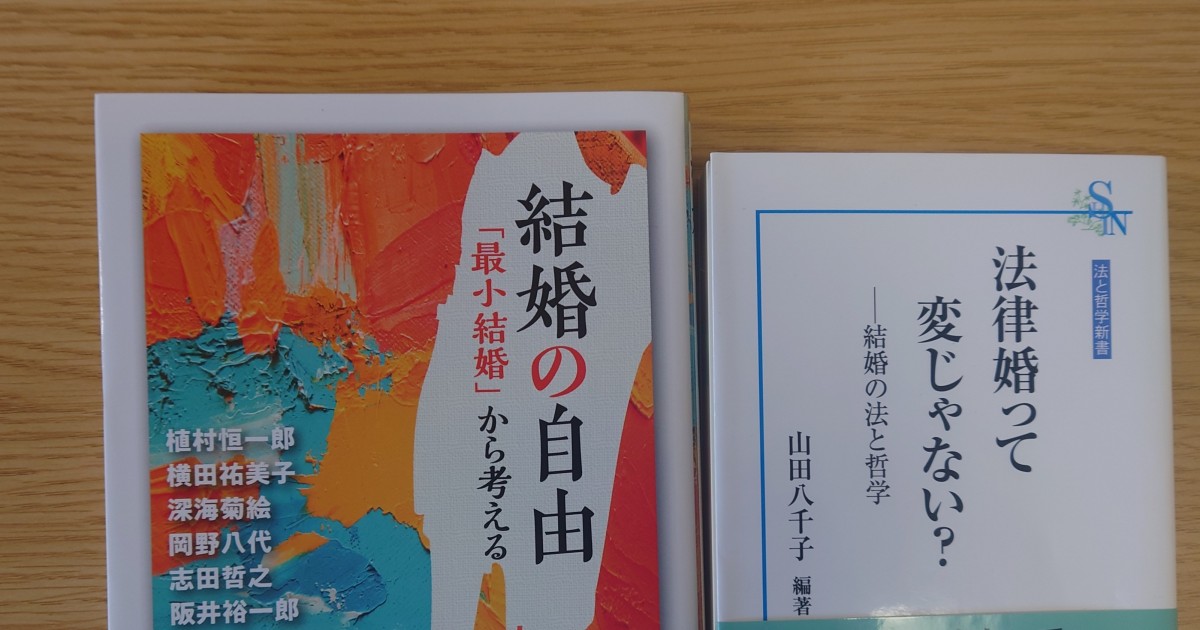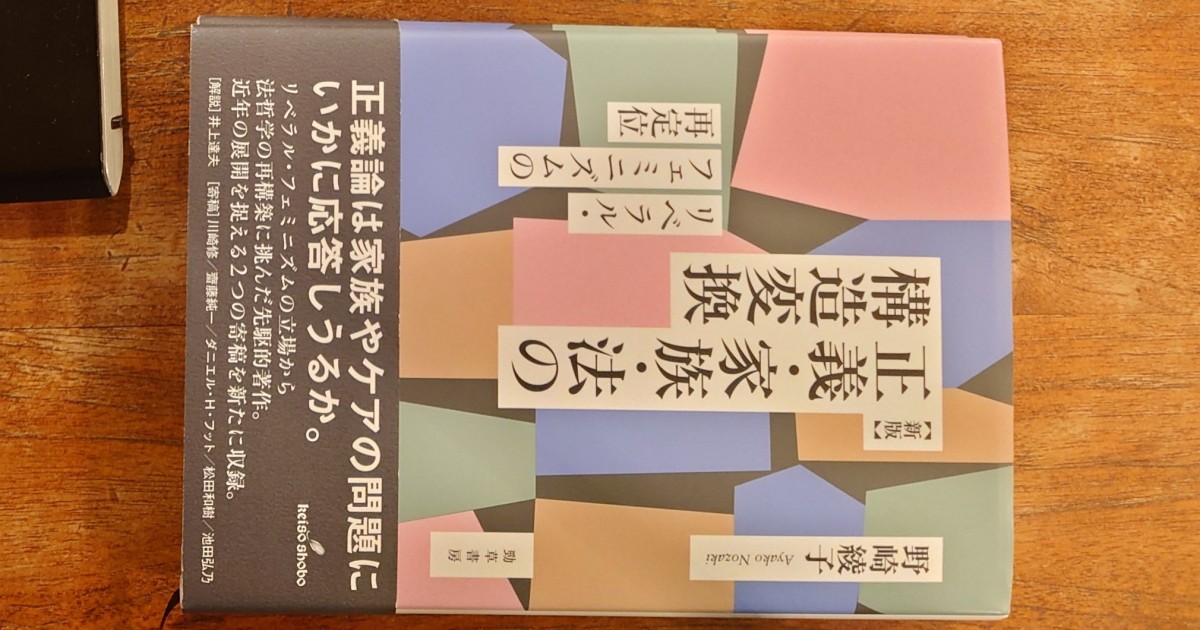水野家族法学を読む(28)「公正な秩序なき財産制」
【前回】
おはようございます。
当地も梅雨に入ったのですが、先週は寒さと出不精ですっかり体調を崩しました。
気晴らしの運動がしずらい季節。皆様もどうかご自愛ください。
今週は、先週ご紹介した、「法学教室」2022年1月号の連載記事に紹介されている関連論文を読んでいきます。
とはいえ、ニュースレターでこれまで取り上げてきた内容と重複するため、わりとあっさり終わってしまう感じがいたします。
民法のかぎりない存在の軽さ
<参考文献①>
水野紀子「民法と社会的・制度的条件」公証法学47号1-38頁(2017年)
※水野先生のHP上には2018年8月とありますが、2017年の誤りです。
「法学教室」連載記事では、P.78に「日本は、司法インフラの不備を、戸籍と登記と印鑑登録という行政インフラで代替させて資本主義を運営してきた。」とあり、その参考文献の1つに挙げられています。
公証法学という雑誌は初めて知りました。。。
日本公証法学会が出している雑誌とのことです。
冒頭、こんなエピソードで始まります。
大学の新入生に民法の初歩を教える講義を担当すると、そのはじめに、「典型的な法として、憲法と刑法と民法のどれを意識するか」と質問することにしている。例年、憲法と刑法にほぼ半々に学生たちの手が挙がり、民法にはほとんど手が挙がらない。同じ質問をたとえば民法の母国であるフランスで行えば、民法に圧倒的に手が挙がるだろう。民法は、日本人にとって、縁遠い法と感じられるようである。本来なら、民法は、市民の妥協と共生の秩序であり、もっとも身近な、日常的に接する法であるはずである。しかし縁遠く感じられるのはなぜだろうか。ひとつは東洋法の伝統であろう。東洋法は、律令すなわち行政法と刑法が主となるものであり、日本も、西欧法継受から一世紀余り経過したとはいえ、いまだに東洋法の伝統のなかにある。また、もう一つの理由として、後述する日本民法の特殊性が、民法を身近に感じる契機を国民から奪っていることが考えられる。
その背景となっている説明・内容自体は、これまでニュースレターでご紹介してきた水野先生の見解と重複しており、日本の近世(徳川日本)から武家法の伝統を色濃く残つつ、フランス法系を継受した明治民法の制定過程、それを支えるツールとしての戸籍/登記の創設。その継受が引き起こした矛盾、それが戦後改正以降も綿々と引き継がれていく過程が述べられています。
その結果、貧弱な司法インフラと公的介入に後ろ向きな政府の態度が、歪で不公平な法制度を数多く残置させ、それが親族・相続法のあらゆる規定に広範に広がっていること。その結果、家庭内の弱者が救済されずに取り残されていることが法制度の欠陥から明らかにされています。
そして「基本的バグ」は、戦後・近時の民法改正でも解決されていない、というのが水野先生の評価です。
冒頭の学生たちの反応は、現行民法が依然として公的介入力が欠如しているあらわれ、と水野先生はみているのでしょう。本来身近ななじみのあるはずの民法が、貧弱な公的介入力のため、市民生活で意識されることの少ない、「かぎりない存在の軽さ」を浮き彫りにしているエピソードなのです。
考察ー法ではなく、祈りー
もう1つ、同じ個所で取り上げられている論文が次のものです。
<参考文献②>
水野紀子「個人財産制と法手続に関する一考察」中田裕康先生古稀記念『民法学の継承と展開』(有斐閣 2021年)73-94頁
水野先生は、冒頭、「2世紀半の平和で安定した徳川日本に形作られたハピトゥス(日常生活の認知、評価、行為を方向付ける性向のこと。)は、日本社会に抗いがたく残っているように思われる。」と述べてから、次のように続けます。
本稿執筆時の2021年は、1868年の明治維新から153年にあたる。そして、1945年の敗戦で区切ると、明治維新からの前半は77年、後半は76年となり、ほぼ中間地点になる。明治維新後30年経過した1898年に施行された明治民法のもとで、つまり個人財産制のもとで、日本社会が運営されるようになって久しい。明治民法は、個人財産制、契約法など、資本主義の法的ツールを導入して、日本の近代化(資本主義化)が進展してきた。西欧近代法を、権利や義務や時効という翻訳語を作り出すところからはじめて短期間のうちに継受した。明治の日本人の偉業は、驚嘆すべきものであった。現在、経済成長の著しい東アジアにおいても、法的ツールは、明治人の作り上げた日本語の法律用語を用いた継受法が基礎となっている。しかしそれでは、日本社会は民法を継受して問題なく運用できているかというと、日本社会のハピトゥスと母法国にはない現実が民法とその運用を変形してきたところがあるように思う。
人間社会であれば、民事的な対立・抗争の存在は不可避である。しかしその対立・抗争の解消方法は、西欧社会と日本の伝統社会では異なっていた。徳川日本における「お上」による治安維持は、刑法・行政法によるものが主であり、民事については、治安を乱した相手方への「処分ないしは説諭を求める訴え」として現れた。それに対して「お上」は、当事者間できちんと処理するようにという「内済」へ向けた教導による解決をはかった。紛争の存在そのものは秩序を害するものであるが、結論がいかなるものであれ当事者間で「内済」されれば、秩序は保たれるのであり、そこには「権利」という概念はなかった。
村上淳一は、西欧法と日本法を次のように対比する。「社会における対立・抗争がノーマルな事態と考えられ、これを法/不法のコードに乗せて処理してゆくことによってはじめて社会秩序が保たれる西洋(とくにその近代)においては、各自の規範的主張も、法/不法のコードに乗る限りでのみ『権利』と考えられるのであり、逆に、その『権利』の主張によって法/不法のコードの内容が満たされてゆくことになる。専門の法律家(法学者ないし法実務家)によって制定法ないし判例法の体系が整備されると同時に、それをマスターした専門の法律家が裁判を担当する(裁判の拒否は許されない)。西洋の近代的な『権利意識』は、まさにこうした構造の上に生まれたものなのである。これに対して、対立・抗争がアブノーマルな事態とされた日本の伝統社会においては、法/不法のコードが独立の枠組として成り立つに至らず、『世間と人間についての知識』に基づく漠然たる『理非』によって紛争の解決が図られる。各自の規範的主張の対立は(どちらに『理』があるか)は、客観的なルールによって判定されるのではなく、その判断を予め読むことが難しいとすれば(大岡裁きは意外性をもつ)、どんな主張でも、とにかく理屈をつけて訴えでようということになり、自己の主張の実現によって社会秩序を形成しようという責任感が醸成されない」。
日本民法は、明治民法の「家」制度、「家」の私的自治は、戦後民法では当事者の私的自治に横滑りし、結果の不公正を正当化する多くの白地規定の存在について、水野先生は次のように述べています。
筆者は、従来、主として日本家族法のこのような特徴を批判的に考察してきた。当事者間の「協議」は、実際にはバーゲニングパワーの弱い当事者の敗北を意味し、裁判官の「大岡裁き」は、見通しの利かない高価な紛争費用を覚悟しなくてはならないことを意味する。このような日本法の家族間紛争対応について、民法学説は、「身分行為の不合理性」というマジックワードで、江戸時代のハピトゥスが日本家族法に影響している現実を糊塗してきたのではなかったか。そしてその大きな原因の一つは、西欧民法を動かす前提となる。村上の言う「法律家」の存在を、日本社会は、西欧社会と同質同量の存在としては準備できなかったことにある。裁判官の数は、すべての離婚を裁判離婚として運営するには、とても対応できない規模であった。
そこで、戸籍、登記、印鑑登録といった行政インフラがそれを補完することになっていきますが、「明治民法立法当時に、このような彼我の相違がどれほど自覚されていたのかは、疑問である」。と指摘されています。
この行政インフラの1つである戸籍制度について、当連載ですでにご紹介したように、「戸籍制度」という論文の中でその限界や疲弊と厳しく分析されていますが、一方で、完成された戸籍制度は、非常に便利な身分制度であることは否定できないとし、「弊害をわきまえたうえで、活用を続けるしかないであろう。」と述べています。
本論文において、水野先生は、家族法だけではなく、財産法領域においても影響があることを指摘し、もっぱら個人財産制について考察しています。
法的な構造において、西欧諸国の法は、個人主義の世界であり、権利義務の帰属主体となるのは、個人か法人のみである。個人への財産帰属を前提にして、家族間の相互扶助については、扶養義務を限定的かつ詳細に明定し、相続も、有効な遺贈以外は、法定の相続人に相続権として保障する。相続人の範囲は非常に広いが、扶養義務者の範囲は日本を含む東アジア諸国と比較すると相対的に狭く、近代以降は、さらなるセーフティーネットとして社会保障が準備された。そして西欧法においては、相続法の基本となる大前提は、相続が被相続人という法主体の消失を「清算」する手続だということである。したがって死亡から短期間のうちに行われる清算手続が、市民社会の中に制度的にビルトインされている必要がある。母法においては、この清算手続を公証人や遺産裁判所が行うことになる。そして英米法における信託は、この清算手続の過程を逃れるために発展した。
しかし東洋法の社会は、このような個人主義の社会とは異なる社会であった…。日本もまた、個人財産制の社会ではなかった。日本のかつての家族は、実際に住んで一緒に働く共同体の連帯が主になっていた点で、東アジア社会の中でも特徴的である。日本では、明治維新前の長い武家政権の間に、「家職国家」といわれるように、家制度が確立していたが、近世の日本人は、一種の「機構」あるいは「法人」としての家に帰属し、武士も町人も百姓もそれぞれ家の職業を営んできた。財産は家という組織に帰属する家産であり、当主は家の代表者に過ぎなかった。明治民法が立法されるまで、日本社会にあったのは、原則として個人財産ではなく家産であった。明治民法は、家産を当主の個人財産とし、個人財産制を立法した。現在の日本では、個人財産制が確立していることを疑う余地はなかろう。しかしその全貌を眺めると、母法における個人財産制の運用とは大きく異なっている。
水野先生は、「契約と財産管理」「不法行為」「夫婦財産制」「相続」という各場面において、西欧的な個人主義を貫徹した財産制と、時にはそれを大岡裁き的に修正する、日本法の融通無碍な、変則的な個人財産制を分析・対比し、最後にこう述べています。
「基本的人権の擁護」など、法の求める価値は、それを実現する仕組みが整っていなければ、法ではなく、「祈り」に近くなる。また、「自由」と「平等」がそうであるように、憲法の求める大文字の正義は、相互矛盾することも少なくない。現実社会に適用するためには、具体的な実定法が、その矛盾を止揚して、妥協と共生の秩序を作り出さねばならない。民法は、その実定法の最たるものである。日本民法が、そのような秩序を作り出し、実際にそれを実現する実定法の役割を果たすためには、西欧法継受国としての構造的相違を自覚しつつ、戸籍などの有り物を用いていかにその役割を果たすかというたえざる自問と自己改革が、日本社会にもそして民法学にも必要であろう。
なぜ、取引安全が極端に重視されるのか
水野先生の上記の問題意識は、「法学教室」連載記事に紹介されていた、この判例評釈にも現れています。
<参考文献③>
水野紀子「夫による妻所有の不動産の売却と日常家事・代理権の範囲」不動産取引判例百選(第3版)26-27頁(有斐閣 2008年)
最判昭和44年12月18日民集23集12号2476頁
夫による妻所有の不動産の売却したという事案において、民法761条をめぐる解釈について、最高裁が判断を示したものです。
<判旨①>
民法761条は法定の連帯責任ではなく代理権を定めている。日常家事債務の範囲の判断にあたっては当該夫婦の個別事情ばかりではなく客観的な視点が判断基準となる。
<判旨②>
民法761条を基本代理権として民法110条の表見代理が成立することを肯定すると同時に、その範囲は日常家事債務の範囲にとどまる。
民法761条はドイツ法・フランス法の継受ですが、条文上「代理権」と明記されていないため、法定の連帯債務と考えるか代理権と考えるか解釈の対立がありました。
しかし、水野先生は次のように指摘します。
不動産取引判例百選の開設という本稿では、家事債務に関するこの規定の議論には深入りしないことにする。なぜなら母法においては、代理権と性質決定しても、かつての夫の強い管理権を伴う不平等な夫婦財産制のもとであったとしても、配偶者の特有財産である不動産の処分が日常家事債務を根拠に認められることはあり得ないからである。本件の問題は、すぐれて日本法特有の状況がもたらした問題である。
実は、戦前においても、大審院は、夫婦間における日常家事代理権を基本代理権とする表見代理の成立を認めてきました。(大判昭和8年10月25日、大判昭和15年8月17日など)
しかし、この判決では、水野先生は、戦前のこれらの判例に批判的であった我妻説が有力化し、本判決にその影響をみています。
<我妻栄の批判>
「婚姻費用を分担すべき夫が子女の養育を妻に任せて他処に居住するようなときには、妻の権限内となる日常家事の範囲は却って拡大され、夫の財政的援助なしに生活するために、必要な借財をし又は夫の名義の財産を処分することも含まれると解さねばならない場合が多いと思う。」「従来の判例は、行為を抽象的に考え、その目的が夫婦共同生活の維持のために必要かどうかを考えないのは不当である。また、夫の不在中に妻が生計に窮して夫名義の借財をし又は夫名義の財産を処分したような場合に、これを有効とするために、夫が暗黙に代理権を与えたものとみようとするのも、無用のことである。」
しかし、先週ご紹介したような、遠藤浩(早稲田大学名誉教授)のように、こうした紛争を単に「みうちのいざこざ」と捉え、表見代理の成立を積極的に容認するような、取引安全を極端に重視する見解を指摘し、その背景に「西欧法のように夫婦財産制によって法的に夫婦個人の財産を相互の占奪から守る文化もなかった。」と指摘します。
これに加えて、これまでの連載で指摘してきたように、家族法だけではなく、財産法領域においても、「公正」を基準とした秩序に基づき、横暴な強者から弱者を保護する機能を、司法が持っていないことを指摘します。
本判決以降、判例は他方配偶者の不動産の処分を日常家事債務の類推適用で認めたケースはなく、不動産取引実務も夫婦であっても名義人自身の取引関与を慎重に要求するようになったとされる一方、水野先生は「問題は解決したわけではない」と釘を刺し、「物権変動に登記を対抗要件としつつも、証書謄写型登記制度や公証人慣行を欠いている日本法の構造的問題が尾を引いている」と指摘します。
やはり、どこまでも「解釈」は弥縫策であり、そもそもの「インフラの欠如」ー公証人や司法の関与に費用をかけて取り組む必要性を示唆しています。
2022年1月号の水野先生の連載記事のご紹介、関連論文の紹介はこれで終了です。
来週は、2022年2月号の連載記事をご紹介します。
【連載記事一覧】
すでに登録済みの方は こちら