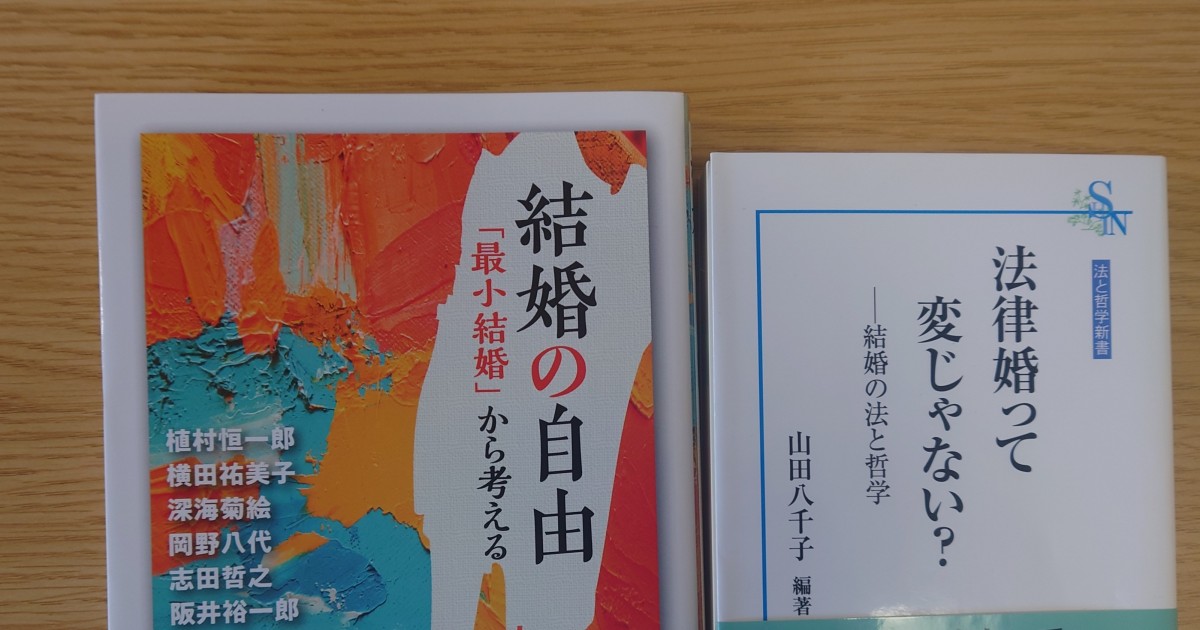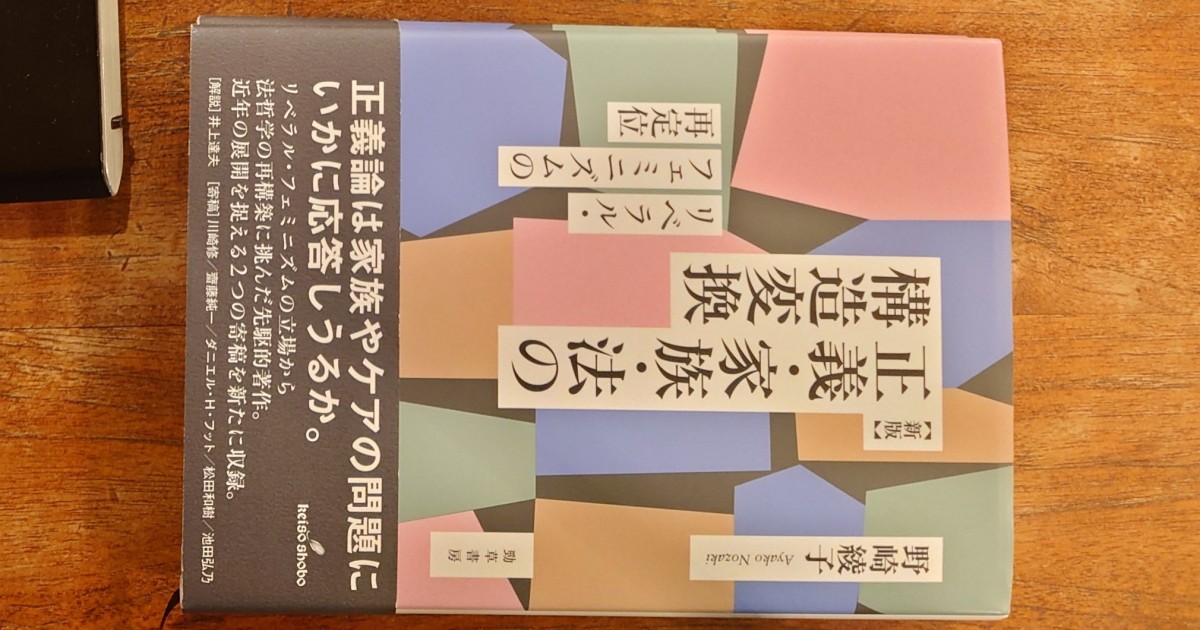水野家族法学を読む(27)「夫婦の財産関係を考える」
こんにちは。
水野先生の連載記事2022年の第一弾は、先月号に続き、婚姻の効力について考察されています。
<参考文献>
水野紀子「日本家族法を考える 第9回 夫婦の財産関係を考える」法学教室496号77頁以下(有斐閣)
民法の規定と制度的特殊性
まず、水野先生は、日本の民法が夫婦財産契約・夫婦財産制についてわずかな規定しか置いていないことをこのように指摘されます。
夫婦の財産関係に、これほどわずかな条文数しかもたない民法は、西欧法では考えられず、はるかに多くの条文を要するのが通常である。しかも第1款の夫婦財産契約つまり約定財産制に関する4か条は、まず使われない条文である。つまり日本の夫婦財産制は、わずか3条で運用されており、基本である財産の帰属については、民法762条の定める法定夫婦財産制、それはまるで他人間の関係のように夫婦相互が独立した完全別産制で運用されていることになる。
民法755条以下の夫婦財産契約を結べば、共有制などの他の約定財産制を選択することは可能である。しかしこの夫婦財産契約は、婚姻前に締結せねばならず(民755条)、登記しないと夫婦の承継人や第三者に対抗できず(民756条・759条)、結婚後に変更することはできない(民758条)。この契約の存在は知られていない上、これらの条件だけでも意気阻喪するだろう。このような契約をする夫婦はごく例外的で年間一桁かせいぜい十数件しかないが、私は夫婦財産契約を締結した知人を2組知っている。こういうことをしでかすのは、民法学者や弁護士のカップルで、彼らの体験談によると、登記をしに行ったら前例がなくて、登記所が上を下への大騒ぎになったそうである。
そしてこう告白します。
そもそも日本人には、夫婦財産制のイメージがあまりないのだろう。実は私も夫婦財産制は苦手である。おそらく私のみならず圧倒的に多くの民法学者も、同様なのではなかろうか。
これに対し、フランスでは、数百条の条文のある夫婦財産制は、それだけで独立した教科書を思想とする、歴史的にも思想的にも重厚で多彩な法領域であるが、日本法とこれだけ大きなd違いを生んだ原因に、やはり司法インフラの整備の欠陥を指摘されます。
日本法は、司法インフラの代わりに戸籍と登記と印鑑登録という行政インフラで代替してきたが、フランス法と異なり、公証人が家族の財産関係に介入しない日本では、利害対立する共同相続人間が遺産分割で対立した結果、所有者不明問題が生じたり、不実登記の危険性を構造的に抱えたりしています。
夫婦財産制の歴史と契約取消権
そして、そもそも夫婦財産制は、現代家族の財産関係に適合しない背景を指摘されます。
夫婦財産契約の原型について、現代のサラリーマン家庭を想像してはならない。イメージとしては、羊などの財産で暮らしている部族がそれぞれの部族に属する若い男女を結婚させる前に、部族同士で2人にもたせる財産と離別時の分配を取り決めておく契約である。民法755条以下が定めるように、婚姻前に定めて婚姻後に変更できないという夫婦財産契約の縛りは、部族間の取り決めと考えれば、自然なものであろう。
このため、西欧では、近代化に伴う夫婦平等な別産制への変化と、夫婦の財産が婚姻家族の基盤となることが同時に前提とされ、夫婦の一体性が尊重される部分と夫婦の平等・独立が尊重される部分が混在した結果、数百条の条文が必要になったと解説されます。
これに関連して、夫婦間の契約取消権を定める754条について、日本では、夫婦間で契約の履行を裁判所の力を借りて強制することは夫婦間の円満を害するとか、夫婦間に司法が介入するべきではないと説明されることが多いですが、これは法は家庭に入るべきではないという日本的な説明である、とされます。
そして、同条の取消権は、母法のフランス法と異なり、贈与に公証人の関与がなく、日本では協議離婚制度の存在によって、母法では想定されない濫用的な用いられ方をしたため、判例(最判昭和33年3月6日、最判昭和42年2月2日等)によって封じられ、事実上適用の余地がほとんどなくなっています。(ただし、学説の一部は、夫婦財産契約締結時に夫婦関係は破綻しておらず、取消し時に破綻していた場合には、遺言の撤回と同様に、取消権の行使を認めるべきと批判されている。)
日本法の夫婦財産制
これまで説明してきたように、西欧法は、ローマ法由来の部族財産制から近代市民社会にアジャストするために、複雑な発展を経ているのに対し、日本法は、明治民法での女性の無能力を前提として、夫が戸主権の下、夫がまとめて管理・収益するという制度から、戦後民法は、機械的な夫婦平等制をに変更します。
ところが、戦後サラリーマン家庭で女性が「主婦」として婚姻することが主流となると、離婚時に、その弊害として、母子家庭の貧困が深刻な問題となります。
水野先生は、離婚給付や養育費の貧弱さと並んで、徹底した別産制もその原因の1つであり、日本法での男女平等の要請は別産制を批判する方向へと働いた、と指摘されます。
水野先生は次のように論じます。
日本の夫婦財産制に関する学説の議論は、従来必ずしも活発ではなかったが、別産制を変更しようとする立法論に対しては、消極財産も共有となるため必ずしも妻の保護になるとは限らないという反論が加えられてきた。しかし夫が勝手に作った借金は夫の特有財産の負担とされる場合が多いだろう。日本法では、所有権者である配偶者の恣意的な不動産処分から、家族の居住権を守ることもできない。これに対してフランス法では、別産制においてさえ、清算にあたって労力による支出を清算するなど、夫婦の属性に応じた複数の救済措置が講じられる。また夫婦別産制の如何を問わず、家族の居住権を保護するための処分に対する制限が存在(フランス民法215条3項・220条の1など)。そしてこれらの保護を実効化するのは、公証人の関与であり、この関与の存在が実際には彼我の最大の相違ではなかろうか。
そして、夫婦別産制を合憲と判断した最大判昭和36年9月6日について、次のように批判されます。
戦後立法された768条の財産分与は、実務が内容を充実させて、現在は、夫婦が協力して構築した財産の清算として扱われるようになっている。つまり財産分与まで合わせて考えると、後得財産参加制を採用しているといえないわけではない。もっともその場合は、財産分与は夫婦財産制の清算分となり、財産獲得能力の差を補う、母法のような離婚給付は、日本法ではまったく認められないという評価になる。戦後改正で認められた配偶者相続権は、昭和55年改正を経てさらに強化されたが、夫婦財産制の清算を合わせて考えると、比較法的には、婚姻中の蓄積のみが遺産の場合が相続権がないとさえ評価でき、到底強力なものとはいえない。最高裁が言うように「実質上の不平等が生じない」かは、大いに疑問である。
一方で、最高裁は、夫婦間における争いでは、必ずしも名義にこだわらない所有権帰属判断をする姿勢を示し、妻名義で取得した土地を、取得代金を出捐した夫のものと認定しています(最判昭和34年7月14日)。
最高裁の判断は、いわゆる主婦婚であるサラリーマン家庭と共同事業を営む夫婦の場合とで、大きく分かれている。その理由のひとつは、伝統的な家業家族の場合には、その実態に合わせる必要があるからであろう。また、家族間紛争では、波及効果が大きく法創造的な要素を持ってしまう主婦婚の妻の保護よりも、共同事業を営む場合の妻保護においては、より当事者間の実質的な関係に踏み込んで、共有を承認しやすいからと思われる。しかしこのような判断の余地は、被相続人名義の財産が必ずしも被相続人の遺産とは限らないことになるので、被相続人が再婚していたような遺産分割紛争で、遺産分割の前提として地裁で争われる遺産確認の訴えを激化させる一因となっている。
日常家事連帯債務
水野先生は、同様の問題構造を、民法761条が定める夫婦の日常家事の連帯債務規定にも見ています。
判例はこの点、761条の日常家事代理権を基本代理権として110条の表見代理が成立することを理論的に認めていますが(最判昭和44年12月18日)、水野先生は、「109条などの表見代理を主張したのであったら認められた可能性はないとはいえないだろう。」と指摘され、そして、761条の法的性質については、かねてから法定の連帯責任とみるか代理権とみるか学説の対立があるものの、「しかしいずれにせよ、母法においては、代理権と性質決定しても、配偶者の特有財産である不動産の処分が日常家事債務を根拠に認められることはあり得ない。この昭和44年判決の問題は、すぐれて日本法特有の状況がもたらした問題である。」と述べています。
そして、昭和44年判決から24年後でも「みうちのなかのいざこざにつき、他人の擬制において解決するのは関心したことではない。自分たちがその損失を引き受けるべきではないか。」という遠藤浩学習大学名誉教授の言葉を紹介し、「学説の中には「家」の感覚を残しており、取引安全を極端に重視する、かつての日本法に強かった特有の発想であろう。」と述べ、次のように続けます。
なぜ、このように母法から見ればいわば非常識な処分権を、学説は肯定するのだろうか。徳川日本の「家職国家」以来の、家業の共同経営者としての伝統がもたらした文化があるのかもしれない。個人財産制でなく家産制であったならば、夫婦はそれぞれが家を代表する存在であって相互の代理権授与は問題にならない。夫が給料をすべて妻に渡して管理を委ね、小遣いをもらうという、日本のサラリーマン家庭の文化も、かつての家業の共同経営者としての伝統がもたらしたものといえる。
しかし文化の違いのほかに、制度的な相違が大きい。(表見代理の成立を批判した)我妻説が心配したような夫の不在のケースは、妻が裁判所によって授権してもらうことが簡単にできれば、日常家事の代理権を拡大する必要はなく、現に母法においてはそのように処理されている。しかし日本では司法の関与が身近でないことが問題の根本にある。つまり、司法制度が確実に授権することによる取引の安全保障のシステムが機能していない。また裁判所や公証人の関与は、家庭内の横暴な代理人による搾取から弱者である本権者を守る機能を持つが、その機能も日本にはない。
そして、結びにおいて、水野先生は、日本の夫婦別産制は、「まるで他人間の間であるような極端な夫婦別産制」であり、家族生活を営まれたことによって生じた富が、家族の保護のためには保護されておらず、所有権者の恣意的な処分への制限もかけられていない、とその問題点を指摘されています。
来週号から、この連載記事の関連論文をご紹介します。
(この連載つづく)
【この連載一覧】
すでに登録済みの方は こちら