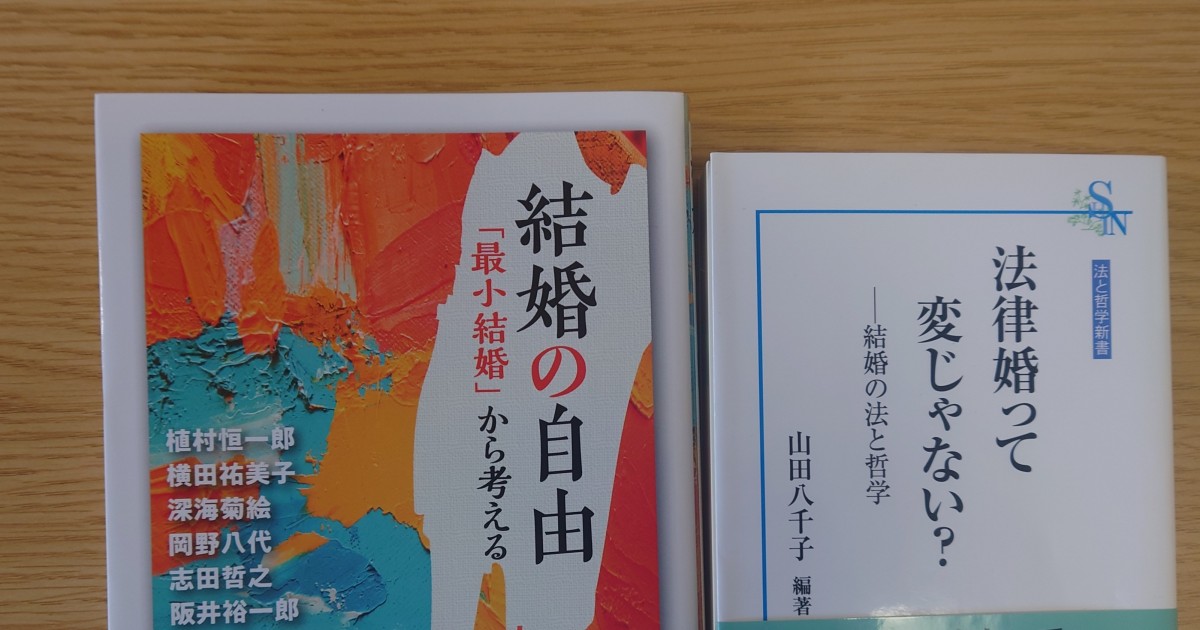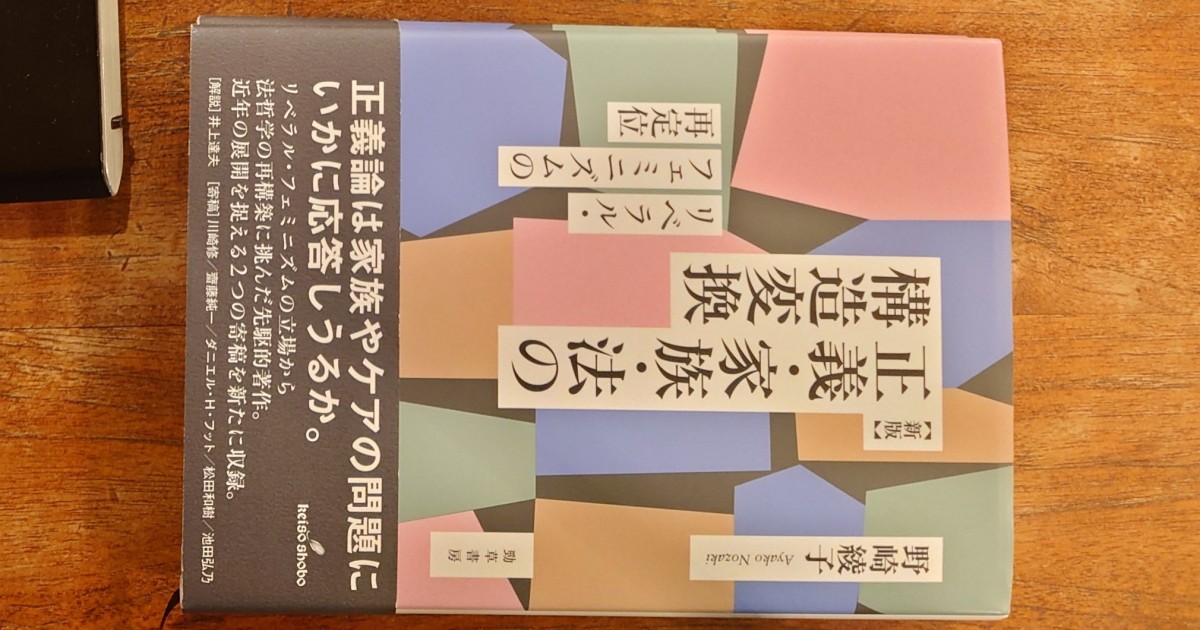水野家族法学を読む(24)「不貞行為の相手方に対する慰謝料請求権①」
【前回】
前回、ご紹介した不貞行為の相手方に対する慰謝料請求権について、水野先生は、「法学教室」2021年11月号において、ご自身の文献を3本紹介されています。
順に読んでみることにしましょう。
<参考文献①>
「最高裁昭和54・3・30判批」法学協会雑誌98巻2号291-318頁(1981年)
※水野先生のHP上では、「「夫と同棲した女性に対して妻または子から慰謝料を請求できるか」最高裁昭和54年3月30日判決評釈」という名称で掲載されています。なお、当該文献の表題は、「東京大学判例研究会「最高裁判所民事判例研究」」です。
それは本当にきちんと考察されていたのか?
「法学教室」の連載記事上でも概略は取り上げられていますが、最判昭和54年3月30日の事案は、不貞行為の相手方に対し、一方配偶者の子からの慰謝料請求が認められるか、というものです。
この判例批評では、冒頭、嚆矢となった判例、大審院決定大正15年7月20日の評価をめぐる、中川善之助と牧野英一の論争を詳しく紹介しています。
これは、妻から依頼された被告人が、夫の不貞行為の相手方に対して損害賠償を要求し、手切金や養育費として金銭を受領した行為について、恐喝罪に問われたものですが、大審院は、夫にも貞操義務があることを明らかにしたうえで、妻の損害賠償請求権を行使した被告人を無罪とした大審院の判断について、中川(否定説)と牧野(肯定説)は、いわゆる「妻権」が確立されたか否かをめぐって、激しく議論を戦わせました。
水野先生は、戦前の学説状況について、次のように整理されています。
第一に、夫の不貞行為について妻がその相手の女性に慰謝料を請求するという事件は現実にはほとんど存在せず、この判決は極めて異例な事案に関するものだったということ、第二に、夫の貞操義務の存在自体が疑わしいほどの圧倒的に夫婦不平等な法体系の下で、夫婦平等という理想をめざす者にとって、この判例は輝かしい思想的価値をもつものであったこと、したがって、第三に、この判例法理の成立においては、配偶者の不貞行為の相手方に対する慰謝料請求という法理の本質的な問題については深い吟味がなされないまま、当時の感覚では当然のものであった夫の請求権が、いわば機械的に妻にも拡大されたものであったといえること、などである。
そして、水野先生は、戦後改革の中で、この点の考察が抜け落ちたことを、次のように表現されています。
姦通罪を夫婦ともに否定することで夫婦平等を達成したように、夫にも妻にも請求権を否定することで夫婦平等を図るべき性質のものではなかったかとも考えられる。ともあれ、この判例法理は、一切明示的にとりあげて論じられることはないまま、戦後に承継されることとなった。
そして、当初、ほとんど存在しなかった妻からの請求が、戦後の権利意識の向上とともに増加を見せ、昭和37年、画期的な事件が登場しました。(東京地判昭和37年7月17日)。
この事件は、原告の夫や被告となった女性の社会的地位が高く有名人であったことでも世間的に騒がれた事件であるが、この判決について中川善之助博士が妻子の請求権を強力に支持する論文を書いたことが、この種の判例の展開史上で大きな意味をもったのではないかと思われる。
中川の論文は、戦後になってこの種の法的問題を論じたものについて、「ほぼ初めての学説」であったにもかかわらず、中川は、戦前自身が否定していた妻権を認めるばかりか、肯定説を戦前から一貫した法理であった、とすらしています。
水野先生は、この中川の「転向」を、自身の過去の論理からして、もっとはっきり論じるべきだったと批判されています。
この中川論文の登場後、戦後長い間、不貞行為の相手方への慰謝料請求権は肯定説が一般的であったものの、近時(1981年のことです。以下同じ。)否定説とまではいかなくても、無条件に肯定しない説が現れた、としています。
また、諸外国では西ドイツ(当時)やイギリス、アメリカなどで、判例法理として否定されたり、立法でこうした訴訟形式を廃止したことなどを挙げ、次のように指摘されます。
以上のような判例や学説の展開の背景には、婚姻外の性関係に対する倫理観の推移がある。婚姻外の性関係を結ぶことに対する倫理的禁忌が、夫にとっては極めて緩やかでありながら、妻には厳しく課せられた時代から、夫にも等しく課せられる時代、すなわち夫婦平等に婚姻道徳の尊重が課せられる時代へという流れが一方にある。他方では、個人の人格や決定権の尊重、とりわけこのような最も私的な事柄においては法の介入はできるだけおさえて個人の判断にまかせ、多様な価値観の流動する時代に対応していくべきだという要請も次第に強まる。その要請の裏には、現代における性道徳の新しい流れがあろう。本判決が提示した問題はこのような流れの交錯点にあり、この問題についての判断は、各人の価値観のいわば「リトマス試験紙」(研究会における唄教授のことば)ともなりうるような難しいものである。
そして、水野先生は次のように続けます。
しかし、たとえ最終的には倫理的な価値判断によって決定されるにせよ、不貞行為についての倫理的な評価と、不貞行為の相手方に不法行為による慰謝料請求を許すかどうかという問題とは、いったんは切離して考えられるべきである。すなわち、不貞行為による慰謝料請求の可否は、その慰謝料請求を許すことがどのような効果をもち、それゆえになぜ必要であるのかということをまず明らかにした上で答えられなければならない。
そして、水野先生は、数多くの下級審判例を収集し、それを(ア)婚姻破綻に至らない場合、(イ)婚姻破綻に至った場合に分け、分析していきます。
そこから浮かび上がったのは、必ずしもそれが被害者の救済、法的正義の実現とは言い難い実態の数々だったのです。
それは本当に正義の裁判なのか?
例えば、(ア)婚姻破綻に至らないケースにおいては、次のような事案を紹介されています。
-
妻が17歳の少年を誘惑した結果、夫がその少年に暴行して重傷を負わせてしまい、少年から傷害による損害賠償請求を牽制する意図があったとみられるケース(熊本地裁山鹿支判昭和39年11月10日)
-
夫は定職をもたないいわゆるヒモで、バー勤めの妻は被告のほかにも多数の不貞相手がいるような状況における、夫からの請求。(横浜地判昭和48年6月29日)
-
夫が独身であると被告をだまして関係をもち、被告に支払われた慰謝料・子の養育費を取り戻す目的で起こされた妻からの請求。(福岡地判昭和25年1月19日)
-
被告が夫に子の認知を要求したことに対する妻からの対抗措置(大阪高判昭和44年6月24日)
-
夫に強姦された女性の損害賠償請求訴訟に対抗して妻から起こされた、いわゆるスラップ訴訟の事案。※請求は棄却(山形地判昭和45年1月29日)
-
不貞行為の当事者の死後、不貞行為の相手方への訴訟(千葉地判昭和49年12月25日ほか)
そして、水野先生は、次のように論じます。
以上のような、不貞行為が婚姻破綻をもたらさなかった類型の事案について、慰謝料請求を認める必要があるだろうか。たしかに、たとえ婚姻破綻に至らなくとも不貞行為によって配偶者たる夫または妻の精神的平和は乱されたであろうし、配偶者の死後、あるいは離婚した後で発覚した場合にも精神的苦痛をおぼえるかもしれない。また不貞行為の反倫理性を強調すれば、あくまでも慰謝料によって制裁すべきであるという立場も成立しうる。夫権の侵害として大審院が不貞行為による慰謝料請求の法理を成立させた当時には、あるいはこのような価値判断が根拠となっていたのかもしれない。しかし、この法理を擁護する近年の学説の論拠は、むしろ婚姻破綻の場合の残された配偶者の救済に力点が移行してきているように思われ、婚姻生活が継続している場合にも配偶者の精神的苦痛を賠償するために慰謝料請求を認めるべきことを積極的に強調するものは見当たらないようである。同P.304
そもそも、他人の行為によって精神的苦痛を味わされれば当然に慰謝料が請求できるというものではもちろんない。不法行為という構成によって慰謝料が認めるには、それだの理由がなければならない。最終的には前述した価値観によって決せられる問題といえようが、不貞行為の反倫理性を重く考える価値観によるにしても、慰謝料による制裁を認めたことで不貞行為が減るかどうかははなはだ疑問ではあるし、婚姻関係が安定するという根拠は乏しいように思う。研究会の席上では、この慰謝料を否定すると権利意識にめざめた妻が夫のいわゆる二号を訴える途もふさぐことになり、妥当ではないという意見が主流であったが、前述したような下級審の事例の他には、夫と平穏に婚姻共同生活を営みながら二号に訴えを起こす妻の存在はちょっと考えにくいし、仮にそのようなか訴えをおこす妻が出てきたとしても、夫の不貞行為を糾弾するためには、夫に離婚を要求する途をとるべきであろう。夫の不貞行為には泣きねいりをする妻という悲劇をなくすには、妻が経済力をもち(もしくは充分な離婚給付を得て)、離婚したければできるようにするようになることが先決であり、その上で妻が夫に対する愛情ゆえに夫に離婚を要求することができず、夫の不貞行為を宥恕してその苦痛に耐えることを選ぶならば、法はもはやその選択に関与すべきではないし、まして夫の不貞行為の相手方に慰謝料を請求することも認めるべきではないと思われる。同様のことは、妻の不貞行為に対する夫の態度についてもいえるであろう。配偶者の人格を尊重することと、配偶者の愛情が移った異性に対して慰謝料請求することとはたがいに矛盾するのではないだろうか。むしろ逆に、妻の不貞行為の相手の男に対する恐喝に、慰謝料請求権の行使として法的根拠を与えるような結果になりうることや、高度に人間性の尊厳にかかわる性の問題に金銭を対価としてもちこむことの方が、ある意味では反倫理性が高いと思われる。
そして、次のように結論します。
結局、筆者としては、配偶者が自由意志で不貞行為をした場合は、その相手に対する慰謝料請求は一切否定すべきであろうと思う。
そして、この結論は上記(イ)婚姻が破綻した場合においても妥当する、と水野先生は考えます。このケースでは、「その破綻自体による損害が発生し、その損害は時には配偶者の生存の基礎を奪うほど大きなものとなる」ことは認めつつも、法の関与できることは、婚姻破綻による経済的困窮の救済だけだとし、「この場合に法が関与すべきであるということは、第三者である不貞行為の相手方に対する慰謝料請求権を認めることとは直結しない」と主張されます。
そして次のように述べます。
婚姻破綻によってもたらされた窮状の救済は、第一義的には配偶者間で行われるべきものであり、そのために婚姻費用分担制度や財産分与制度などがあるのである。なぜなら、まず婚姻破綻は直接的には配偶者の意思決定によるものである。また、婚姻破綻に至る過程には、夫婦間のさまざなな作用・反作用の積み重ねがあり、それを不法行為として法的に評価するとしても、他人間に働く一般不法行為の法理とは異なった基準や原理が働くはずである。むしろ、夫婦間の不法行為の多くは一種の不法行為の擬制とみるべきであろう。それは実質的にはすぐれて婚姻法の領域の問題であり、またそれにふさわしい制度(家庭裁判所や調停・審判制度)が設けられているのである。そして、不貞行為、つまり夫婦の貞操義務違反の問題は、まさにこのような婚姻法の領域でえ扱われるにふさわしい、またそれ以外では扱いえない問題ではないだろうか。不貞行為が婚姻制度の安定を害し人倫に反するものだとしても、また、愛情をめぐる葛藤が、当事者の心に深く癒し難い傷を残したとしても、その慰謝料による制裁が可能なのは夫婦間においてだけであろう。
そして、評釈の題材となった、最判昭和54年3月30日の最大の争点、子から不貞行為の相手方への慰謝料請求権も、上記の論理から否定されます。
愛情に満ちた幸福な家庭ではぐくまれる権利をすべての子が享受することは、家族法が究極の目的とする理想である。そしてその達成のために、法はもちろん、あらゆる分野の政策における努力が要求されるだろう。しかし、親の離別による子の不幸を、不法行為を構成して慰謝料で賠償させるのは、この目的達成のために妥当な途ではないと思う。
こうした、徹底した水野説の否定の論理は、不貞行為の被害者を単純に「かわいそうな被害者」という視点だけでは見ない、複眼的なものがあります。
そして、その背景には、当事者間の法律関係を整理して論じるだけではない、別の理由があったのです。
次週、別の論文でその点を読み解いてみたいと思います。
(この連載つづく)
【連載一覧】
すでに登録済みの方は こちら