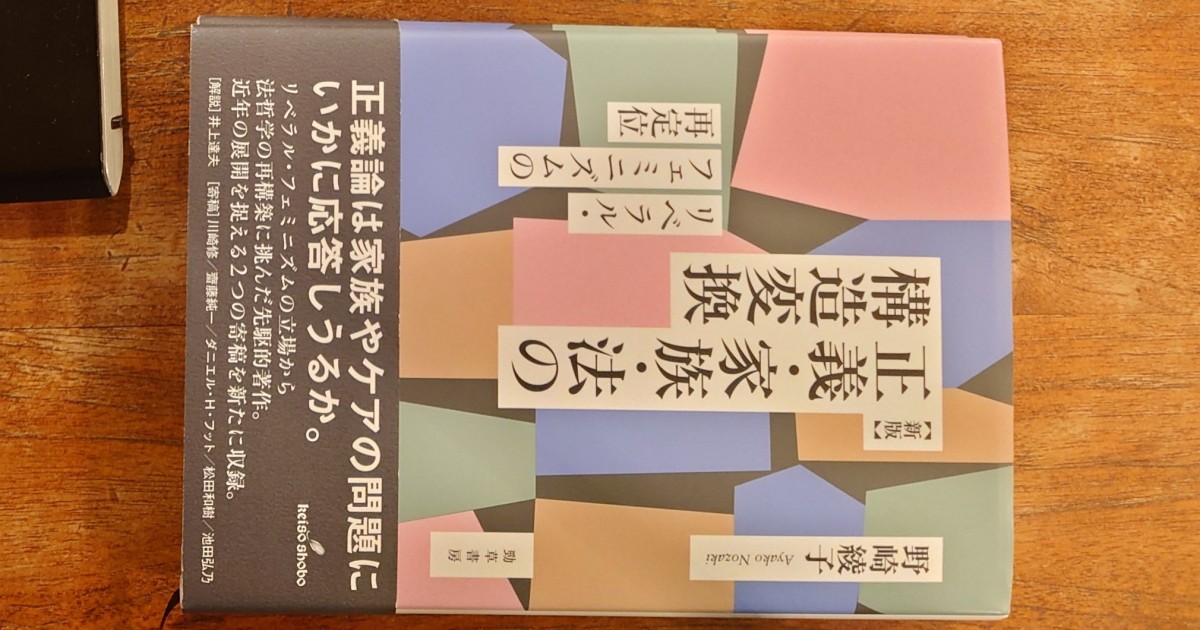水野家族法学を読む(35)「"最小結婚論"が突き付けるもの」
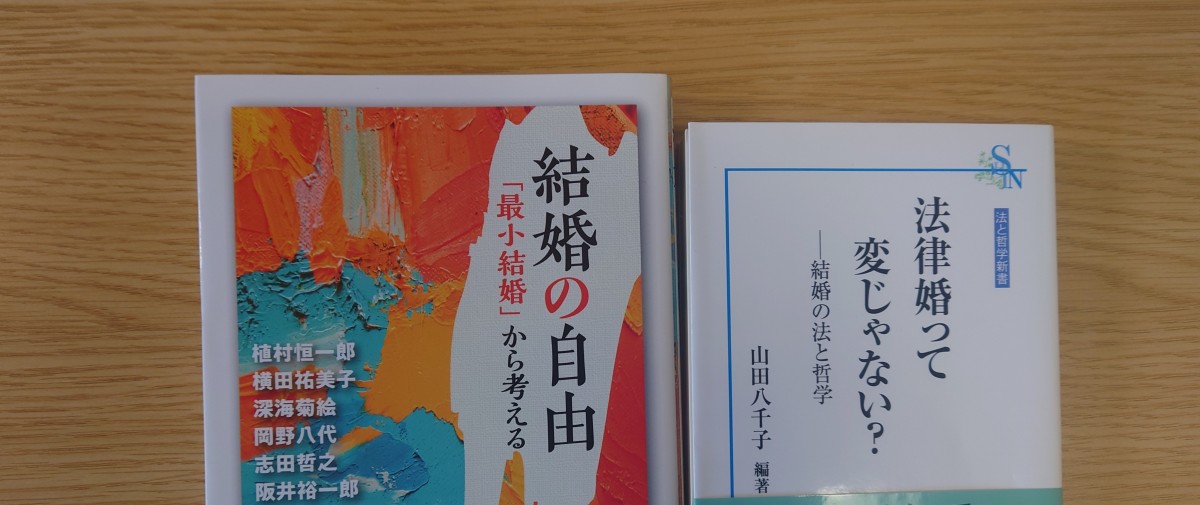
今回ご紹介する2冊をパチリ
「フランソワ殿、私を軽蔑しておられますか。結婚にしがみついたりして。」
<前回>
結婚と離婚-現行法をプラティカルに再定位する水野説
ここまで、水野先生の結婚と離婚をめぐる論考を、本連載第14回から、20回かけて追いかけてきました。
-
日本の婚姻制度は、西欧諸国と同様、第一義的には、次世代(子ども)を育む(繭)の機能を持つものである。そのため、水野説は婚姻成立の厳格性を重視し、婚姻意思の追認を容易に認めない。
-
しかし、日本の婚姻法・離婚法は、これまでの水野説の紹介で繰り返し述べられてきたように、日本の家族法の「弱さ」が典型的に表れている場面の1つである。法は、婚姻時の経済関係や離婚給付等の経済的な面で、弱者(多くは女性や子ども)を保護するものとして機能していない。
-
また、現実の離婚の9割が協議離婚によるもので、公正な基準に基づく国家の法的介入が行われていない。
-
水野説では、これらの原因を踏まえて、国会による法的介入の強化を志向する。婚姻法では、その骨子として次の3つの視点を提示する。①男女(配偶者間)の平等、②夫婦の共同生活の存在(第三者に対する共同責任)、③弱者の保護である。①と②からは、夫婦の財産形成への対等な考慮が払われ、③からはその実効性の保護を志向する。
-
そのため、5の立場から、稼働能力を持つが配偶者が夫のみである場合に、夫婦別産制を貫徹しようとする最高裁判例(最判昭和36年9月6日)を批判的である。また、夫婦の日常家事代理権に民法109条の表見代理が成立する余地があるとした最高裁判例(最判昭和44年12月18日)も問題視している。
-
また、離婚法においては、その骨子として、①積極的破綻主義を拡大して早期の離婚を実現(当事者の紛争からの解放)、②迅速で公正な離婚給付の実現(扶養的要素の加味する)、③離婚後共同親権の容認(子の奪い合い紛争の早期解決と責任の重視)となる。
-
一方で、婚姻時における不貞行為の有責配偶者に対する慰謝料請求は認めるものの、第三者に対する慰謝料請求には否定的である。
-
一方で、水野説には、家族法の第一義的任務は、「家族を作り子を生み育てる環境を、安定的に確保すること」(※1)としつつ、以前ご紹介したように、民法は妥協と共生の秩序であり、短い言葉(条文)による正義の対極にあって、正義は不可知ですらあるという観念が底流に流れている(※2)。
-
そのため、弱者保護機能という絶対的に重視されべきように思われる価値ですら、この不可知性の中で相対化(厳密にはそれぞれの「正当性」をいったん承認)され、離婚後共同親権を容認するような態度(水野先生の言葉を借りれば「妥協と共生の複雑な線を引く」)を取ることになる。
家族法を、ご自身のプラグマティズムの範囲内で、プラティカルに解釈の「変革」を志向するのが、水野家族法学の真骨頂といえるのではないでしょうか。
しかし近年、その「線の引き方」の視点を、大きく揺さぶる動きがあります。「最小結婚」の論者や、婚姻=契約説論者です。
ブレイク教授「最小の結婚」の影響
まずその嚆矢となったのが、上記リンクにエリザベス・ブレイク(ライス大学教授)の「最小の結婚」(白澤社 2019年※原著は2012年)でしょう。
ブレイク教授の主張は、現在の婚姻制度は異性恋愛に基づく延長形態として制度化されているものと捉え、これを人と人が互いにケアし合う関係性の制度に転換するべきだ、とするものです。(※3)
結婚の要素は愛ではなく、ケアであり、パートナー関係と出産・育児の保護を切り離す。ポリアモリー(同時異性恋愛)すら容認する主張は、アカデミズムを中心に大きな議論を巻き起こしていると認識しています。(※4)
この議論の方向性は2つあって、1つは「婚姻を特別扱いすること自体に対する揺さぶり」と、もう1つは「婚姻の効力を強化する方向性に対する揺さぶり」です。
池田弘乃教授の疑問
まず1つ目の揺さぶりとしてご紹介したいのが、池田弘乃山形大学教授の主張です。(※5)
その論旨を私なりにまとめると、次のようになります。
-
結婚が重要な制度であり、かつ、よい制度であるという前提自体を疑ってみる必要がある。
-
日本の婚姻法は、(これまでの連載でみてきたように)弱い当事者を保護するには、弱い機能しか持っていないにもかかわらず、近年、同性婚訴訟において裁判所は、あたかもそれが重要でよい制度であるかのように繰り返し言明しているのは矛盾ではないか。
-
親密な関係といっても子供の有無や人数、性的関係の有無、ケア労働の提供の有無、多くの差異が家族ごとにみられる。最小結婚論をさらに押し進めるならば、「何が結婚か」という問いから離れて、端的に法が保障する関係は何かを考えてみるべきではないか。(性愛単位や愛情単位を擁護する水野説への批判になる)
-
最小結婚、そして婚姻の契約化論に賛同するとき、国家が関与すべき事柄の主要な候補は、ケア関係の規律と公的承認のニーズ(例えば同性婚や選択的夫婦別姓)であろう。これらを婚姻制度の枠外に制度を創設するとき(例えばPACSやパートナー制度)、問題とすべきは結婚する人のために提供されるべき制度の存在自体ではなく、その硬直性や絶対性ではないのか。
-
問題なのは、マジョリティが享受している婚姻制度の奇妙さ(弱い機能の制度を神聖視すること)である。婚姻が一級品であるかのような通念をそのままにして、そこに新規参入(別姓婚や同性婚)を祝福するのは奇妙ではないのか。
-
池田教授は、婚姻(結婚)から離れた「結婚ではないもの」、つまり親密圏そのものを保護する制度の意義を検討する。ただし、それは「婚姻を一級品とし、その他を差別的な二級品としない」ことを前提とし、また、婚姻自体にも様々な婚姻形態を承認しつつ、その障壁(例えば同氏強制)の合理性を厳しく問うことは可能だともする。
確かに、そもそも婚姻に求めるニーズは人それぞれであって、いわゆる現役世代の婚姻と、リタイア世代の婚姻とを同列の価値観で論じることはナンセンスでしょう。
現代の婚姻が神聖化される背景に、いわゆるロマンティック・イデオロギー(恋愛結婚観)があると思いますが、それがそんなに「いいものじゃない」ことは、離婚後共同親権の当事者のご証言を待つまでもない話かとも思います。
岡野八代教授の指摘
そこにもう一歩押し進め、最小結婚論を、水野説が提示するような婚姻の効力の相対化ではなく、現実の不正義への適用可能性を考えるのが、岡野八代同志社大学教授です。これが「婚姻の効力を強化する方向性」に対する揺さぶりです。
そのご主張を私なりにまとめます。(※6)
まず、ブレイク教授の主張を次のように分析します。
-
ブレイク教授の主張は、結婚そのものが抑圧的なのではなく、性愛規範性が抑圧的だとするものである。
-
ロールズは、その公正な配分こそが政府の存在意義とされた社会的基本財の中にケアを含めるべきだと主張しているように、最小の結婚が国家の制度として正当化される公共的理由は成人間のケア関係である。
-
また、現在の婚姻制度が女性の社会的立場をより弱体化し、正義に悖るような不公平な家庭内の財の配分を遂行する装置である。ここに同性婚を含めるだけでは、一夫一妻的単婚への同化政策であり、合衆国の文脈では人種差別すら助長してきた。
-
にもかかわらず、ブレイク教授は結婚はこうした不正義を助長し温存するよりもむしろ、こうした不正義を乗り越えるのに役立つような形で、再構成することができると論じている。それが結婚の要素は性愛ではなく、ケア関係で再構成するということである。
-
一方で、ブレイク教授は、婚姻の私事化を否定する。それは自由を広げるどころか、むしろ社会的抑圧や市場による支配にさらされることになる。
-
ブレイク教授の主張は、リベラルな国家を構想しその介入によって過去から続く現在の不正を修正しようとする、修復的観点を見出すことができる。
-
上記のような論旨から、ブレイク教授の主張に2つの意味を見出す。1つはこれまで結婚に負わされていた宗教的・道徳的イデオロギーの根拠になっていた「再生産」が、結婚の本質ではないこと。そして、再生産が結婚から切り離されることによって、これまで国家こそが特定の人種や、同性カップル、ポリアモリー、友人関係などに対する差別を生み出し、助長し、維持強化してきたが、それと対決するという副次的効果を期待する。
そして、岡野教授は、国家の責任で時に罰則を課したり補償を与えたりしながら、その不正をただしていく必要があるだけではなく、現状の結婚を厳しく正義の枠内でチェックしなければならない、と主張するのです。
岡野教授のご主張は、国家が擁護すべき結婚のアウトラインを明確に(過度な介入の抑止)しつつ、現状の婚姻制度がもたらす社会的不正義について、明確にターゲット(偏向的な宗教的・道徳的イデオロギーがもたらす差別や社会的抑圧、当事者間の不公平に基づく支配や暴力、市場の操作等)を絞って、厳しい法的チェックを求めていく点で、水野教授の「正義の不可知性」の観念とは正反対に位置づけられるものです。
なお、ブレイクブレイクが参照したロールズの議論を家族法・契約法に適用する射程については、若松良樹学習院大学の論考においても、税法や相続法にまでリーチする、興味深い議論を展開されています。(※7)
弱者の保護の「あり方」の違い
ここで改めて、水野先生と、池田・岡野両教授との異同点を私なりに分析したいと思います。
-
家族法に弱者保護の機能を付与することについて、3名の学者の考えに大きな違いはない。家族形態の多様性を承認することについても、水野説は、それを法律婚に取り込むことに消極的であるものの、現行の法律婚とさほど異ならない開かれた制度が、広い範囲で平等に形成される、という効果を志向している点で、池田・岡野両教授との方向性は共通している。
-
一方、その実現の理路は決定的な違いがみられる。まず、法律婚に優越的な地位を付与することに水野先生は好意的といえるが、池田教授は否定的にとらえる。また、統合的な社会正義の理念を家族法に取り込むことにに水野先生は消極的であるが、岡野教授は積極的である。
水野家族法学の魅力というのは、卓越した現実への対応力と、家族法を体系立てて理論化することを高いレベルで融合させていることにあると思います。しかし、そのプラグマティズムが守ろうとしているもの・実現させようとしているものと、「実際に実現している現実」には相当な乖離が常に存在しています。
例えば、この記事をご覧いただければご理解いただけると思います。
一方、池田・岡野両教授のご主張は、従来の家族法学の主流的な考えに大きな揺さぶりをかけるものではあるものの、法的整合性には疑問があり、非現実的なレベルでの司法リソースを要求する点で、ラディカルで実現性に乏しいフェミニストの理想論のようにも読めます。しかし、現実の法律婚が減少というか、激減の一途を辿っている今、従来の家族法学の延長線では、現実の法律婚制度がメルトダウンするリスクは確実に高まっているきています。池田・岡野両教授の構想を、家族法学の側が真剣に考慮すべき時は迫っているようにも思えます。
最小結婚論の日本法への応用可能性
さて、最小結婚に好意的な立場の論者は、「離婚」についてはどのような姿勢を取るのでしょうか。
実は、最小結婚の関連論文のほとんどで、「離婚」についての言及はあまりなされていません(※8)。
当のブレイク教授本人は、「最小の結婚」の第1章で「離婚は約束の破棄なのか」という問題提起をして、詳細に論じています。そこでは、婚姻時の誓いは、それが「愛」に関わる限りは(法律上の)約束ではない、と主張しています。また、第8章で最小の結婚を実現する課題点として離婚時の財産分与の公平性を論じていますが、その結論はシンプルなもので、結婚を対等な契約化をすれば、公平な財産分与による「退出」が可能になる、というものです。
何事も私人間の契約を尊重する、英米法圏の方らしい発想といえます。
日本法への応用可能性を私なりに考えてみます。
既にみてきたように、ケア関係の規律に、国家の(最低限度の)介入を支持するということは、対等な「関係の解消」にも介入するというのが論理的です。 そして、最小結婚論の立場では、婚姻の解消と親子関係の解消は、多様なケア関係を前提にするため、一律な法的パッケージではありません。そのため、親権者の決定や、離婚後共同親権(単独親権)を行使可能な範囲、養育費の支払義務の存否等は、必ずしも論理的に自明なものではありません。
ブレイク教授自身は、子どもの養育については社会が直接的な責任を有することを承認することを可能にする、と論じています。これは、欧米の法制度が親子関係の不分離、つまり、親の子に対する養育責任(ケア責任)を徹底することが建前であるが、最小結婚論によって、その「ケア責任の重さ(さらにいうならその重さから生じる様々なひずみ)から個人の解放」を志向しているように読めます。
また、岡野教授が主張するように、最小結婚論という構想が修復的正義(不正義の是正)までをその理論的射程に入れている場合、法は家庭内の弱者保護機能を強力に有するものになります。となると、最小結婚論の立場では、パートナー関係の解消(離婚)時において、経済的に対等な関係解消や子の養育へのケアなど、多大な司法リソースを投入しなければならないはずです(実際に欧米各国の司法予算は多大である)が、最小結婚に好意的な立場の研究者からは、そのことにあまり関心がないように見受けられます。
結局のところ、「最小の結婚」という、一見リバタリアニズムに親和的に思える構想とはうらはらに、それを長期にわたってフェアに運営するための国家の公的介入は、強力かつ広範囲に行われなければならないように予想します。
やはり、それが可能なのは、提唱者のブレイク教授には、欧米流の司法制度のイメージが根底にあって、日本のような司法制度をイメージしていないからではないでしょうか。
結婚にしがみつかない設計の欧米法と、しがみついてしまう設計の日本法
冒頭、直木賞を受賞した中世の法廷サスペンス「王妃の離婚」の一節を紹介しました。
この作品は、結婚の無効取消をめぐる史実の裁判が題材で、この物語のヒロイン、フランスのジャンヌ王妃は、夫ルイ12世からの不当な離婚要求を拒否し、辣腕弁護士フランソワを立て、政治的に危険な裁判を戦います。
ところが、ジャンヌ王妃は、あるきっかけで結婚という頸木を自ら断ち切り、離婚(厳密には婚姻の無効)を決断して、新しい人生に踏み出していきます。弁護士フランソワの優れた交渉術で、広大な領地と法外な終身定期金を分捕り、「これでは離婚する意味がない」とフランスの大臣を嘆かせました。史実では死後聖人に列せられたジャンヌ王妃ですが、不当な離婚請求の代償をきっちり払わせたわけです。
法制史的にいえば、フランスに近代的な離婚制度が生まれるのは、この物語の約300年後、1792年です。そこからさらに200年以上かけて、フランスは、紆余曲折の末、男女の平等や弱者保護の法整備を進めてきました。だが、21世紀の今になっても、法は十分ではなく、まだまだ議論が続いています。
「自由・平等・博愛」が曲がりなりにも国是の国で、「公正な社会とは何か」という、議論を進めて行く社会的土壌(合意)が存在するからでしょう。結婚にしがみつかなくても安心して手放しても大丈夫、という法の伝統がそこにはあります。
一方で、日本はどうなのか。脆弱な司法でよしとされ、弱者の保護が弱い社会で、有責性をめぐって長い紛争が戦われる。いったん踏み切った結婚を、スティグマ(社会的烙印)を押されることなく安心して手放せるだけの土壌がまだまだ欠けている。
まず、その現実と向き合う必要があるように思います。
<今回ご紹介したい本>
<この連載一覧>
〔脚注〕
1 水野紀子「戸籍制度」ジュリスト1000号(有斐閣 1992年)171頁。これ自体は水野先生の独自説ではなく、近年の同性婚訴訟において、下級審が繰り返し類似の言明をしている。
2 水野紀子「家族法の弱者保護機能について」鈴木禄弥先生追悼・太田知行・荒川重勝・生熊長幸編「民事法学への挑戦と新たな構築」(創文社 2008年)677頁
3 ブレイクの論旨については、植村恒一郎「「結婚」に求めるものは、「人それぞれ」ー『最小の結婚の主要論点』(所収:植村ほか「結婚の自由ー最小の結婚から考える」(白澤社 2022年)に詳しい。
4 瞥見の限り、前掲2の書籍のほか、「法と哲学」第9号(信山社 2022年)の特集、2023年の家族問題研究学会のシンポジウム、2024年の基礎法学系連合学会のシンポジウム(法律時報97巻3号に詳細な紹介がある)、2025年関西倫理学会シンポジウム等を確認することができる。
5 池田教授のご主張は、「婚姻の契約化と婚姻廃止論ー婚姻法と親子法の幸せな「離婚」は可能か」法律時報97巻3号(日本評論社 2025年)74-78頁、「「結婚でないもの」とは何か」(山田八千子編「法律婚って変じゃない?」(信山社 2024年)223頁以下)に拠った。
6 岡野教授のご主張は、「「結婚」はどこまでも必要なのか?ーケア関係からの照射」所収:前掲3の書籍123頁以下に拠った。
7 若松良樹「ロールズにおける家族法と契約法」前掲5の書籍149頁以下
8 最小結婚と離婚法との関係を論じる論考は、管見の限り存在しない。後期博士課程の大学院生の手による、フランス法とブレイクの議論を手がかりに日本の離婚法への論考が存在する。(松本薫子「婚姻法の再定位:フランス民法典の変遷から(7・完)」立命館法学404号408頁以下(2022年))
<この連載一覧>
すでに登録済みの方は こちら