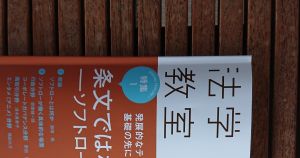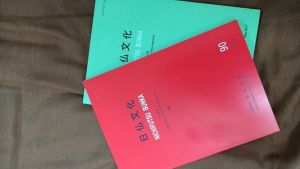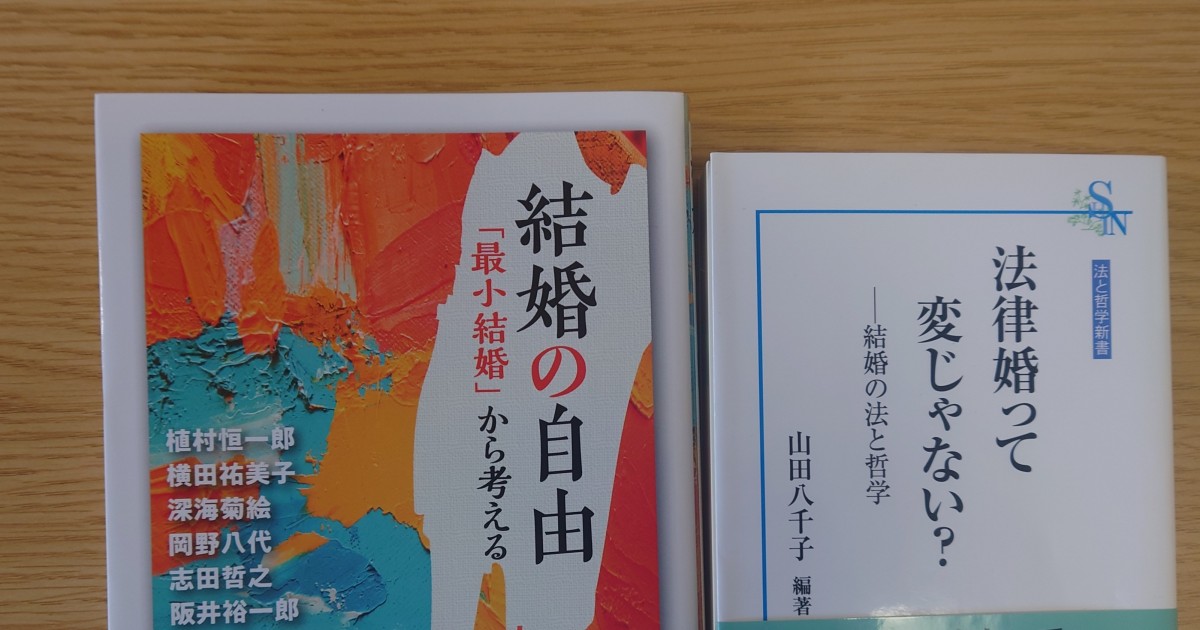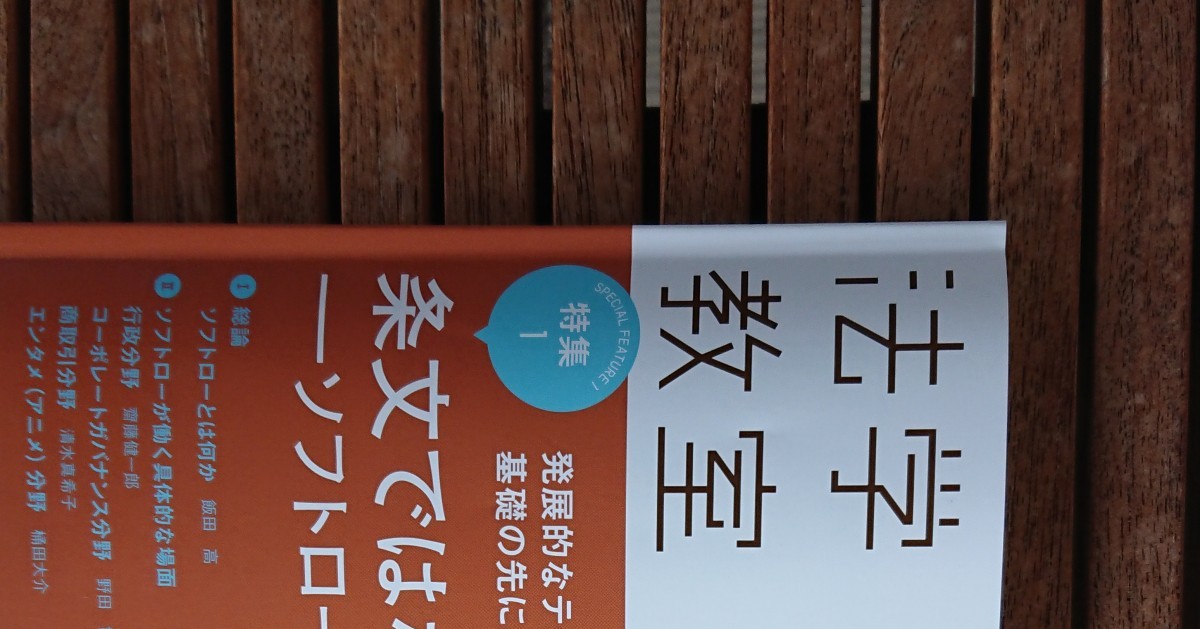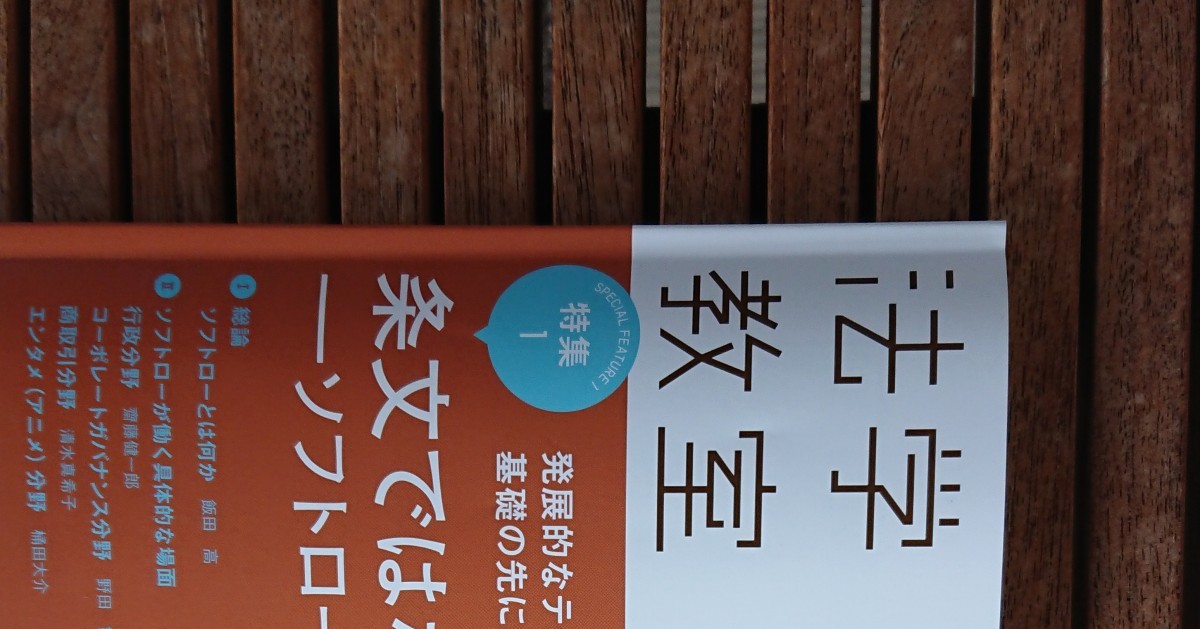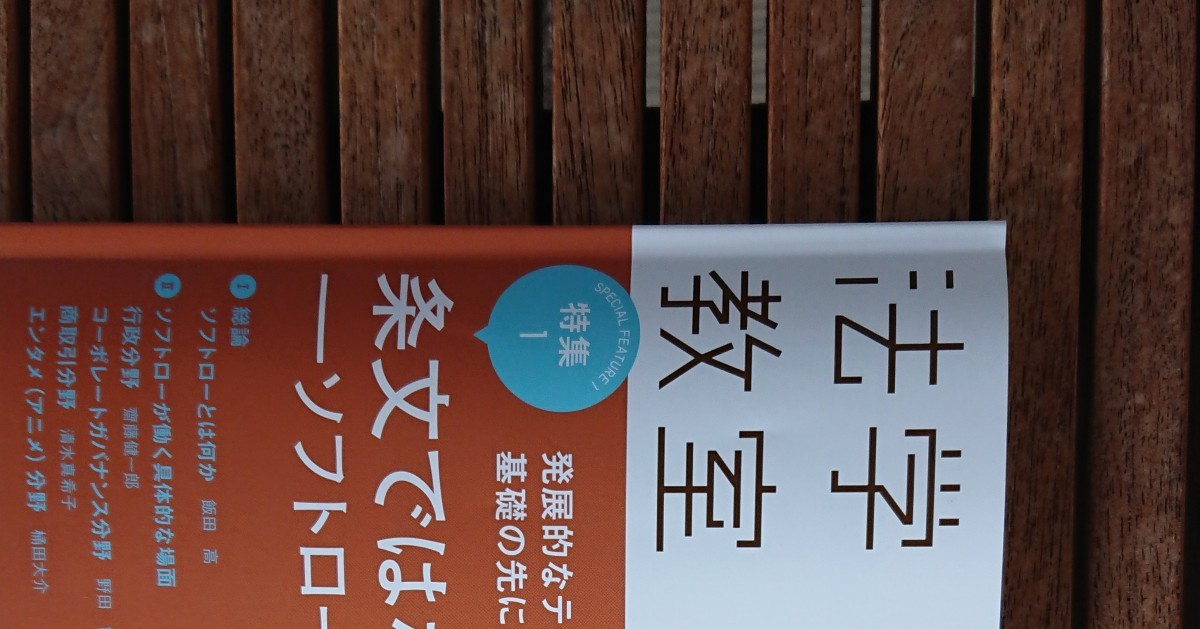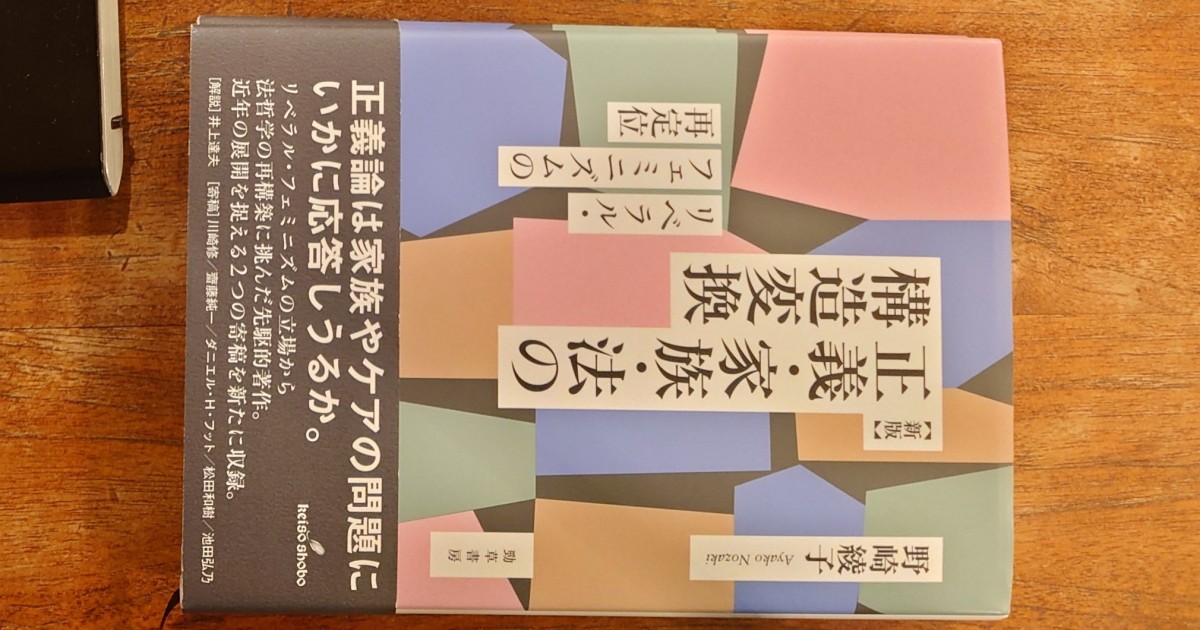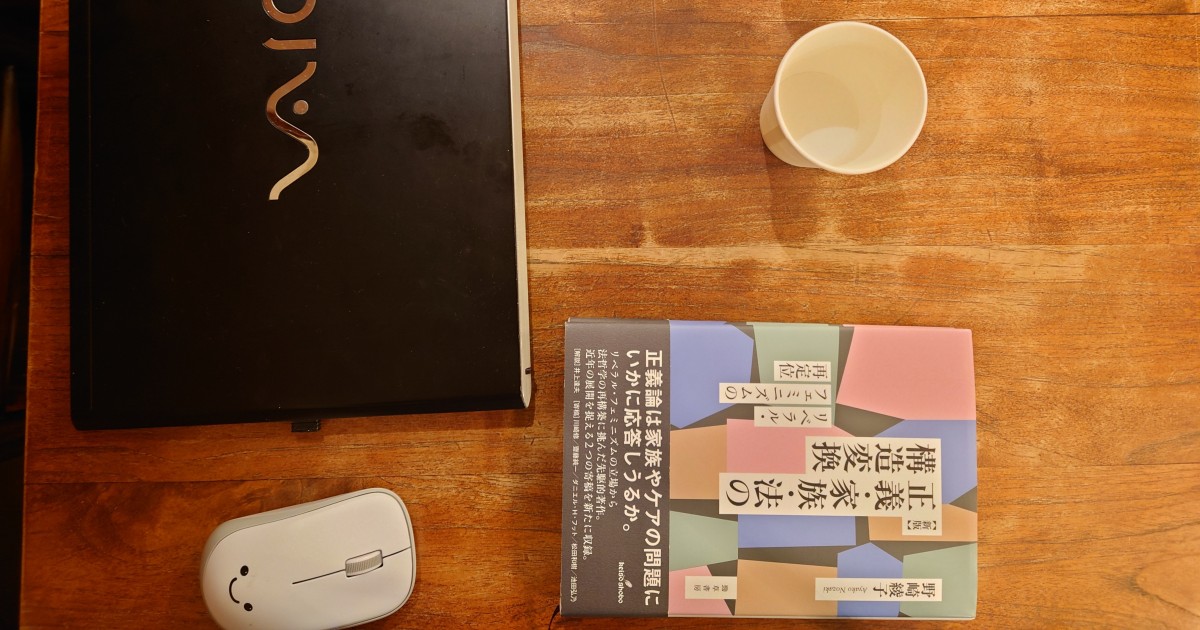水野家族法学を読む(31)「離婚/離婚訴訟に関する法的規整を考える(2)」
おことわり
本稿は、2022年6月26日に配信した、「水野家族法学を読む(30)「離婚/離婚訴訟に関する法的規整を考える(1)」の続きからスタートします。
これまでの経緯を書こうかとも考えましたが、それは本対談を全部ご紹介しきってから、お話しした方が良いと考えました。
これまでのあらすじを追いたい方は、以下2つの記事をご覧ください。
<参考文献>
対談「離婚訴訟、離婚に関する法的規整の現状と問題点」判例タイムズ1087号4-39頁(2002年)
※対談者の肩書は当時のもの。また、条文等は参考文献掲載時の法令です。
離婚原因の審理をめぐって
(前回の続きから)
ここから、話題は離婚訴訟における争点の限定の話題にシフトします。
まず、話題に上がったのが離婚原因の審理について、瀬木裁判官が切り出します。
確かに、自分で今回、最近三年間の離婚訴訟の判決だけを抜き出して読んでみて、あんまり興味深く読めないなというか(笑い)、フラットだなというか、事実がべったり物語的に認定されていて、その意味で通常の判決とは随分形が違うなとは思いました。
ただ、その物語という点なのですけれども、まさに離婚訴訟の場合に、点でとらえるのが難しいところがあると思うのですね。一つ一つの行動を点でとらえるのが難しいと。例えば七七〇条一項の事由でも、一号は不貞、二号は悪意の遺棄ですけれども、不貞は間接事実の積み重ねから推認するしかないことも多いし、悪意の遺棄は非常に評価的な概念なので、いずれも、ある点だけを取って評価、判断することは難しい、かなり長いスパンを取って事実を全部とらえてゆかないと評価ができないし、当事者の納得も得られないというところがあると思います。そういう意味で争点をきっちり限定しにくいのが離婚訴訟の悩みだということです。ましてや五号となると、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」というかなり無限定な条文で、しかもそれに有責的破綻主義とその限界という解釈上の問題がかかってくるわけですからね。
それと、当事者の感覚として、裁判官に全部を聞いてもらいたいということは、日本の離婚訴訟の場合にはありそうですね。新民訴で陳述書に基づく時系列的な尋問をやるわけで、それは、通常の訴訟では争点にフォーカスが絞られてとてもいい機能を果たすのですが、離婚訴訟の場合は、双方の、水野さんの言葉を借りて言えば「自分の側からの物語」というものが述べられて、そして相手の物語も聞いて、場合によっては反発し、場合によっては相手の気持ちがわかりあきらめる、あるいは、裁判官が自分の立場を理解してくれたと考えるか否かによってその判断に服するか否かを決めるというようなことに、もしかしたらなっているのかもしれない。
そして、法律論を少し超えた部分、まさにさっきの言葉でいけば、上位の判断者としての判断的な部分が離婚訴訟にはあるので、若い裁判官にとっては適正な事実認定と判断をするのが比較的難しい類型の事件であるということは言われているようです。
ここでやり取りは、ヨーロッパにおける離婚原因の条文適用に移ります。瀬木裁判官は条文上は、フランスやドイツの有責事由もあまり限定していないようにみえることを指摘しますが、水野先生は、"条文の解釈の仕方"が限定的であることを指摘したうえで、次のように説明します。
水野 従来、離婚事由の理解とか、過酷条項の理解とかを、それらが母国で果たしている機能や実態よりも、とかく日本人の感覚に近づけて理解する、という傾向があったのではないかと思います。ドイツ離婚法に過酷条項があっても(BGB§1568)、何年に一度も使われない例外的なもので、日本の裁量棄却とはまるで違いますし。離婚事由の立証は、その事由事実の立証そのものであって、日本のようにそれがいわゆる「相対化」されたり、点が線になって物語になることはありませんよね(笑い)。
瀬木 なにしろ五号の作り方がすごく広いことになっているので、それに見合ったということも言えるかもしれないのですが、結局、水野説は、条文批判でもあるわけですか。
水野 もちろん離婚法の七七〇条の条文に対する批判はあります。全体の作りが穂積案をもとにしています。穂積先生は、有責主義の離婚事由が限定列挙されることの意味を評価されず、大岡裁きをめざされましたから。
この水野先生の「大岡裁き」批判は、これまでの本連載(水野家族法を読む)の中でも紹介してきましたが、ここでも、水野先生は判断基準の公平性が担保されないこと、具体的判断が裁判官の個人的傾向に依存することを指摘したうえで、次のように述べます。
離婚後共同親権への発想の萌芽
実務家との共同研究会の機会に、家裁の経験豊富な判事から愚痴をきいたことがあるのですが、子供の奪い合いで、この母親にはとても任せておけないと父親に親権を与える審判をすると、高等裁判所でよく覆されてしまうのだそうです。高裁の男性判事は、自分が子育てをするということが夢にも考えられないので、確かにものすごく問題のある母親ではあるけれども、でも、やっぱり母親だとしてしまうのだ、とその家裁判事は言っておられました。そういう裁判官の傾向の問題性ということが、この家庭内の領域の問題には大きくあるだろうと思うのですね。妻が家事全般をするのが当たり前だと考えながら判断するのか、それともそのこと自体に対してまた違う評価の仕方をするのか、それによってもずいぶん違うでしょうし。
たしかに子供の問題はあります。子供の問題は、対審構造の紛争対象とすることに一番相応しくない問題で、両親に自己発見して譲り合ってもらわなくては困ります。
子供の処遇については、まさに両当事者が対立しないで協力してもらわなくてはならない問題ですから、それに相応しい手続をどう切り離して別建てにしていくかが問題になる。
2021年9月に、筆者(foresight1974)は、当メールマガジン上において、水野先生はかつて離婚後共同親権導入論者だった時、「子の奪い合い紛争を解決するため」であったことを指摘しました。
本対談が行われた当時、存在していたといわれる「母性優先原則」について、水野先生は目の当たりにしていたことが分かります。そして、この時点においては、かなり牧歌的な共同養育論者であったことも分かりますね。
その後、縛るルールの是非について、大陸法や英米法の例を挙げられながら、二人の対談は進んでいきますが、水野先生が辛辣な調停制度批判を繰り広げます。
辛辣な調停制度批判
縛るルールのない大岡裁きは、裁判だけではなくて、調停のルーツでもあるような気がします。北村一郎先生の最近の論文(北村一郎「訴訟モデルと調停モデルとの対照に関する比較法的一試論」新堂古稀所収)にも、清代の中国の裁判手続、つまり調停役の地方官が「情理」を規範として「説得と強圧」を繰り返す手続と、フランスの裁判手続とを対比させ、日本をその中間に位置づける見方が示されています。一般論としてのADRの評価をしようとは思いませんが、私が家事調停に批判的なのは、そんなルーツを感じるからかもしれません(「民法典の白紙条項と家事調停」家族〈社会と法〉一六号)。
滋賀秀三先生の『中国家族法の原理』を読みますと、集団の中の秩序維持をする方法が、西欧法のルール依存の方法と、まるで違うのですね。その集団に属したければ自ずから紛争はおさめなくてはならないという構成員への圧力が基本です。そして集団の規律内部では、何らかのチェックアンドバランスはある。中国の女性の地位は低いものでしたから、妻には離婚請求権はなくて、妻に対する虐待ももちろんあるのですが、最後の最後に彼女には武器があって、その武器は自殺をすることなのですね。妻が自殺をすることによって、婚家先は途端に集団から激しい非難を受け、妻の実家からは莫大な金額の賠償金を要求されることになる。いじめ過ぎて死なれると大変なサンクションが待っているから制約が働く。こういう秩序維持の方法は、集団の拘束力が失われた現在ではもちろん無理ですし、そもそもこの方法では、女性を守れません。もちろん今の家裁の家事調停がこんな古い中国の裁判だといっているわけではないのですが、ルーツの発想は似たものだったのではないか、と、人事調停法以来の歴史を見ても、思えるのです。
ここで、瀬木裁判官から「調停の話はまた後のほうでしていただくして...」と促されますが、水野先生の話は続きます。
調停論に話がそれてしまって申し訳ありませんでした。日本の戦前からの展開をふりかえりますと、集団の中で紛争を抑え込んでしまうという役割を持った調停が根底に流れているような気がして、その発想が日本の離婚訴訟のあり方にも、離婚調停のあり方にも、ずっと影響を与えていたような気がします。
この調停制度批判は、離婚当事者の皆さんにはとても「刺さる」話ではないでしょうか。
刺さらなかった瀬木裁判官の指摘
上記の水野先生の見解を受け止めつつも、これまでの議論を瀬木裁判官がまとめます。
そうですね、そういう面はあるかもしれません。ただ、現象的に見れば、法廷でのやり取りというものには、近代的な法廷のやり取りにしても実際には相互の物語をぶつけ合っているという部分はあるわけで、そこが程度の違いで非常に強く出ているという側面もあるように思います。実際に法廷をごらんになると、多くの離婚訴訟の尋問は、客観的な書証を中心に淡々とやっていて、お白洲的な雰囲気はそんなにないと思うのです。
私の感覚でいうと、メルクマールのゆるい限定的な消極的破綻主義の下での判断については、確かにある程度裁判官によってムラが出るかもしれないけれども、それでも、さっき私が述べたような離婚訴訟における裁判官の判断過程を考えるならば、通常の民事訴訟とそんなに大きくは違わないのではないかとも思うのです。
それよりも、水野さんの指摘に沿っていうと、審理の過程で双方が互いの有責性を言い立てることによる弊害のほうが大きいように思います。尋問が終了した段階では双方が相手に対する根本的な不信に陥ってしまうことになる場合があるのですね。まあ、だからこそあきらめがつくということも、あるのかもしれませんが。
結局、水野さんのおっしゃることは、日本の裁判官の審理方法に対する疑問というよりは、五号の無限定な定め方や、同様に無限定な部分のある消極的破綻主義それ自体への疑問、法廷で非常に広い意味での有責性を争うことへの疑問ということなのではないでしょうか。
水野先生もこれに応じます。
そうですね。たしかに裁判官の裁量性への疑問というより、この争い方の弊害の大きさが問題だというほうが、よかったかもしれません。いずれにせよ、裁判に無理を要求しているために、異常な裁判過程になってしまうことが問題です。
しかし、20年近く後になって、水野先生が「法学教室」に連載を掲載している時点においても、裁判官の傾向を批判する点は変わっていないところからすると、この時点での瀬木裁判官の指摘は、水野先生にはあまり「刺さらなかった」ということかも知れません。
(この連載つづく)
【連載一覧】
すでに登録済みの方は こちら