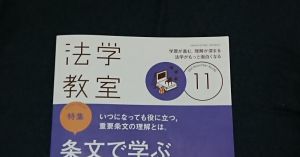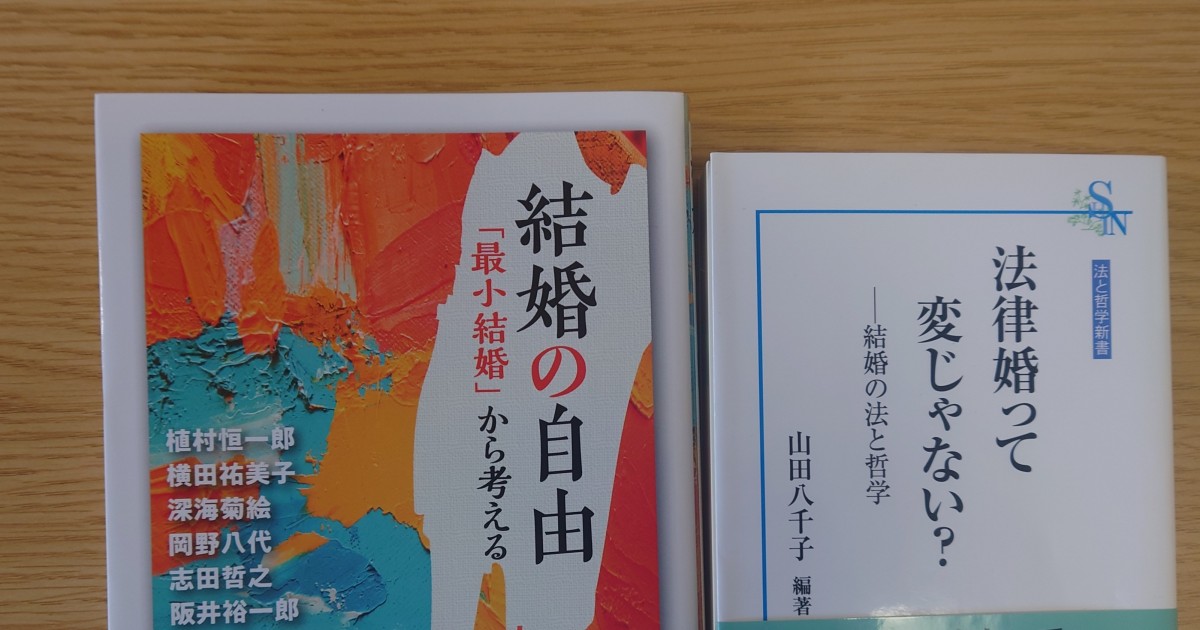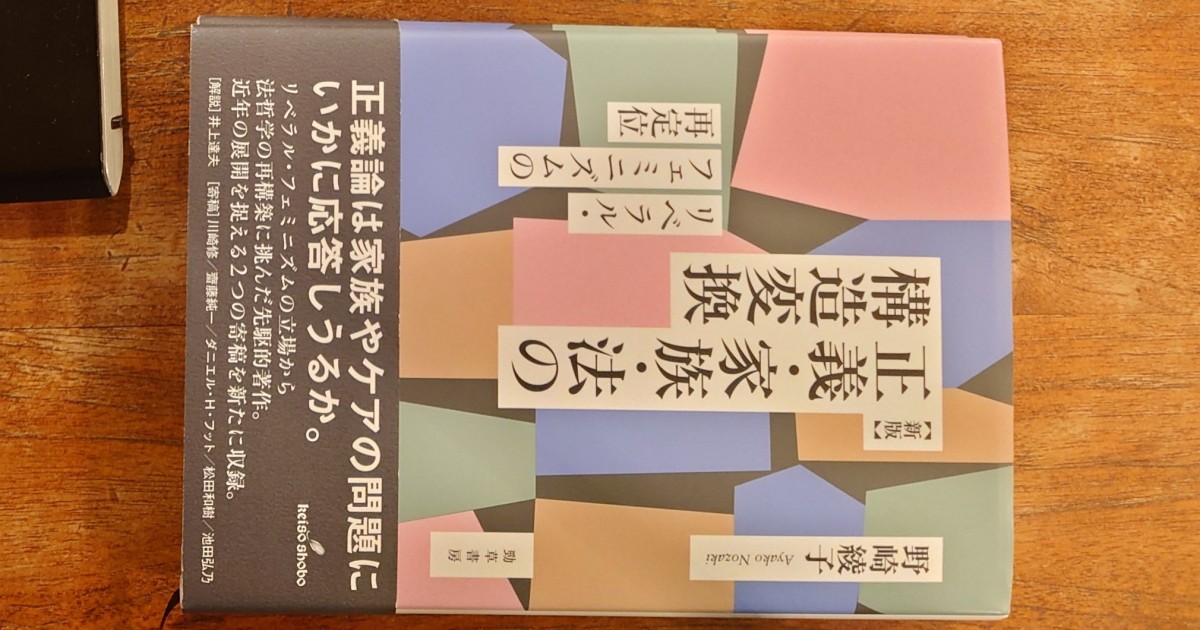水野家族法学を読む(34)「離婚/離婚訴訟に関する法的規整を考える(5)」

法学教室2022年2月号を喫茶店の椅子の上でパチリ
<前回記事>
時間が空きましたが、今回もこの論文を読んでいきいます。
長文ですが、いよいよ白眉の部分に入っていきます。
<参考文献>
対談「離婚訴訟、離婚に関する法的規整の現状と問題点」判例タイムズ1087号4-39頁(2002年)
事実婚と法律婚ー国家の法的介入をめぐってー
水野先生の国家の法的介入の必要性については、この回で触れていますのでご覧いただけますと幸いです。
ここでご紹介したように、水野先生は、「家庭内であっても人権は守られなければならない」という信念があります。
むろん、この点は瀬木裁判官も前提を共有しているのですが、「ごく普通の法律家の感覚でいくとなかなか(理解が)難しいように思う」と述べます。
水野先生はここで、自説の背景を説明します。
私は、法律婚と事実婚を区別することと、事実婚や非嫡出子に対する差別論とは、別の話だと思っています。日本社会に存在する差別構造があることは否定しませんし、もちろんその構造に対しても批判的です。事実婚は自由に行われてしかるべきですし、非嫡出子差別は許し難いと思います。
だからといって、法律婚と事実婚を同様に扱うべきである、法律婚と事実婚を同視すべきだというのは、おかしいということなのです。
(中略)
それから協議離婚についてですが、とても安上がりだなというのが素朴な実感ですね(笑い)。欧米法の離婚訴訟というのは、国家的に多額のお金を使っていると思います。当事者主義を守るために、フランスでもドイツでも法律扶助で弁護士を付けて、皆に裁判所を経由させるわけですね。
それに比べますと、ほんとに日本は安上がりです。そして家庭裁判所の中で行われている調停も、お安いですね、調停委員は裁判官のような給料はとりませんし。家裁における関与の仕方も、安上がりであるがゆえに、公権的かつ後見的な親切の範囲と当事者主義の原則が、なにかそれこそ「身分法の非合理性」的に混沌として混ざっているような気がします。安上がりにすむように、当事者の合意の枠組みでどんどん落としている。
安いに越したことはないと思うかどうかですが、私は、やはり安かろう悪かろうはある、という気がしています。とくに日本民法のように基準がありませんと、弊害は大きい。一定の基準というものがどうしても必要で、基準がないときにすべてを合意に任せておきますと、どうしても離婚したい側はバーゲニングパワーを失ってしまって、不当なまでに全部譲るだろうと思います。今の女性たちは、結構しっかり、権利意識を持っていて、そう甘くはない、という話も家裁の実務家から聞きますが、やはりその危険はあると思えます。
このようなケースを、しかもマスコミのセンセーショナルな記事で読んだだけで口にするのは不謹慎なのかもしれないですが、池田小事件の容疑者が調停離婚をしているようですね。私が読んだものは不正確な報道かもしれませんから、それを留保したうえで申しますと、その調停離婚は、彼が非常に執着した妻との調停離婚なのですが、この結婚は、内容からしますと結婚詐欺のようなものでしたし、婚姻中ずっと彼女はドメスティックバイオレンスの被害者でした。彼女は彼から一刻も早く逃げたいと思い、彼女の側で何百万かのお金を積んでようやく彼の離婚合意を得ています。
極端なケースではありますが、こうなってしまうと、合意に基づく離婚というのは、日本の離婚の欠陥だなと思います。彼女をなぜ日本法は救えなかったのか、家庭裁判所の中にまで入りながらなぜ守ってやれなかったのかと、その記事を読んでからずっと考えています。
ドメスティックバイオレンスの被害者保護が遅れているという問題もありますが、離婚法だけを考えても、合意に任せておいたときに、離婚するために被害者はどんな犠牲でも払うというケースがあると思います。客観的に基準というものがはっきりしていて、必ず離婚できるということになれば、彼女は何百万も払って離婚を買うことはなかったでしょう。彼のドメスティックバイオレンスのひどさを考えれば、それは法的に不法行為、犯罪行為として評価されるものでしょうし。
ただし、今後の日本の制度設計としては、母法のフランス法やドイツ法のように、離婚を全部司法に任せて、裁判所を経由させるという設計が必ずしも不可欠な解決策とも思いません。これも一つの伝統に規制されたあり方かもしれませんし。
現在の日本の協議離婚は、これは行政的な処理ですね。特に日本の法曹人口の少なさ、裁判官の少なさを考えますと、今後も行政的な処理ですむ離婚を維持したほうが現実的かとも思います。ただそのときに必要なのは、当事者を守れる基準であり、その基準をチェックできる機構ですね。それは司法であるとは限らずに、行政であってもいいかもしれません。
瀬木裁判官は、民主的な議論の中で立法的に解決するべきでは、と指摘しますが、水野先生の応答はなかなか辛辣です(ちなみに、水野先生もかかわった、選択的夫婦別姓の答申が行われたのはこの対談の5年前。)。
立法を目指すべきだという筋がもっともなことは、今、私自身が申したところなのですが(笑い)、ただ婚姻法改正の経緯を考えますと、法制審で時間をかけた私の五年間の立法準備作業は何だったのかという経験もあるのです(笑い)。条文が白地規定ですから、逆に基準を盛り込むことにも立法的な制約はないわけで、基準作りについて実務家が解釈を手伝ってくださると、そのほうがよほど実現への現実感があるのですね。国会に任せておくと、素人の保守的な議員の先生方が潰しちゃうという(笑い)実感が背景に見え隠れしているところがあります。
ここに瀬木裁判官は核心的な疑問をぶつけます。
水野説は論理的に筋の通った、全体として一貫した考え方だとは思うのですけれども、私には一つよくわからないところがあって、それは、国家の役割ということなのです。
国家が直接前面に出るのは謙抑的であったほうがいいとおっしゃる。例えば裁判の場面では、かなり裁量性を厳しくチェックしていこうという指向がある。
ところが、協議離婚の規制といった部分になると、今度はかなり国家が出張ってきて後見的に保護してしてやってもいいというお考えなのですね。その辺がどういうふうに統合されるのかなと疑問に思ったのです。
(中略)
離婚規制という局面で見ると、先のような水野さんのお考えにはちょっとねじれがあるように感じるのです。つまり、協議離婚などという大きな場面で、国家が行政的にそこまで出張ってチェックしてゆくということになれば、それこそ離婚訴訟における裁判官の裁量なんて小さい問題で、国家によるすごく大きな裁量の行使が、協議離婚のレヴェルで、国民、市民に対して働くと思うのです。そこについては不安を感じられないのか、あるいは裁判官の裁量を規制する議論との兼ね合いでどういうふうに考えられるのか、そこをちょっとおききしたいのです。
これに対する水野先生の回答は、一般的に首肯しうる内容です。
それは婚姻制度全体に対する規制の設計の仕方に対する議論であって、私の中では、それほど矛盾するものではないのですね。
婚姻制度をどういうものと構想するかということですが、婚姻制度は国家がカップルに関与する制度、あらかじめ明示した効果を当事者に強制することによって関与する制度だと考えます。扶養義務があり、嫡出推定があり、将来離婚するとなるとこれだけの負担が課せられる、そういう関係にあなたたちは入るのですね、と国家が用意をしておいて、当事者たちは、それでもその関係に入るか、あるいはそんな面倒なことはいやだから勝手に事実婚でやります、という選択肢をもちます。選択肢があるのにそれを承知で婚姻した当事者たちに対しては、国家が予告しておいた婚姻制度を働かせることができる。国家権力行使に対する謙抑性の要請は、それでクリアされます。もっとも法律婚の中身を妥当なものに改良していくべきことは、もちろんです。法律婚に入ることをためらわせるような不当な効果、たとえば夫婦同氏強制のような効果は強制すべきではないので、その改善の努力は絶えず必要です。
裁判官の裁量性については、すでにお話ししたように裁判の公平という観点から、考えます。ちなみに日本の裁判官の質は平均してとても高いものだと思いますが、そういう質の高さに全面的に依存した大岡裁きの制度設計ではいけないと考えています。
また、裁量性については、裁判の公平性という観点の他に、国家権力行使に対する謙抑性からも、消極的にならざるを得ません。
婚姻制度として予告した以外の形で、当事者が予期しない形で、当事者の生き方、プライベートな性生活、婚姻生活の形成の仕方に、国家権力が、内縁準婚理論で、あるいはまた不法行為を理由に関与してくるのは、いかがなものかと思うのです。そこはやはり謙抑的であるべきでしょう。婚姻制度という枠に入ることを当事者が選んだことによってはじめて、数多くの規制が正当化し得るだろうと思います。
瀬木裁判官は同意しません。
原理的にはおっしゃることはわかります。裁判官の裁量云々の議論も、裁判官に対する不信でなく、現在の離婚訴訟の形がよくないという意味合いで言っているのであって、国家の介入それ自体がいけないと言っているわけではないということでしょうか。
しかし、それにしても、先のような行政による協議離婚の規制をすれば、個々の場面で担当官がかなり杓子定規なことを言って、個人主義の夫婦達からは、どうしてこんなプライヴェートな場面で、しかも裁判手続といった場所を利用したわけでもないのに、いろいろ言われなければならないのか、大きなお世話であるという不満が、それこそ出てくるのではないでしょうか。私や私の友人達なら、法律家に限らずそう感じるのではないかと思うのです。行政的な規制が、例えば一定の条件を満たさないと離婚させませんよといった形を取ったりすると、その個々の場面で働く裁量性は、多分、現在の地裁の民事訴訟で裁判官がかなり厳密に法を扱って行使している裁量性とは比較にならない実質的な意味で大きなもの、あるいは硬いものの行使を許容せざるをえないのではないかと感じるのです。カフカは、下位の権力の行使というのは、現実の場面では上位の権力よりもずっと苛烈でありうると、『城』や『審判』で言っていますよね。
離婚訴訟や第三者に対する不貞慰謝料請求の議論における水野さんのデリケートな配慮、その背後にある懸念がこうした場面で消失してしまうのが、やはりちょっと解せないのですね。バランスの問題、どうして裁判の場面では非常に厳密に国家を規制するということがありながら、それ以前の段階では割合安心して介入してもらってもというふうにお考えになるのかということなのです。ここは一つ指摘を残しておきたいと思います。
私の感覚からすると、要するに不正が行われなければいいのですから、水野さんがおっしゃったように基準が明示されていることと、もう一つは法的なアクセスを容易にしておけばよいのではないかと思うのです。つまり、自分の権利が守られていないと思ったら、容易に相談にゆける、アドバイスを受けられる、あるいは法的な手段に訴えることができる、そういう場所と手続が確保されることが大事なのではないかと思うのです。もちろん現状は必ずしもそうではないので、それはよくないのですが、でも、反面、右のような情報とアクセスが満たされればそれで一応のところは十分ではないかなと私は感じるのです。
瀬木裁判官は、「日本の社会も実際には階層化がどんどん進んでいく。ただ見えにくいだけですね。で、底辺に近いほうでは家庭が崩壊していったり、親子関係が無残に崩れていったりする現象が出てきている現状で、その問題のある部分に目を向けるならば、より深く手を差し伸べてもいいのではないかというお考えなのかなと思うのです。」(同29-30頁)と、一定の理解を示しつつも、次のように述べます。
水野説の、法律婚に対する深い意味付け、これに対する含意が大きいということが、今のことと関連しているのでしょうね。
ただ、これについても思うのは、婚姻のとらえ方に関しての日本人の感覚が、ほかの生活場面との間でかなり差がありそうだというふうに感じるのですね。例えば、もうある程度前ですが、あまり見ないテレビをその時はたまたま漫然と見てたら、大学生達がいろんな議論をしていて、そのうち、事実婚と法律婚の選択ということになって、非常に賢い女子学生、常に筋道立ててしゃべっていた学生が、あなただったら学生で事実婚しますかと問われて、やっぱり同棲だと親が悲しむから籍は入れたいと思います、って言ったのです。そこで私は、うーん、親が悲しんじゃうのか、そうかあ、とちょっとショックを受けたのですけれど、もし水野さんだったら私よりもっとショックを受けたのではないかと(笑い)。
その学生の一般的な思想や人格のでき方と、その部分の発言には、すごく大きな落差があるのですよね。水野説の中のある部分は、こういう落差をいくぶん度外視して成り立っているところが、ないではないように思います。そして、その部分というのが、実務では、地裁ではまだ何とかなりますけれども、家裁実務ということになってくると、なかなか無視できないのでしょうね。
これも感想にすぎないのですが、事実婚か法律婚かというときに、入籍とか外聞とか世間体とか、実にそういうレヴェルでとらえられてしまっていて、法律婚の法的な意味合いなどといったことはあまり考えられていない。これはまさに教育の問題も含むのだと思うのですが、きちんとしたコンセンサスが市民の間にできないと、なかなかそこは変わらない面があるのではないか、法律婚に水野さんのおっしゃるような深い意味付けをする基盤が形成されにくいのではないかと思います。
子の引渡し、扶養料、養育費をめぐって
話は、子の引渡しをめぐる家裁の保全処分の話に移ります。
なお、ここからの対談は平成14(2002)年当時の民事執行法、民事保全法の規整および判例に基づくものであることにご留意ください。
瀬木裁判官は、「別居夫婦間等の子の引渡しに関しては、非常に長い間、人身保護請求が適切ということで地裁に事実上ゆだねられていて、先の平成五年判例以降の一連の判例で初めてその点が是正されたということがあります。」と話を向けると、水野先生はこう応じます。
今いわれた子の引き渡し請求では、その結果、とても悲惨な例も生じています。先日、東北大学の研究会で、最二小判昭61・7・18民集四○巻五号九九一頁のケースを紹介したら、名誉教授のお一人が「国家賠償ものだ」といわれました。これは、実親が短期間のつもりで叔父夫婦に預けたら、預かった方が離せなくなってしまって、実親の悪口を吹き込んで育てたケースで、比較的初期から実親は裁判所に救済を求めていましたのに、救済に非常に時間がかかってしまったのですね。子供は実親に怯える痛ましい成長を遂げてしまいました。でもこれを「国家賠償もの」と感じるような感性は、家族法学者にも実務にも、薄かったのではないでしょうか。
このような強制力を欠く問題は、子の引き渡し請求に限らず、家事事件一般に見られたと思います。昨秋の学会で報告を担当された家裁の実務家は、最近はかなり変わってきていて、迅速になっていると言っておられましたが。とくに次第に地裁的な裁判官が増えてきたために、体質が変わってきているそうです。
でも従来は、活字になった裁判記録を読んでも、かなり長い間、積極的な判断を下さずに当事者の合意に委ねて、いつまでも調停を繰り返していたという経緯が少なくありません。
(中略)
家事紛争の解決は当事者の合意で収めるのが一番望ましいという考え方が伝統的に強くあって、家庭裁判所が迅速な紛争解決の任務を負った司法裁判所だという考え方は、その後景に退く傾向があったことです。
もう一つは、民法の条文が白地規定になっておりますから、審判をするにしても、判断をするときに頼りになる基準があまりないこと。白地規定を解釈して審判してみても、その基準は何とでもいえますから、高裁にあがったときに、覆されてしまう可能性があります。その危険をなるべく冒したくないということはきっとあったでしょう。
もう一つは、強制執行手段の不備です。低額で継続的な家事債務についてはふさわしい強制執行手段がありませんので、命じてみても空しいということになります。
(中略)
家事債務の強制には、高額の土地代金債権などの強制と異なる強制手続きが必要ではないかといいたかったのです。フランスは、直接税の取り立て手続きにのせています。少額執行については期限到来前の執行も許すとか行政が取ってしまうとかいった相当大胆なことをしないといけないと思います。扶養料債権者は弱者ですから。
もっとも踏み倒しても平気だという日本の社会通念と、それを作ってしまった法の甘さが問題だったのかもしれません。英米法では裁判所侮辱罪になってしまいますし、ドイツでも扶養料債務を踏み倒すと刑事罰が待っていると当事者は認識していて、必死で払うそうですから。
日本では、債務の履行が行われる可能性が高いということが調停の存在意義とされるありさまです。家庭裁判所の審判は、もっと権威がなくてはいけません。
執行手段の不備だけではなくて、もちろん、その背景には、執行に対する消極的な考え方があったし、現にあるでしょう。消極性を正当化する理屈が一貫してありまして、とくに「身分法の非合理性」と言われるテーゼですが(「中川理論―身分法学の体系と身分行為理論―に関する一考察」山畠=五十嵐=藪古稀『民法学と比較法学の諸相Ⅲ』所収)、身分法の領域では、財産法のような領域とは異なり、強制ということは基本的に望ましくないという考え方が、強固な理念としてあったことは否定できないと思います。「身分法の非合理性」は同時に「事実的なことが法律的である」というテーゼですから、事実上離婚状態になっていると、解釈論上も離婚状態に合わせて、婚姻費用分担義務も消滅、親権も事実上監護している親の単独親権、となって、つまり婚姻法の保護をすべて否定することになります。
さらに金銭債権の強制執行以外になると、最初から否定する学説も勢力をもっていました。
昨秋の学会で、瀬木さんが子供の引渡しについて、強制執行について肯定的なお考えを表明してくださったので、非常に心強かったのですが、外国法を見ましたら、子供の引渡しについても、それなりの工夫はいりますけれど、もちろん強制執行があるわけですね。それどころかフランスは刑事罰による制裁が主戦場になっているくらいです。金銭給付以外は一切強制執行をしてはいけないというような硬直化した考え方ではなくて、場面場面でどうやって何をしていけばいいのかという、細かい考察が必要であったと思うのですが、日本では、実務も学説もそうではありませんでした。
現実にこういう強制執行は専門の手当がないとやりにくいという制度的な不備の理由があり、白地条項の条文上の不備という立法上の不備があり、これらの二つの制度的な理由があってやりにくいところに、やらないことを正当化してくれる一つの思想的な基盤があったということなのでしょう。
瀬木裁判官は、自説を次のように補足します。
家族法上の権利、ことに身分上の権利というのは必ずしも執行になじまない、少なくとも従来の民事執行にはなじまない、かえって継続的な親族関係に禍根を残しかねない、もしそれを全面的にやるのであれば身分法上の権利の特質に応じた独自の体系が必要ではないか、というようなことです。
そのメモの内容自体は、地裁実務、特に手続法をよく見てきた私にとっては、もう一つわかりにくい部分もあるのですけれども、おそらく、ここまで意識化はされないまでも家裁実務家にはある程度一般的な感覚としてあるものではないかと。
水野さんが家族法の従来の通説として批判されるような、そういう、身分法(家族法)の特殊性、ある意味での非合理性を重んじる考え方、私は、それは、水野さんが前記座談会でおっしゃっているように中川家族法から生まれたというよりも、むしろ、それこそが中川家族法を生んだ思想ではないかと思うのですけれども、そこに何らかの根拠はないかということは一つ思うのです。
つまり、例えば、この前の子の引渡しの問題でも、あの問題については、私としては考えられることは全部詰め、分析した上で、民事執行としてここまではできるはずだというぎりぎりのところを述べた、そして、刑事的制裁を伴う人身保護というものは、手続的フェアネスとか手続的保障の観点からは、あくまで民事執行という通常の強制手段が功を奏しなかった場合にのみ用いるべきであるとの議論を展開しました。その論点については私は今もそう思っているのです。
これに対する水野先生の応答です。
日本人が代々と作り上げてきた法システムですから、それなりのものはあるでしょう。我々はまさにその理屈が説得力をもつ社会の中で生きています。美しく言えば「和」の精神ということになるのでしょうか、世の中で自我を殺してお互いに譲り合うこと、その譲り合いの部分を大切にすべきであるという文化ですね。中川善之助先生が命名したとしても、この文化の中で生きてきた我々が作り上げてきたものとして、身分法の非合理性という概念があるのでしょう。また実態としても、この文化がそれにふさわしい紛争解決の力をある程度もっていたのかも知れません。つまり具体的には「世間」が日本の社会の中で果たしてきた機能ですね。でももはや日本社会からかつてのように実際に共同体で援助作業をする「世間」は失われて久しく、力のあるのはマスコミの集中砲火を意味する「世間」だけだろうと思いますが。
この概念の中に、何らかの根拠と言いますか、あるいは文化として大事にしていくものがあるのではないかという感覚は、それは私も共有します。そこまですべてを否定するつもりはないのですが、この概念を制度設計のところへ持ち込みますと、ある種の思考停止をもたらしているのではないかと思うのですね。
それが大前提になってしまって思考停止をしたときに、現実として起こってくるのは、弱肉強食です。子供の奪い合いの場合には、悲惨な自力救済が起こるということになると、もっと思考停止をしないで突っこんで考えなくてはいけないだろうと思います。
大前提から考えてしまうと、非合理性の家裁の調停制度か、当事者主義の美しい近代の訴訟構造の地裁か、という選択になってしまいます。地裁の離婚訴訟で全部かたがつくかと言ったら、決してそんなことはない。特に子供の部分です。子供については当事者主義の構造ではかたがつかない部分です。その部分をどうやっていくのかということを、個別具体的に分析していく必要があります。
これは当事者構造の民事訴訟の枠組みでやるべきだと言うか、あるいは身分法の非合理性なのだから、そういうものには馴染まないのだと言うか、そういう対立的な議論の仕方は、双方に不毛なものをもたらすという気がいたします。だから今度の家裁への移管の問題になると、まさにそこのところで本当に緻密な議論が必要になってくるのだろうと思っております。
不思議な対立
ここまでの議論を私なりにまとめると、次のようになります。
-
水野先生は、国家の法的介入について肯定的であり、近代法のシステムの中で家族の弱者保護に積極的である。これに対し、瀬木裁判官は、こうした国家の法的介入は、当事者の協議や調停に批判的ではなく、それを前提として、法的介入はフェアネスが欠ける場合に段階的に(特に刑事手続きは最後の手段として)手段として選択されうる。
-
その背景として、水野先生は、中川理論にみられるような身分法独自の理論に否定的であり、近代法的な当事者対等を原則としつつも、現実的な不平等(バーゲニングパワー)に基づく、不均衡な力関係に対して、法的介入を要請する。対して、瀬木裁判官は、中川理論に肯定的であり、裁判官の裁量に基づく具体的妥当性のある法的解決を志向する。
-
その帰結として、水野先生は、裁判官に裁量を与えることは概ね否定的であるが、瀬木裁判官は、否定的ではない。
-
両者の間に、大きな不一致が生じているのは、水野先生は人間(裁判官)の裁量に基づく法的介入は、「大岡裁き」になる危険性をはらみ、法的安定性を害すると考えているのに対し、瀬木裁判官は、実際の立法こそが不均衡や法的安定性を害する内容を持っているのであり、裁判官の解釈による是正(具体的妥当性のある解決)によって、均衡を保つことに期待しているからだと思われる。
<参考文献>の対談はまだまだ続きますが、ご紹介はここまでにします。
ここまで読まれた方(特に実務の先生方は)、全般的にいって、瀬木裁判官より水野先生に好意的な感想を持たれた方が多いのでは?と予想します。瀬木裁判官の発言は、全般的にコンサバティブであり、ところどころにジェンダーバイアスも見え隠れします。
しかし、24年後の世界からこの対談を眺めている私たちは、不思議な対立に見えてくるはずです。
なぜなら、両者は24年後にその論理的帰結をそっくり逆転させているからです。
離婚後共同親権をめぐる「逆転」
<参考文献>でご紹介した対談からすると、水野先生は、離婚後共同親権については、厳格なルールの下に認め、瀬木裁判官は、その点においても裁判官の裁量が妥当するように思えます。
しかし、24年後(2026年)、水野先生は、当事者の協議によっても可能となる、非常に緩やかな要件に基づく離婚後共同親権制度に賛成します。これに対し、瀬木裁判官(現在は明治大学名誉教授)は批判的な見解を述べています。
共同親権制それ自体は、両親と子、また両親どうしの関係に問題がない場合について認めるのなら、一つの望ましい制度です。
ただし、海外の制度は、家庭裁判所等の注意深い監視とケア(たとえば、一方の親に何らかの問題があれば家庭裁判所が即時に介入して適切な処置をとるなど)とセットになっています。そうした制度的手当てのないままこれを実施すると、必ずさまざまな問題や紛争が生じます。
私は、共同親権を認めるのなら、その要件については、とりあえず厳しく限定し、当事者の申立てに基づき簡易な審理を行った上での家裁の許可を必要とし、家裁が当事者の意思や具体的な共同親権行使の方法について確認した上でこれを認めるのが相当と考えます。
父母の協議だけでこれを認めると、力関係の弱い者(全体としてみれば、妻の側であることが多い)が合意を強いられるなどのことから、先のように種々の問題が生じ、ひいては子の福祉にも悪影響を及ぼし、制度の信頼もそこなわれるおそれが大きいからです。
離婚に関しては、最低限共同親権の問題だけは家裁が関与すべきであり、それが無理なら、当面は単独親権制を維持するのが穏当だと思います。
対談の後、瀬木裁判官は退官し、明治大学法科大学院教授に転身します。2014年に著した「絶望の裁判所」(講談社現代新書)で、日本の裁判制度を鋭く批判するようになります。
こうして対比してみると、瀬木裁判官が水野先生に向けた「懸念の消失」という批判は、なかなかに核心をついていたように思えます。
(この連載つづく)
<この連載一覧>
すでに登録済みの方は こちら