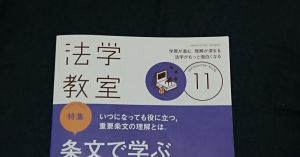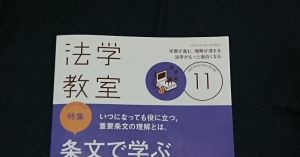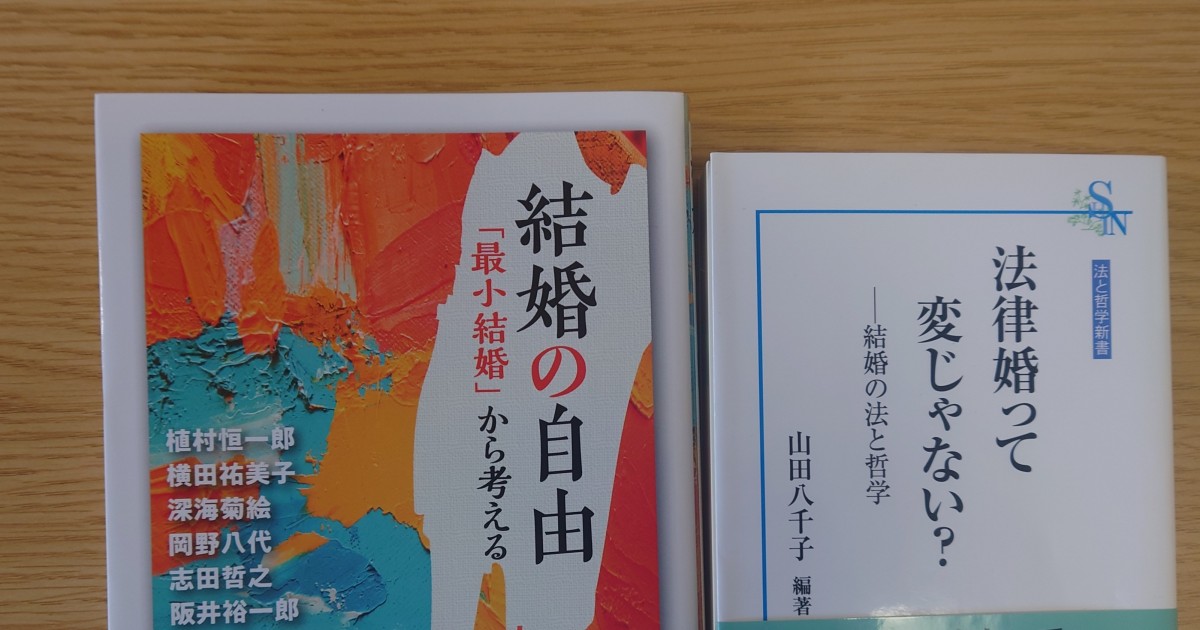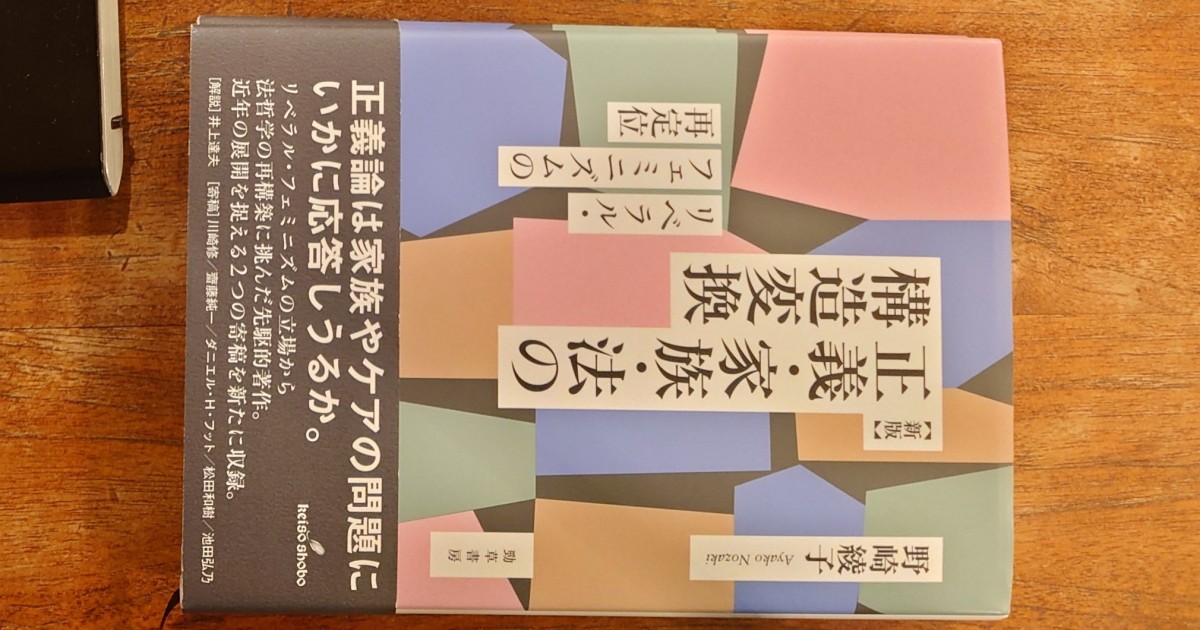水野家族法学を読む(33)「離婚/離婚訴訟に関する法的規整を考える(4)」

法学教室2022年2月号を喫茶店の椅子の上でパチリ
<前回記事>
時間が空きましたが、今回もこの論文を読んでいきいます。
本日は多少長文です。
<参考文献>
対談「離婚訴訟、離婚に関する法的規整の現状と問題点」判例タイムズ1087号4-39頁(2002年)
第三者に対する不貞行為請求権ー整合性への疑問ー
話は、第三者に対する不貞行為請求権に移ります。
水野先生は、この請求権について否定説の立場に立たれていることは、以前(3年前...)このメールマガジンでご紹介した通りです。
これについて、水野先生はこう述べています。
夫婦関係、男女関係がこじれたときは、当事者は愛憎の渦のなかにいます。本人はとてもひどい目にあったと思っていても、国家権力の保障を求めて、裁判所に行って救済してもらえるとはもちろん限らないわけで、法律婚に限ってかつその当事者間についてだけ国家権力が干渉するということで、ちょうどいいと思うのです。
どうも従来、内縁関係に法律婚の規定を準用したり、婚約破棄に損害賠償を認めたり、裁判所が請求を認めすぎる傾向があったように思います。不法行為の条文を根拠に、裁判所が男女間の紛争を対象としすぎたのではないでしょうか。もちろんドメスティックバイオレンスとか児童虐待とかいう人身被害になったら話は別ですし、その救済が遅れていたことはたしかですが、これらの被害も必要なのはむしろ実際の救済であって、損害賠償という救済ではないでしょう。自己決定と自由の領域を尊重することは、原理的に、国家権力が裁判によって損害賠償を命じる領域について、謙抑的に設計すべきことを意味すると思います。
法律婚においては、国家権力が当事者に介入して守ってやらなくてはならないところですのに、まさにそこにおいて十分なことをしてこなかったから、その歪みがほかのところで妙に介入する結果と結びついてきたような気もします。配偶者が他の恋人を作って家族を捨てたら、配偶者にしっかり責任をとらせれば、それで足りるでしょう。
瀬木裁判官はこの説に一定の理解を示します。
消極説の指摘に沿って考えてみると、原告が配偶者に対する態度を決めていない場合については、不法行為の侵害利益が婚姻共同生活の平和の維持ということであるのに、第三者を訴えることでその利益自体がかえって不安定にならないかということがいえるかもしれませんね。一方、離婚後の請求については、確かに、損害の賠償を求めるというより、むしろ、相手を法廷にさらして復讐したいという気持ちが強く出ている場合も、ないではありません。弁護士としても訴えを起こす前にまず訴訟外でよく交渉してみてもよかったのではないか、そうすれば訴訟外で解決したのにと思われる事案があります。
ただ、反面、実際のケースにおいては、第三者の側に原告を積極的に傷付ける行為、良くない行為があったという場合も多いですね。たとえ原則的に消極説を採ったとしても、そういう場合には不法行為と評価しうる場合があるでしょうね。
いずれにしても、ヨーロッパ的な考え方、それがすべて正しいとは思わないのですけれども、ヨーロッパ流の洗練された個人主義というものを前提にして、個人の人格の尊重ということを非常にデリケートに考えた場合に採るべき一つの考え方が消極説であるということはうなずける部分があります。調査官の解説に要約されている欧米諸国の考え方(最高裁判所判例解説民事篇平成八年度(上)二四五頁)も、ここは大体きれいに消極説でそろっているようですね。その根拠もおおむね水野説と同様のようです。
ですから、この点に関しては、水野説の意味というのは、現在の通説的な考え方に対する一つの根本的な批判ということになるのでしょうね。
水野先生は付け加えます。
離婚同様、法体系全体から見なくてはならないということです。この慰謝料請求権が非嫡出子の強制認知抑圧機能をもつことも、体系全体からみれば、見えてきます。
先ほど原告がひどく傷つけられる被告の行為があることがあるといわれました。実務をたくさん見ていらっしゃると、たしかにそういうケースもあるのだろうと思います。でも、そう簡単に不法行為になるとは思えません。
恋愛に失恋して傷ついて逃げた恋人を追いかけたという場合ですと、それは法的な問題にはならないわけですが、あるときその追いかけ方が異常になった。追いかけている本人は相変わらず失恋で追いかけているだけのつもりかもしれないけれども、法的に評価したときに、ある時点からそれはストーカーという犯罪行為になっていたということがあり得ます。不貞行為の相手方がそのようなレベルの行為までしてしまったときに、それは不貞行為を理由としてではなく、つまり失恋をして追いかけたということではなくストーカー行為をしたということによって違法行為になるように、ひどい嫌がらせをしたこと自体をとらえて不法行為で評価するということはありうると思います。
といった具合に、徹底して否定的であるのですが、水野先生は、法学教室の連載論考(2021年11月号)では、「(貞操義務を破ることは)配偶者に対する最大の精神的DV」とも述べておられます。実際には共同不法行為と評価されても仕方のない事案も多いと見られる中で、ここまで徹底的に否定説に立たれる必要性があるのか、容易に整合しないように思えます。
水野先生は、当該論考の中でも「慰謝料請求権を否定する代わりに、離婚給付を手厚く保障して不貞行為のような精神的苦痛をもたらす婚姻生活から逃れる自由を確保する方向が望ましい」と述べ、ご自身のプラグマティズムに強烈なこだわりがあるので、法解釈の整合性より、法政策的な整合性も加えて俯瞰しておられるのかもしれません。
離婚給付のあり方-水野先生の「怒り」-
続いて、話は離婚給付に移ります。
ここでの水野先生の主張はかなり強硬です。
財産分与が現存財産を前提として、現存財産の分割ということになってしまいましたから、解釈の硬直化が生じています。いまだにその二分の一を目標とすることになっているわけですが、でも、財産獲得能力のある夫と専業主婦の妻の場合に、二分の一であったら、離婚給付としてはとても足りない、もっと多額を妻に取らせたいと思います。民法改正要綱は、寄与度についてはむしろ二分の一ルールを明示する方向でしたが、その上位の基準として「離婚後の当事者間の衡平を図るため」諸事情を考慮できるとしていますから、最低の寄与度として二分の一の権利性を確保した上で、財産獲得能力のない当事者にはそれ以上のものをとらせる基準と読めます。
婚姻は一応生涯を約束した契約であったはずで、それがうまくいかなくなってしまったのですから、将来の生活保障というのは当然必要になる、婚姻という契約の中の根本的な部分だろうと思うのです。ですから、婚姻がうまくいかなくなったときに、有責であったからということではなくて、婚姻をしたという事実から、それだけ重い債務を、夫たち、つまり財産獲得能力のある側に課してもしかるべきであろうと思います。フランスの補償給付も離婚後の生活保障をしておりますし、ドイツ法は扶養義務が継続しますし、英米法でも、ずっとアリモニーが認められてきたわけですね。
ただ離婚した後も扶養をする義務というのは、日本人の感覚には遠いのかもしれません。日本人の伝統の中にはそういう発想はなかったのでしょう。法的な離婚に至らない事実上の破綻の場合ですら、義務の消滅をいう学説や判例があるくらいですから。子供については、日本人でも、扶養義務の存在はもっともだと思うでしょう、それは両方の子供なわけですから。でも、別れた女房に対してどうして扶養しなくてはならないのかという疑問は日本では説得力があって、離婚後の扶養という考え方はなかなかコンセンサスが得られないことであったのかもしれませんが、私は、それが日本の婚姻法の問題点であったと考えています。
婚姻は一生をともにする約束なので、破綻したときには、現存財産が全部妻にいってしまって、かつまだ借金を負うという形で別れるというくらいが、妥当な線だと思うのですね。財産分与の現存財産の山分けという概念は、大幅に修正しないといけないと思うのです。
90年代の家族法学者の議論をご存知ない方に補足すると、「夫は借金を負ってでも払え」という議論は決して極論でも異端でもありません。当時、おそらく現在もスタンダードな理論だとは思うのですが、財産分与は①精算的要素、②扶養的要素、③慰謝料に分かれ、このうち②については、実務的運用では、他の要素を考慮してもなお経済的に困窮する場合に限られる等、限定的に考えられてきました。
残念ながら、今回の家族法改定について、国会では、財産分与については除斥期間の伸長(2年→5年)についての質疑はいくつか行われたものの、財産分与の二分の一ルールを超えた議論はほとんど行われませんでした。
<参考文献>の対談当時(つまり2002年)に行われた、水野先生の主張は強硬であり、瀬木裁判官から借金して払うことになることについて指摘を受けると堂々と返します。
ええ、それはもちろん借金をして払うことになるのだと思います。扶養義務という形にするのか、あるいは借金という形で一時金の定額にしてしまうのか、独仏法は手法はわかれますが。一時金の定額にしたフランスの補償給付は、とても高額でかつ硬直化しすぎだというので、最近の改正で、事情変更で修正される可能性を広くする形で手が入りましたけれども、それでも、給付の内容は、離婚した二人が生涯にわたって生活程度を同じくらいにする金額ということですから、それは随分の金額です。ほとんどの男は現存財産では払いきれないので、定期金という形で将来の借金になるわけです。
瀬木裁判官は、水野先生の主張に対し、バブル崩壊(1990年)前後で財産分与の金額が低調に推移している実務状況を解説した後、いくつか疑問を提示します。
-
実務感覚として、財産分与に生涯補償的な考え方を含めることに(女性裁判官を含めても)賛成する人は少ない
-
社会的な不平等を個々の人間にどこまで埋めさせるのか
-
離婚恐怖を広い意味での法的な賠償・補償まで含めると、他の場合(不法行為)等との解釈のバランスを考慮する必要があるのではないか
これに対する水野先生の応答は、いかにも2002年の時代を反映したものです。
日本の女性の地位の低さは、社会の中のみならず、家庭の中でも深刻です。内閣府の「女性に対する暴力に関する専門調査会」に所属しているのですが、そこでの調査によると、日本の社会における「養ってやっているんだ」という夫たちの横暴は、DVの根底にもあり、ときには目を覆わんばかりです。別れたら食べていけないという恐怖が妻たちをそんな家庭に留めています。そこまで含めて日本の「風土」だといってしまえばそれまでなのですけれど、離婚法が独仏並だったら、こんなひどいことにはなるまい、と思うのです。
思春期の精神的問題を専門にしている精神科医の知人がいるのですが、彼は、「結局、主婦は、弱者なのですね。弱者である主婦自身がかかえている自分の問題を、子供にすがったり転嫁したりすることでやりすごすので、子供が精神的に問題を抱えてしまう、という構造です」と分析していました。女性を守ることは、子供を守ることを意味するでしょう。
人間の生活を支える家庭は、一定の財とサービスによって維持されます。アンペイドワークであるその私的サービスを供給するのは、これまで役割分業で女性の仕事とされてきました。婚姻による生活保障は、婚姻が作り出す家庭生活におけるアンペイドワーカーの生活保障という側面もありました。婚姻によってアンペイドワーカーになったために、賃金労働者になる機会を喪失したと考えれば、その機会費用を請求できる、とも考えられます。
離婚後の母子家庭は経済的にとても大変です。それでも女性たちが、離婚できるようになったのは、社会保障のおかげです。少なくとも社会保障で生きてはいける、となった女性たちが、忍従の一生から逃れて、離婚するようになりました。タックスペイヤーの私からすると、その母子家庭の生活を保障すべきなのは、税金より先に、まず別れた夫だろう、と思います。
当時の女性の労働力率の推移(いわゆるM字型カーブ)、これに起因する女性の収入機会の喪失額は、現在よりも顕著でした。水野先生の主張には、その収入を機会を奪い続けてきた男性に対する「怒り」が垣間見えます。
ただ、この「怒り」のバックには、この当時を生きていた人全員が受ける思考的制約も見られます。例えば、上記引用のように、水野先生は「結婚は一生涯続くもの」を原則とされていたり、「女性が子育てをする」というジェンダーロールを前提として主張を組み立てられているのは、それが厳然たる社会的背景として存在しているからでしょう。
この後、二人の対談は、いったん「結婚は一生涯続くものなのか?」という文化的背景について交わされますが、本筋に戻って、瀬木裁判官は水野先生の主張に一定の理解を示されます。
少し長いですが引用します。
仮に実務を知る研究者的な目から水野説を汲むとすれば、まず、離婚に伴う財産給付については有責的要素からなるべく解放するということでしょうか。先にお話ししたとおり、有責的要素が強い場合には慰謝料を求めたいというのはあるでしょうけど、基本的には、給付の問題を考える場合には有責性をあまり重視すべきでないだろうということがあります。
それから、一番汲めると思ったのは扶養的財産分与の見直しということなのですが、それに先立って財産分与のうち清算的なものについてまず言ってしまいますと、これの重要なのは手続法的な部分で、財産開示だと思うんです。夫がどんな預金を持っているかわからない。逆に妻のほうが全部持ち出してしまって内容がわからない。これを開示しろというのだけれど、制度がないから、弁護士も、自分の依頼者に対して全部開示しなければ駄目ですよと言いにくい。水野さんからいただいた文献を見たところでは、開示制度があってもなおかつ従わない人が外国でも多くて、それは開示しない場合の制裁ないしみなしが難しいからだろうと思うのですが、それでも何らかの財産開示制度を設ける意味、それが訴訟で一番大きいのは、一つは離婚訴訟かと思うのです。現在、担保・執行法制の見直しということが検討されていて、そこで財産開示が一つ出ていますが、こういう部分こそ家族法がまず注目すべき点だったのではないかと思います。
さて、扶養的財産分与では、少なくとも、所得機会の喪失を補うということは言える、一定の合理性があると思うのです。結婚したために、より高い収入を得る機会を定型的に失った、実際そういう場合も多いわけですし、それはある程度みなすということもできるわけですから、それで生活水準の差ができる場合に、例えば少なくとも相当期間、何年分かの差はきちんと埋めるという形で、扶養的財産分与といっても、現在の実務で割合よくある調整的なレヴェルの金額のもの、あるいは一括しての財産分与算定の一要素として考慮するものにとどまらず、ある程度実質的な金額を出していくことが可能になるのではないか。そういう実質的な扶養的財産分与のあり方は、今後考えられていってもいいのではないかと思います。
もう一つは養育費で、支払うべきことについて争いがないのは子供の部分だと思うのです。先ほど種としての人類の話をした、それはもう種としての部分ですからそれを現実に当てはめるのは乱暴だということはよくわかるのですけれども、少なくとも言えるのは、おっしゃったとおり、家族は子供を守る繭であるという面が大きいわけですから、養育費については、現実の必要額をきちんと算出して負担させるということ、もう一つは大阪弁護士会からそういう案が出ていますけれども、従来の執行制度では難しいので、例えば給与天引制度といった形により行政レヴェルで裁判の実現を確保してしまうということ(「家事事件審理改善に関する意見書」本誌一〇四五号一六頁)、これは、養育費以外でも、例えば年金分割といったことがあるかと思います。
そういう意味でこの部分は、ことに積極的破綻主義の方向へ進めば、これから変わってきうるところだし、そして、こういう部分は本当に家裁のお家芸なのですね。給付とか財産分けという部分についてはノウハウがある。だから、ここは移管によって大きく変わってくることが期待できるところ、そのメリットの一つではないかと思いますし、家裁実務に詳しい裁判官からもそのような感想はありました。
この瀬木裁判官の実務感覚は、近年の民事執行法等や今回の家族法改定で、配偶者への財産開示が一定程度認められることになり、反映されていている部分はかなりあるように思います。
一方で、扶養的要素の部分は、決定的な進展は見られなかったように思えます。今回の家族法制部会の議論では、審理の複雑化や事案によって大きく変わり得る等の理由から慎重論も強く、「婚姻中の生活水準」「職業及び収入」としては考慮することは明示されたものの、「稼働能力」や「経済的不利益」「居住環境」といった点は明示されませんでした。
この改正点について、法務省の立法担当者の解説(※)では、家庭裁判所の合理的裁量に委ねられているとだけあり、扶養的要素の考慮が前進するかどうかは微妙なところ(判例の蓄積を待たなけらばならない)とみられます。
さて、この対談については、1月中まで読んでいく予定です。
その後、いよいよ「離婚後共同親権」の話に改めて戻ります。
(この連載つづく)
※北村治樹編「一問一答 令和6年民法等改正 ー家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)」(商事法務 2025年)169頁
この連載一覧
すでに登録済みの方は こちら