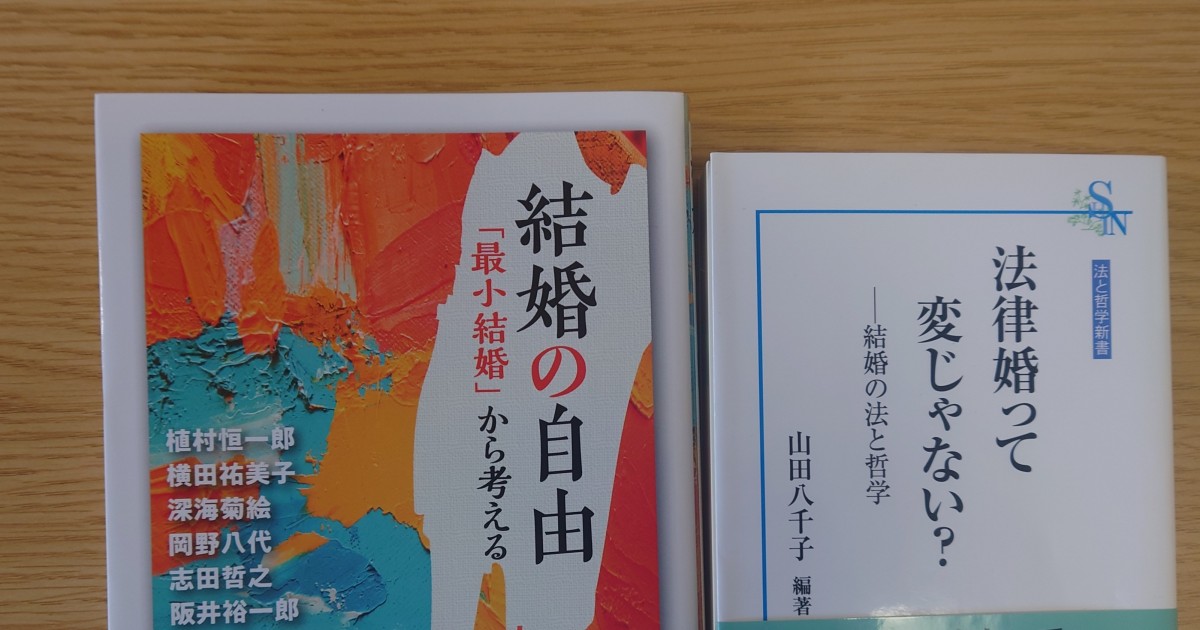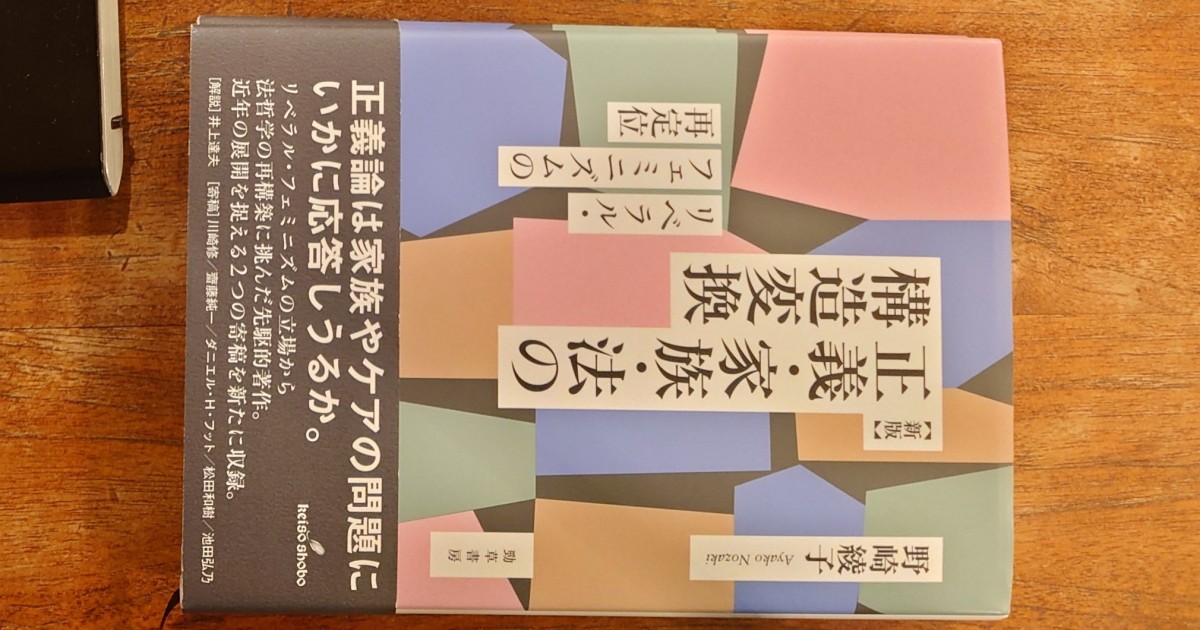民法学の第一人者は、なぜ離婚後共同親権「反対」に転じたのか(4)「着想」
<前回>

諦観
前回ニュースレターでご紹介した、2000年後の水野先生の論稿から約20年後。
東北大学で教鞭を取られていた水野先生は、学生新聞のインタビューに答える形で、家族法の魅力をこのように語っておられます。
家族法については、学生時代から疑問を持っていました。民法を適用すれば紛争解決の答えが出るはずなのに、家族法の部分は、当事者の協議に委ねるだけで解決しないのです。研究室に残ってから、それは日本民法のいささか困った特徴なのだと分かりました。当時から、自由や平等という短い言葉による正義よりは、具体的な問題に取り組んで、より確実に権利と法益を守る民法の方に魅力を感じていました。複雑さに耐えて思考し続ける大人の学問だと思ったのです。

また、2008年に発表された次の論文では、家族法の性格をこのようにも述べています。
<参照文献①>
「家族法の弱者保護機能について」「家族法の弱者保護機能について」鈴木禄弥先生追悼・太田知行・荒川重勝・生熊長幸編「民事法学への挑戦と新たな構築」創文社651-684頁(2008年)
民法は、妥協と共生の秩序である。「法=正義」といわれるが、民法は短い言葉による正義の対極にあって、むしろ、正義は不可知であるという諦観が、民法の底にあるように思われる。いいかえれば、民法は、多様で相互に矛盾する多くの正義を内包しているともいえる。数多くの言葉と概念を駆使して、妥協と共生の秩序を作り上げてきた民法は、度し難い人間社会を何とか平和裡に運ぶ知恵と技術をローマ時代から蓄積してきた成果である点で、少なくとも社会にとって安全なものであることは間違いない。家族の保護も、家族に介入する力を民法にもたせ、救済策を民法体系と整合的に制度化したときに、自ずから安定的に実行可能なものにすることができるだろう。
こうした水野先生の家族法学の基本的コンセプトは、その研究生活の中で一貫していました。
2006年に発表された講演録で、離婚法のあるべき姿と現状との差異について、次のように述べています。
<参照文献②>
「日本の離婚手続について」ケース研究286号55-96頁(2006年)
日本の裁判離婚は非常にいびつですので、それと比べますとフランス法の構造は、有責離婚でも先ほど言いましたように裁量権は限定されていますし、それから、世界的に見ると、離婚法は、もうそういう有責離婚すら、つまり不貞行為の有無すら立証させることをやめて、客観的な破綻の年限で離婚できるとする方向に進んでおります。離婚法の将来像は、そういう形にならざるを得ないのではないでしょうか。むしろ離婚の後始末が大切です。離婚給付とか子どもたちの処遇が主問題になって、そこのところで十分に弱者保護がなされる必要があります。そういう制度設計が望ましいわけですが、現在の日本法はそうではありません。現存財産の2分の1が上限という財産分与は、あまりに低額過ぎますし、上乗せの可能性となる慰謝料は、有責構成に乗っていて問題が大きい。離婚後の生活をある程度、均衡にするだけの給付が必要でしょう。それがない現状では、離婚は経済力のない方に不利になりますから、それを是正するために、婚姻費用分担を事実上の離婚後扶養にして婚姻を形式的に継続したり、有責配偶者の夫が妻の離婚合意を買い取る手段として現在の有責配偶者からの離婚請求に関する判例法を利用したりすることが行われているわけです。破綻離婚に反対する論者が現在の判例法のもたらすこれらの利点を挙げますが、妻に経済的な給付を得させるという目的と結論は妥当とはいえ、この結果的利点を加味して考えても、このいびつな離婚訴訟構造の弊害の深刻さはカバーできないと思います。実際には離婚を望む配偶者の多数は、経済力のない妻のほうで、その場合には弊害しかもたらしません。
特に、この紛争を解決する必要性に関心を強く持っておられました。
子の奪い合い紛争を解決するために
前回ニュースレターでも取り上げました小論文の中で、子の奪い合い紛争を次のように分析しています。
<参照文献③>
「子の奪い合いの法的解決を目指して」家族〈社会と法〉18号37-42頁(2002年)
両親の子の奪い合いは、深刻である。また、「現代親子法がかかえる難問中の難問」といわれる。両親にはぐくまれて暮らすという最善の解決が不可能となった後で、所詮、より害の少ない解決を模索するにすぎない努力であるし、裁判官にとっては両親のどちらかに監護権を与える判断は、子の未来の幸福さの予測という不可能に近い判断を迫られるのであって、要件の立証で解決のつく通常の民事裁判と比較したときに、あまりにも徒労感ばかり大きな難しい問題であるかもしれない。
法廷外の悲惨は、とかく見えにくいけれども、きわめて深刻である。暴力的奪い合いの対象となる子、奪取を予防するために行動の自由を奪われる子などの物理的な被害の他、片親の悪口を吹き込まれて育つ子などの精神的な被害も大きい。子の健康な自我の成長にとって、自己の存在のルーツである親を否定的に認識させられることの被害は、計り知れないものがある。児童の権利条約第9条は児童が「父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利」を謳っているが、従来のわが国の学説・実務は、必ずしもこのような権利を重視するものではなかった。離婚後の面接交渉権の権利性は重視されず、婚姻中は共同親権であるにもかかわらず、子と別居した親の親権は、事実上のみならず解釈論上も、行使が不可能となり、親権単独行使とされてきた。子と離れている親がこの状態を甘受するのであれば、それが子の幸福であるかどうかはともかくとして、それなりの平和な状態が維持されるであろうが、親が争う意思を持ったとたんに、解決の困難な悲惨が始まる。
幼児の引渡しをめぐる争いの解決には、特徴的な要請がある。幼児はきわめて可塑性に富み時々刻々成長するので環境の影響が非常に大きく、本来の適正な生育環境から離された場合の精神的傷や刻印はわずかの間にいやしがたいものとなるため、解決は迅速に行わなければならない。しかし同時に結論を導くにあたっての最高の基準は子の幸福であるから、父親から母親のいずれかを無条件に優先したり親権の有無などによる形式的結論はとれないため、誰の手元で育つことが子の幸福かを見極めることは、慎重に確実に行わなければならない。この矛盾した要請に答える手続をどのように設計するかというのは、難問である。
2002年のこの論文でも、前回ニュースレターで指摘した「片親洗脳」の弊害を指摘されています。
そして、2000年の論文では、子の奪い合い紛争の特徴をこうも述べています。
<参照文献④>
「日本の離婚における法規制のあり方」ケース研究262号2-18頁(2000年)
日本では子ども監護問題は、自力救済によるしかないという「知恵」が行き渡りつつあり、深刻な事態となっている。子の監護紛争では自力救済を有効に禁止するという形で法の保障が図らなければならないだろう。
ここで注意しなければならないことは、水野先生は、この自力救済という指摘は、離婚後共同親権推進派がいうところの、いわゆる「連れ去り勝ち」攻撃とは一線を画している、ということです。
前回ニュースレターでご紹介したように、水野先生が念頭にあったのは、DV追い出し婚のケース(最判昭和46年4月23日)であったり、公的介入などの法的措置が有効に機能していないケース(最判昭和61年7月18日)であったりしました。
ちなみに、後に触れますが、いわゆる子連れ別居のケースについて、水野先生は、「逃げる権利」だと述べています。
そこで、次の論文ではこう述べています。
<参照文献⑤>
「家族の法的保護」辻村みよ子・河上正二・水野紀子編「男女共同参画のためにー政策提言」東北大学出版会429-441頁(2008年)
裁判所が強制力をもって早期に介入しないと、裁判所外の自力救済による悲惨が募るばかりである…。家事債務の強制履行手続も日本法は不備であるが、子の引き渡しの強制執行手続については、さらに不備で、事実上不可能であり、それが子の奪い合いの悲惨を招いている。子の奪い合いについても強制力を制度的に確保するとともに、その強制力を担保にしながら、裁判官が、従来以上に広範に介入して、家族の調整を行わざるをえないであろう。
そして、前掲<参照文献②>の講演録の中で、次のように述べ、子の奪い合い紛争の解決策としての離婚後共同親権の導入に好意的な見解を述べるのです。
離婚事件の司法的処理は、客観的な線を引くことで定型的に処理されるという方向が望ましくて、唯一長期的に続く人間関係調整として線を引けない問題は、両親の協力が必要な子どもの育成という問題だけです。
最後に、この子どもの育成の問題についても、少しお話をしたいと思います。戦前は親権者は父親で、離婚してもそれは変わりませんでしたが、戦後の改正で離婚後の親権者をどちらかに決定できることになり、次第に母親が親権者になる場合が多数になってきました。日本では、離婚後、親権者にならなかった法の親は、子どもと接触することをあきらめて、子どもが小学校に通う時にそっと電信柱の影から登下校の様子を見るくらいなことで我慢するという傾向がかつてはありました。確かに一方がそういうものだとあきらめてくれたら、紛争は生じないわけですが、このような文化は良いとは言えないと思います。両親ともその子供に関与する権利はあるでしょうし、子どもも両親と接触する権利はあるでしょう。お父さんとお母さんは、夫婦としては、夫と妻としては失敗したけれど、離婚後もずっとお父さんとお母さんは協力してやっていくからと言えるのがあるべき方向でしょう。諸外国は離婚後も共同親権に改正する傾向にあります。この改正は子どもや両親の権利だからというばかりではなく、どちらか一方のみに親権を与えると、離婚に際して子どもの奪い合いが深刻になり、子どもの奪い合いという争いは、暴力的な争奪や自衛のために閉じ込める事態など、深刻な児童虐待を引き起こすので、共同親権にして奪い合い紛争を封じるという目的もあります。
これらの論文が発表された時期と同時並行して、水野先生は、ある研究会に参加していました。
民法改正委員会家族法作業部会
2001年2月、民法改正委員会という自発的な研究会が発足しました。
中田裕康東京大学大学院教授によれば、当時、民法改正分野では、成年後見人制度の導入や定期借家制度の創設、担保・執行法改正については法制審議会で審議がされていましたが、「民法研究者は個々の立法への対応に追われていたが、もう少し長期的な、民法全体にわたる観点からの検討が必要ではないかとの問題意識が語られることがあった。法制審議会の改編により、2001年1月をもって常設の民法部会が廃止されたことも、その必要性を感じさせる事情であった。」(後掲参照文献⑥4頁)
そこで、内田貴東京大学教授が音頭を取り、「ジュリスト」でお馴染みの有斐閣が協力する形で、有志研究者の民法改正委員会が発足します。
2003年12月から家族法作業部会が発足します。中田教授の説明によれば、やはり1996年の法制審議会の答申、要綱案の法制審議会決定まで至ったにもかかわらず、自民党保守派の強硬な反対で立法化の見通しが立っていないこと背景にあったようです。
この成果をまとめた、次の文献を読むと、いわゆる選択的夫婦別姓問題など、特定の問題にフォーカスさせず、婚姻・離婚、親子、親権など、幅広い親族法分野を対象にして、改めて問題に取り組もうとした意図がうかがえます。
<参照文献⑥>
中田裕康編「家族法改正 婚姻・親子関係を中心に」(有斐閣)
この部会に参加された水野先生は、親権法を担当。
以後、2006年2月までに10回の会議が開催され、中間的な成果として公表するとともに、座談会が行われました(成果①)。
その後、新たに3名の研究者が加わり、8回にわたる会議を重ねた後、2009年9月、「ジュリスト」で6本の論稿が掲載(成果②)。2009年10月に成蹊大学で開かれたシンポジウムで成果を報告(成果③)されました。
水野先生が離婚後共同親権案を発表したのは、成果①、②であり、内容はほぼ共通していますが、学術論文で言及されることが多いのは、条文解説も付されている②の方です。
成果③については、講演部分と報告内容について改めてまとめられ、参照文献⑥に収録された一方、質疑応答の部分については、以下の文献で確認できます。
<参照文献⑦>
「家族法改正・シンポジウム」私法72号3-52頁(2010年)
※J-STAGEで確認可能です。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/shiho/2010/72/2010_3/_pdf/-char/ja
つまり、約7年にわたって、水野先生は離婚後共同親権の導入を構想・提言してきたわけですが、それはいかなるものだったのか、次回以降、ご紹介したいと思います。
<次回>

【連載一覧】
すでに登録済みの方は こちら