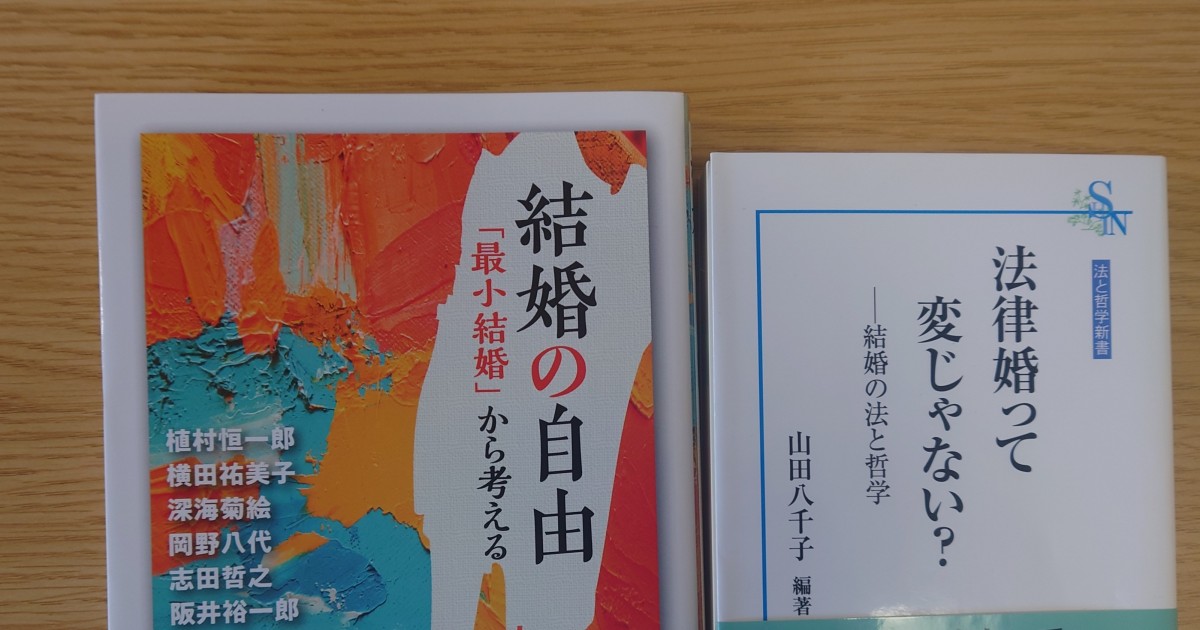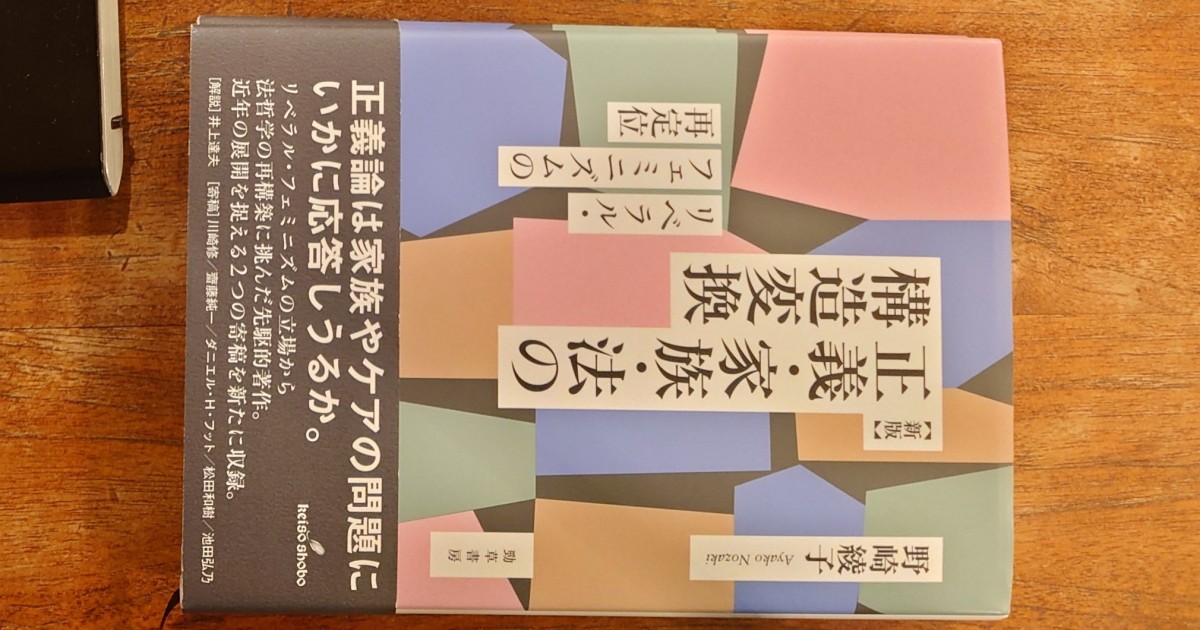水野家族法学を読む(15)「なぜ出生は、この世への強引な拉致なのか」
こんばんは。
前回、2021年7月号「法学教室」連載記事の中で、水野先生は、タイトルにもあるように、出生について、暴言ともとれる激しい表現を用いています。
【前回ニュースレター】
「子を持つ権利」を否定することを論じる文脈で用いられたこの表現。
その思想的・理論的背景として、水野先生は、脚注の中で、次の3つの論稿を挙げています。
<参考文献>
①「人工生殖における民法と子どもの権利」湯沢雍彦・宇津木伸編『人の法と医の倫理』信山社201-231頁(2004年)
②「性同一性障害者の婚姻による嫡出推定」松浦好治・松川正毅・千葉恵美子編『市民法の新たな挑戦(加賀山茂先生還暦記念)』信山社601-629頁(2013年)
③「死者の凍結精子を用いた生殖補助医療により誕生した子からの死後認知請求を認めた事例」高松高裁平成16年7月16日判決評釈」判例タイムズ1169号98-105頁(2005年)
いずれも、水野先生のHPで閲覧することが可能ですが、今回は、③の論稿についてご紹介したいと思います。
※該当の判例評釈のHP。
事案
本件は、A女が、同人と生前婚姻関係にあった亡夫B男が生前に採取して冷凍保存していた精子を使って人工生殖を行い、Xを出産したところ、Xにおいて、Bの自分に対する認知を求め、検察官を相手方として認知請求をした事案です。
Bは白血病の治療に際して、無精子症になる可能性を考慮して、平成10年に精子を保存凍結していました。精子を保存する病院に対してA・Bは「依頼書」と題する書面に署名押印して提出していますが、この書面には、骨髄移植前に精子を凍結する精子凍結保存法について、次のような説明がありました。
5.死亡した場合は必ず連絡すること。精子は個人に帰する考えより、死亡とともに精子を破棄すること。
6.死亡後の精子を用いた生殖補助操作はしないこと。
ところがBは生前、Aに対し、Bが死亡してもAが再婚しないのであれば、自分の子を産んで両親の面倒をみてほしいと話し、Bの両親には、自分に何かあった場合、Aに保存精子を用いて子どもを授かり、家を継いでもらうようにと伝えていました。
平成11年にBは死亡しましたが、AはBの両親と相談の上、夫が死亡したことを告げずに精子を保存していた病院から体外受精実施病院へ精子を搬送し、体外受精を受けて平成13年にXを出産してしまいました。
Aは、A・B間の嫡出子として出生を届け出たものの、死亡による婚姻解消後に出生した子であることを理由として受理されなかったため、検察官を相手方として死後認知請求を提訴しました。
※請求権者は子Xであり、AはXの法定代理人として提訴しています。
一審判決(松山地方裁判所判決平成15年11月12日)
(判旨)
法律上の父子関係が認められるか否かは、子の福祉を確保し、親族・相続法秩序との調和を図る観点のみならず、用いられた生殖補助医療と自然的な生殖との類似性や、その生殖補助医療が社会一般的に受容されているか否かなどを、いわば総合的に検討し、判断していくほかはない。
死者について性的交渉による受精はありえないから、このような人工受精の方法は、自然的な受精・懐胎という過程からの乖離が著しい。そして、そのことが原因かどうかはともかくとして、社会的な通念という点からみても、このような人工受精の方法により生まれた子の父を、当然に、精子提供者(死者)とするといった社会的な認識は、なお、乏しいものと認められる。その意味で、精子提供者が死亡した後、保存精子を用いて人工受精がされて、懐胎し、子の出生があったという場合において、精子提供者(死者)をもって、当然に、法律上の父と認めることには、なお、躊躇を感じざるを得ない。
監護、養育、扶養を受けることが考えられない者との間で、法律上の父子関係を認めることが、当然に、子の福祉にかなうことであるとも言い切れない。被告が指摘するとおり、法律上の父子関係が認められたことで、かえって、子に負担をかけることも、場合によっては考えられないわけではない。
また、いったん、精子提供者が死亡した後の精子使用を認めてしまうと、精子提供者の死後、精子をいつまで使うことができるのか、どのような条件の下に認めていくのかなどの困難な問題も派生することになる。
二審判決(高松高等裁判所判決平成17年7月16日)
(判旨) ※控訴人(X)、被控訴人(検察官)
認知請求が認められるための要件は、自然懐胎による場合には、子と事実上の父との間に自然血縁的な親子関係が存することのみで足りると解される。
しかしながら、人工受精の方法による懐胎の場合において、認知請求が認められるためには、認知を認めることを不相当とする特段の事情が存しない限り、子と事実上の父との間に自然血縁的な親子関係が存在することに加えて、事実上の父の当該懐胎についての同意が存することという要件を充足することが必要であり、かつ、それで十分であると解するのが相当である。
確かに、認知の訴えが制定された当時は、自然懐胎のみが問題とされており、同規定は、人工受精による懐胎を考慮して制定されたものではない。しかしながら、上記のとおり、認知の訴えは、婚姻外の男女による受精及び懐胎から出生した子について、事実上の父との自然血縁的な親子関係を客観的に認定することにより、法的親子関係を設定するために認められた制度であって、その観点からすれば、認知請求を認めるにつき、懐胎時の父の生存を要件とする理由はないというべきである。
この点、被控訴人は、認知の訴えは,父が自発的に子の認知をしない場合のことを慮って,訴訟という手段で,法的な父子関係の形成を行うためのものであるから,その請求権者は,父が自発的に認知をする余地がある子に限ると主張するが,法律上,死後認知が認められていることとの対比(父が自然懐胎直後に死亡したような場合には,実際上,父が自発的に認知をする余地はないといわざるを得ない。)からして,上記は,懐胎時に,事実上の父が生存していることを要件とする理由とはなり得ない。
被控訴人は、父の死後に懐胎された子に認知請求権を認めても実益がないと主張する。しかしながら、認知請求が認められれば、父の親族との間に親族関係が生じ、また、父の直系血族との関係で代襲相続権が発生する。被控訴人は、代襲相続制度は、死後に懐胎した子を想定していないので、死後に懐胎された子には代襲相続権が発生しないとするが、認知請求が認められた場合、代襲相続権の発生につき、死後の懐胎の場合とそうでない場合とで差を設ける理由は全くない。
確かに、認知請求が認められたとして、既に死亡している父の関係で父の監護、教育及び扶養を受ける余地のないことは当然であるが,それは、父が自然懐胎直後に死亡したような場合に比しても何ら変わりはない。
ヒューマニズムを超えた重い正義感
水野先生は、この判決を厳しく批判します。
本判決のこれほど乱暴な議論に、正直なところ驚きを禁じ得なかった。民法における法律上の親子関係の設計の議論においてどのような立場に立つとしても、本件は民法が予定している通常の生者間で懐胎された子ではなく、それとは次元の異なる問題がまず前提として存在するのであり、法的親子関係の問題としてそれをどう考えるかということが、ここでの最大の問題である。
と問題を設定されます。その上で、次のように述べます。
出生は、子にとってこの世への強引な拉致である。人生の重さは、いうまでもない。その重荷をあえて背負わせる新しい命の創造は、生きている両親の意思によって、はじめて正当化できることである。たとえ親が意識においては出生を望んでいなくても、性行為には潜在的にすべてこの意思があるといえる。本件を、未亡人が夫の忘れ形見を産んだケースと考えてはならない。性行為によって懐胎した子を親の死後に出産するケースとは根本的に異なり、母胎内における生命の誕生の瞬間に夫が生きていたかどうかは、決定的な相違である。死者の生殖子を用いたこの人工生殖は、けっして行ってはいけないことであったと筆者は考える。
死者の凍結精子を使ってつくられた子は、死体の細胞を使ってつくられた子で、その意味では、むしろクローンに近い要素がある。アメリカでは、クローン技術の進展に備えて、早死にした子の親がその子の体細胞を保存していると伝えられる。このような親の願いと自己決定が、たとえどれほど強いものであったとしても、死んだ子の細胞を使ってクローンをつくってもいいものだろうか?同様に、死後、自分の精子を残しておいて、子をつくってくれと言いのこした男性がいたら、その意思を尊重すべきであるといえようか?
そして、安楽死と対比しながら、こう問いかけます。
子を持つ「権利」は、権利と呼べるだろうか?自然懐胎によって出産する権利は、もちろん権利として保護されるべきであるが、医師という第三者が関与して人工的に生命をつくる人工生殖においては、子を持ちたいという「願望」は「権利」の名に値しないと筆者は考える。かりに百歩譲って権利と呼ぶとしても、少なくとも子が両親をもつ権利は、親が子をもつ権利よりも、重視されなくてはならない。もちろん自然懐胎で生まれる子には、出生の時点では両親をもたない片親の子もいるが、受胎時には必ず両親がいるのであり、本件の子とは異なる。また死者の凍結精子によって子をつくるべきではないという主張は、非嫡出子や片親しかもたない子を差別してはいけないという議論と異なる次元のものであって、その次元を混同してはならない。結婚した夫婦間で自然生殖によって子をもうけるべきであるという議論をしているのではなく、あくまでも死者の生殖子によって子をもうけてはならないという議論をしているのである。本件のような問題では、人間を手段化・目的化してはならないというカントの古典的なテーゼを、より根源的な意味で再考してみる必要があるだろう。
なぜここまで否定的なのか
この理由については、次のくだりにその思想的背景を看取することができます。
もしこの問題を「子の利益」という概念によって論じるとすれば、以上に述べた死者の凍結精子を用いた生殖に対する否定的な評価は、将来的にそのような手段によって生まれてくるかもしれない「子の福祉」を考えた判断だともいえるだろう。このようなつくられ方をしてこれから生まれてくる子の存在が、そもそも子の福祉に反するといえるからである。もっともすでに生まれてしまった本件の子だけを考えれば、死後認知を認めて戸籍の父の欄を埋めたほうが、本件においては、子の福祉になるといわれるかもしれない。しかし本件の原告にとっても、死後認知を認めることが必ずしも福祉になるとは思われない。長期的に考えたときに、子にとって、死者との親子関係を作ったことが、スティグマ(精神的な負担・傷)になる可能性もあるからである。本件において松山地裁判決が「監護、養育、扶養を受けることが考えられない者との間で、法律上の父子関係を認めることが、当然に、子の福祉にかなうことであるとも言い切れない。被告が指摘するとおり、法律上の父子関係が認められたことで、かえって、子に負担をかけることも、場合によっては考えられないわけではない」と述べたのは、その意味だったとも考えられる。
そして、水野先生は、近親相姦によって生まれた子のケースを引き合いに出して、次のように論じます。
死者の生殖子によって子をつくることを禁止して社会が禁忌感をもつようになれば、そのような親子関係をもつことが、本人にとってスティグマとなる可能性が高い。たとえば、フランス法は近親相姦から出生した子について法的親子関係を作ることを一方の親としか許していないが、それは、近親相姦を明示する法的親子関係をもつことの重さをその子に強いるわけにはいかないという判断からである。社会の価値観は流動的であるとはいえ、インセスト・タブーという観念は人類社会にとってかなり根源的なものであり、そのタブーは優生学的な見地からもまた家庭生活を平和に営むためにも必要な観念であるから、人類社会から失われることはないであろう。死者の子をつくり出すことは技術進化によって可能になったばかりであるから、社会のなかにタブー意識はまだ成立していないけれども、将来社会がこの禁止規範を観念として確立したときには、インセスト・タブーと同様に、生まれた子にとってスティグマとなりうる親子関係である…社会はこの禁止規範を共有するべきであると思う。
自己決定権の弊害
自由の伝統をもつアメリカ社会と異なり、女性の地位が低く共同体の抑圧も大きい日本社会においては、自由と自己決定の尊重は、もちろん今後とも強調されるべき価値ではあるが、その反面、自己決定が万能の口実となることの危険性も大きいように思われる。たとえば経済的にも肉体的にも負担の大きい不妊治療を受け続け、ドナーとの生殖医療によっても子を持つことを求める日本人女性の自己決定は、はたして産まない自由を真に保障された上での自己決定だろうか。ここで危惧した事態が、本件では、まさに最悪のパターンとして生じてしまったように思われる。
自己決定と自由の論理が信仰のように強烈に主張されるアメリカ社会の人工生殖事情では、自立した強い女性が精子バンクから望ましい遺伝形質の精子を購入して子を作るような事態が生じている。本件の母親の意思は、果たしてそのようなアメリカ女性の自己決定に匹敵する自己決定といえるだろうか。本件の人工生殖は、決してなされてはいけないことであった。日本社会の最も弱い輪のところにこのような逸脱が生じてしまったようで、痛ましい限りである。本判決のようにこのような逸脱を追認することになっては、亡夫の家族から、「家」の跡取りを産んで夫の両親の老後をみるようにという、同様の圧力が未亡人にかかりかねない。日本の状況は、いまだに、医師が「子どもを産めないと離婚される妻を救済する福音」としてドナーによる人工授精を自画自賛し、跡取りを産めという要請は妻に強い抑圧・精神的負担としてのしかかり、障害児を産んだ妻は離婚されるという風土なのである。このような状況を思うとき、上野千鶴子氏の次の願いに共鳴せざるをえない。「産みたいときに産みたいだけ産む権利と能力を。産みたくないときに子どもを産まない権利と能力を。産めないとわかったときに、その事態を受け入れる権利と能力を。そして、どんな子どもでも生命として受け入れる権利と能力を。」
自己決定は、たとえば医師のパターナリズムから患者の身体に関する決定権を守る場合のように、かなり限定的な問題について、かつよほど条件を整備して、用いられるべき概念である。人間は周囲から思わされるように思うものであるのだから、一般的な自己決定をすべての正当化根拠にするのは、非常に危険である。とりわけ生命の誕生においては、子の尊厳と人生の重さを十分に考えて、法秩序を構築しなければならない。法学は観念の学問であり、人間は、観念で思考して意識をもつ、言葉の奴隷なのだから、実親子法は、社会の中に生きる人間の尊厳を守るにたる慎重な法理でなくてはならないだろう。
こうしてみると、水野先生は、本件事案の結論の具体的妥当性だけではなく、強制認知という法制度が利用される様々なケースを想定し、法体系の全体的整合性を踏まえながら、本件事案の妥当性を論じていることが分かります。
ただ、私見ではありますが、それでもなお、水野先生のご主張が2021年の現在において、なお妥当するかどうかは再考の余地があると考えられます。
本件のような家の跡取り的な話だけではなく、死者の精子・卵子を利用した出産には、様々なニーズがありますし、そもそも、婚姻関係にあった女性が、亡くなったパートナーの生殖子を用いて出産することと、それほど大きな倫理的批判に値するかどうか、水野先生が設定された倫理基準が妥当なのか、議論が必要だと思います。
フェミニズムで議論される「リプロダクティブヘルス/ライツ」との整合性も重要です。1994年、カイロ行動計画で提唱された4つの権利は、女性の健康や権利についてアウトラインは示しているものの、具体的に「誰が誰の生殖の力をコントロールする権利があるのか」という問いへの明確な回答を示しているものではありません。
その後(最高裁判所判決平成18年9月4日)
実は、高松高裁の判決は、最高裁判所で否定されています。
(判旨)
民法の実親子に関する法制は、血縁上の親子関係を基礎に置いて、嫡出子については出生により当然に、非嫡出子については認知を要件として、その親との間に法律上の親子関係を形成するものとし、この関係にある親子について民法に定める親子、親族等の法律関係を認めるものである。
ところで、現在では、生殖補助医療技術を用いた人工生殖は、自然生殖の過程の一部を代替するものにとどまらず、およそ自然生殖では不可能な懐胎も可能とするまでになっており、死後懐胎子はこのような人工生殖により出生した子に当たるところ、上記法制は、少なくとも死後懐胎子と死亡した父との間の親子関係を想定していないことは、明らかである。すなわち、死後懐胎子については、その父は懐胎前に死亡しているため、親権に関しては、父が死後懐胎子の親権者になり得る余地はなく、扶養等に関しては、死後懐胎子が父から監護、養育、扶養を受けることはあり得ず、相続に関しては、死後懐胎子は父の相続人になり得ないものである。また、代襲相続は、代襲相続人において被代襲者が相続すべきであったその者の被相続人の遺産の相続にあずかる制度であることに照らすと、代襲原因が、死亡の場合には、代襲相続人が被代襲者を相続し得る立場にある者でなければならないと解されるから、被代襲者である父を相続し得る立場にない死後懐胎子は、父との関係で代襲相続人にもなり得ないというべきである。このように、死後懐胎子と死亡した父との関係は、上記法制が定める法律上の親子関係における基本的な法律関係が生ずる余地がないものである。そうすると、その両者の間の法律上の親子関係の形成に関する問題は、本来的には、死亡した者の保存精子を用いる人工生殖に関する生命倫理、生まれてくる子の福祉、親子関係や親族関係を形成されることになる関係者の意識、更にはこれらに関する社会一般の考え方等多角的な観点からの検討を行った上、親子関係を認めるか否か、認めるとした場合の要件や効果を定める立法によって解決されるべき問題であるといわなければならず、そのような立法がない以上、死後懐胎子と死亡した父との間の法律上の親子関係の形成は認められないというべきである。
以上によれば、本件請求は理由がないというべきであり、これと異なる原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。
水野先生が高裁判決時に問いかけた峻厳な生命倫理について、結局のところ、最高裁判所は、非常に形式的な論理で高裁判決を否定したにとどめました。
しかしながら、この判決には、滝井繁男、今井功両裁判官による詳細な補足意見が付されており、最高裁判所が事例判決の枠内で、生命倫理に懸命に回答を試みようとした形跡をうかがい知ることができます。
<最高裁判決>
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/033488_hanrei.pdf
<最高裁判例評釈>
栗原由紀子「凍結精子を用いた死後懐胎子による認知請求」尚絅学院大学紀要第57集33頁以下
https://libwww.shokei.ac.jp/image/bulletin/57/KJ00005305579.pdf
(この連載つづく)
【連載一覧】
すでに登録済みの方は こちら