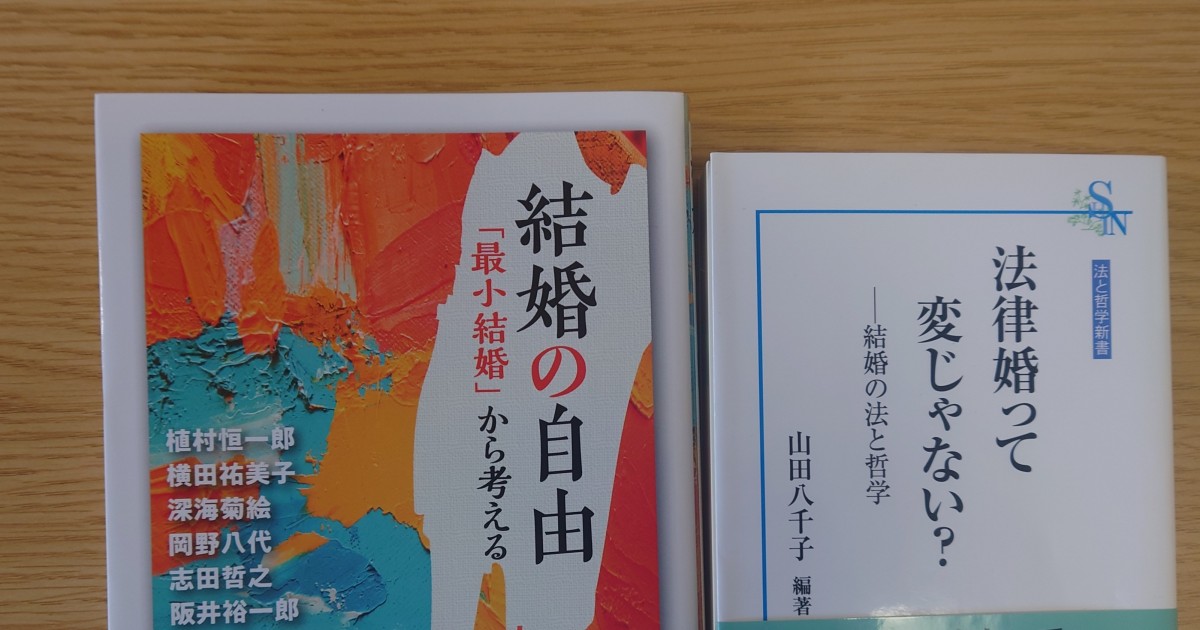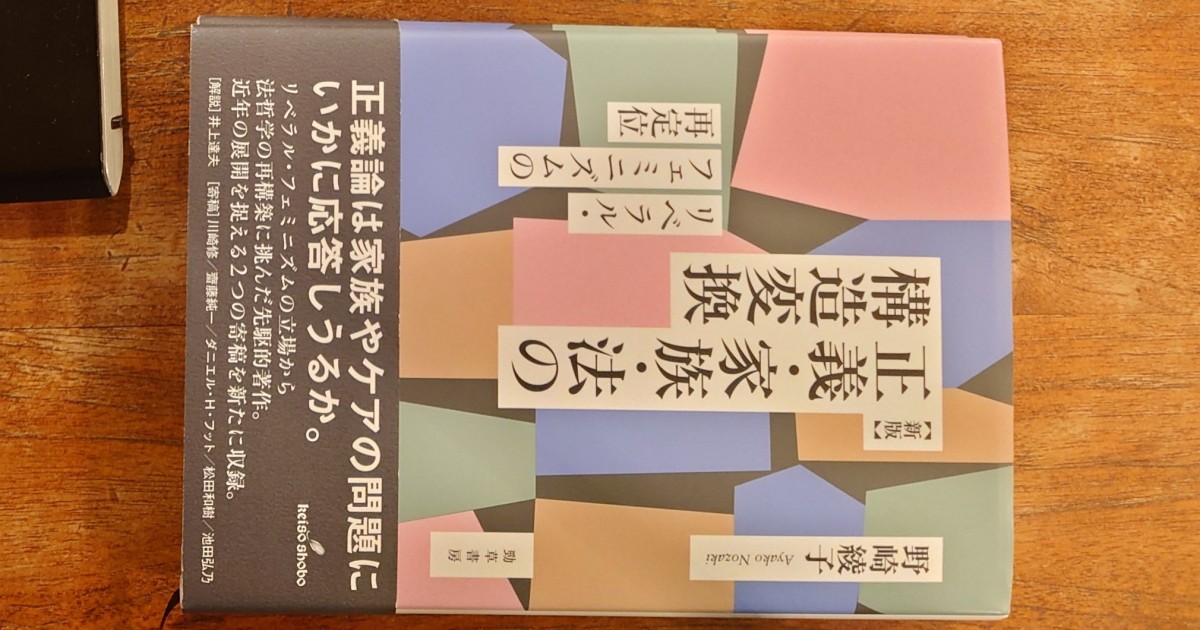水野家族法学を読む(22)「裁判所はどこまで家族に介入できるのか?」
<前回>
家族と裁判に関する国際会議
<参照文献①>
水野紀子「日本家族法を考える 第7回 婚姻の効力を考える」法学教室2021年11月号(有斐閣)88頁以下
前回のニュースレターで、フランス民事訴訟法学者のロジャ・ペロの次の言葉をご紹介しましたが、水野先生によれば、この言葉は、1994年7月にブリュッセルで開催された国際会議を記録した出版物「家族と裁判」のはしがきの言葉だということです。
「家事裁判は非常に興味深い現象である。幼いモーツァルトが不協和音をならして顔をしかめ『この二つの音は愛し合っていない』と言った言葉を思い起こさせる。家庭と裁判は、それぞれ貴重な制度であるが、それらもまた、愛し合ってはいない。家族の中に判事が干渉することは、圧倒的多くの場合には既に修復しがたいひび割れがあることを予示するか確認するとい、たいていは失敗のしるしである。そして司法が救済に乗り出すときには、まず逃れ得ない家族的な要請の圧力下で、司法自身もまた一定の脆弱化を免れ得ない。」
前回、「法は、家庭に何を命じることができるのか?」という小見出しを掲げましたが、実務的な場面に換言すると、これは「裁判所は、家族に何を命じることができるのか?」ということになるでしょう。婚姻という契約の法的拘束力を、裁判所が法的にどこまで担保しうるのか、という問題です。
この点を水野先生が原理的に考察した論文があります。
<参照文献②>
水野紀子「家族と裁判に関する覚書」北村一郎編集代表「山口俊夫先生古稀記念祝賀論文集 現代ヨーロッパ法の展望」255-274頁(1998年)東京大学出版会
調停制度という紛争解決手段
水野先生は、上記のペロの言葉を冒頭に引用してから、次のように問題を提起します。
家族の間に生じた紛争はどう解決されるべきか。当事者間では解決できなくなったとき、司法が介入するべきか。介入するとすればどのように介入するのであろうか。家族の間の裁判は、どう行われるべきであろうか。これらの問いは、家族と裁判という「愛し合っていない」二つの制度の調和をどのように求めるかという課題であり、わが国においても長らく議論されれきた課題である。
水野先生は続けて、家庭裁判所が、調停制度という紛争解決手段を大きな柱として運営され、裁判の敷居を下げ、裁判的正義の高価さという欠点を解消した長所を否定できないとしつつも、合意成立を至上とするあまり、当事者の権利を擁護せず、調停制度が裁判的正義に代わりうるものかという原理的な問題が常に意識されてきたことを指摘します。
そして、(あえて乱暴なまとめ方をすれば)家庭裁判所の調停制度について、実務家から積極的な評価、学者から消極的な評価に分かれてており、実務側から改善や試行錯誤が続けられてきたものの、近年では学説も全面的否定論→現実的・消極的是認論→理論的・消極的肯定論へと変化してきた、と分析されています。
そして、野田愛子元判事の言葉を引用されます。
「従来の家事調停論は、筆者(野田)も含めて民法改正以来の啓蒙的機能に重点を置き過ぎていたように思われる。近時の諸外国の傾向として、民事紛争の自立的解決に論議が集まっているようであるが、その傾向に注目すると、今後は、家事調停プロセスの客観的分析をし、裁判官や調停委員の個人的体験に頼るばかりでなく、当事者の調停行動の客観的分析に即した調停技法を検討すべきではなかろうか。」
しかし、水野教授は、そのような調停技法の開発は果たして可能なのか?と疑問を投げかけます。
家族法の実体法規定が与える影響
まず、水野先生は、家族法の実体法規定が、家事裁判・調停の手続きの在り方にどのように影響を与えているのか、2つの角度から分析を試みます。
① 家族法の規定の明確性
家族法の実体法規定が、財産法の規定のように一定の明確性を持ち得るならば、調停より通常訴訟の方が、紛争解決手段として親和性を持つはずです。
しかし、当ニュースレターで度々ご紹介している通り、日本の家族法にはいわゆる白地規定が多く、裁判官に紛争解決の明確な指針を与える条文が非常に少ないため、裁判官の判断の裁量が非常に大きくなる(法的安定性を欠く)という致命的な問題を抱えています。
この論文においても、水野先生は改めてその点を指摘されています。
ところが、水野先生によると、同様の困難は西欧法にも共通している部分があることを指摘されます。
しかし日本法の現状は裁判離婚にしろ財産分与にしろこの点で極端に行き過ぎとはいえ、問題は、日本法に限らず一般的に、現代の家族法においては、かつてのような一義的で明瞭な条文を作りにくくなっていることである。戦後の日本民王改正の際に平等化がこの傾向を助長したように、夫婦の間の権限を平等にすることは、夫の決定権限を立法できないため親権行使などの規定から一義性を失わせる。さらに家族生活に当事者の自由を取り入れることも、家族生活の規律を一義的に明瞭な規定によって構成しにくくする。また子の実質的な保護や子の主体性を配慮することは、父と母との対立、両親と子との対立の場面で、法が明瞭で一義的な条文を設けにくいことを意味する。西欧社会で家族の裁判の在り方が問題としてクローズアップされた背景には、このような家族法の変化が基礎にあるように思われる。
前述した国際会議のレポートでフランスのラブリュス教授は、この家族法の変化について次のようにまとめている。「1960年代からヨーロッパのほとんどすべての国で家族の領域で行われた改革は、立法者の配慮という特徴を持っていた。婚姻とその効果、離婚、親権、親子関係、家庭裁判所として特別裁判所や特別判事を創出した制度改革などを定める現代の法は、国によってその実体や方法がどれほど異なっていようと、立法者の決定には共通点があることを示すものであった。つまり自由の尊重、両性の平等、嫡出子と非嫡出子の平等、子の主体性の認知などの正義の原則に従うと同時に、だからといって家族関係の創設形式に関する公の秩序を法規することなく、家族関係を再構築し再整備しようとする立法者意思である。自由主義はごく慎重に判事のコントロールのもとでその効果を調整されてはじめて導入された」結果、「準拠する抽象的な規範と判決の具体的な命令との調和」が必要となることとなった。具体的にはたとえば、「契約において信義則概念が重要な地位を占めるように、子供の利益とか家族の利益とは扶養債権者の必要性といった不鮮明な概念を法が入れる」こととなり「それらの概念の具体的な内容の決定は判示の仕事となった」のである。メルドラー教授は、この間の事情を、家族間の紛争が増加しそこに国家が裁判によって介入するようになった原因は、時系列でいうと、最初に子の保護の要請のため、次に平等の要請のため、そして最後に自由と幸福追求のためであった、と説明する。
そこで、実体法が曖昧さを抱えて規律されてしまうため、第2の角度からの分析が必要になる、と水野先生は指摘します。
② 当事者の合意の効力
水野先生は、次のように述べて、現代のフランス法の改革にも関わらず、フランス法は依然として、家族に実効的に介入している、と分析され、その基本的原則をフランス民法2060条の規定に看取しています。
<フランス民法2060条>
人の民事身分や能力に関する問題について、離婚や別居に関する問題について、また公の集団や公共施設やさらに一般的な公の秩序に関するすべての事柄にかかわる争いについて、何人も仲裁契約を結ぶことはできない。
一連の改正にもかかわらず、フランス法は、当事者の合意にすべてを委ねることを許していないのです。
調停制度の評価に関する各国の比較
続いて、水野教授は、調停制度の評価について各国の比較を紹介しています。
<英米法>
離婚訴訟が高価で疲労困憊する手続であった経緯から、好意的な評価がされているとしています。
ただ、水野教授によれば、「英米法における調停制度の導入と活用は、筆者には、理念的なものとして正当であるからというより、政治的・政策的な必要性から推進されてきたもののように見える。」
<フランス法>
法理念・裁判理念を根拠に、家族間紛争の調停に対して基本的に懐疑的な姿勢を取る。
理由としては、当事者の合意に委ねることは、バーゲニングパワーの強い側による合意形成の弊害が指摘されていること、デュープロセスの手続ならば守られた権利が守られないことなどが指摘されています。
また、日本の家庭裁判所実務でかつていわれた隣接諸科学との協力にも否定的で、裁判官は、あくまで法という領域にとどまり、法の統一的判断を維持する建前を重視しています。
そもそも、「家族間紛争だから裁判になじまない」という日本的発想とは真逆であることがわかります。
<ドイツ>
ここでは、ドイツのシュワーブ教授の考え方を中心に紹介されています。
「幸いにしてほとんどの離婚は相互の合意で行われる。しかしこの合意はそれほど意味をもたない。なぜなら、大きな傷を残しとりわけ子供たちに賀巌もたらす長くつらい手続の結果、単なるあきらめがもたらした合意であることが多いからである。」
「「調停」という言葉は、法律家や心理学者に魔法の威力をもつ」
そして、シュワーブ教授は、家族法の「民営化」に反対します。
「裁判所は正義を行いもっとも弱い者を守らなければならない。この理由によって、裁判官が結果についてコントロールをし続けなければならない。」
水野先生の結論は。。。
水野先生は、かつて「身分関係の非合理性」から我妻栄や中川善之助らの先輩たちが、家事調停を評価したことについて、批判的な立場をとっています。
我妻博士が(家事調停を積極的に評価した)立論の補強としている中川善之助博士の「身分関係の非合理性」という概念について、筆者は基本的に批判的な立場をとる者である。この概念によって家族法を近代民法として継受することが疎外され家族法学が思考停止してしまったと考えるので、同様の思考停止を家族間の紛争解決について持ち込むべきではないと思う。しかし同時に、他人間と同様の手続きで家族間紛争が解決されるべきとも思われない。家族間紛争では、当事者間の葛藤が深く、過去の裁断より未来の構築が重要であり、近づき易い親切なガイドが必要であり、なにより子どもの保護というもっとも深刻でありながら客観的な線を引くことができない問題を内包している。我妻博士の調停肯定論が、家族間紛争の解決は家事調停で可能である限り裁判よりも調停によるほうが望ましいという内容であれば、その限りでは理念的には政党なものを含んでいる。問題はどの範囲でどのような条件が満たされたときに調停がふさわしい解決手段なのかということであり、その点をもっと詰めて考える必要がある。
具体的に、①調停では裁判官が主役であり続ける。②白地規定を運用する共通の基準の確立。の2点を提言されて論文は締めくくられています。
最後に
個人的感想を少々。
①この論文は、水野先生がいかにフランス法から影響を受けてきたかがよくわかる論文です。だからといって、フランス法に「かぶれている」わけではなく、西欧法対比説の立場から、日本法にmoderateにその論旨を取り込もうとされています。
②昨年からずっと読者の皆さんに申し上げていますが、水野先生のプラグマティストぶりがいかんなく発揮されています。法をグランドデザインし直すのではなく、あくまでマイナーチェンジ。既存の司法リソースを「上手にやりくり」する方向を指向されています。
さて、日本の司法はそれでどこまで持つことやら。
(この連載つづく)
【連載一覧】
すでに登録済みの方は こちら