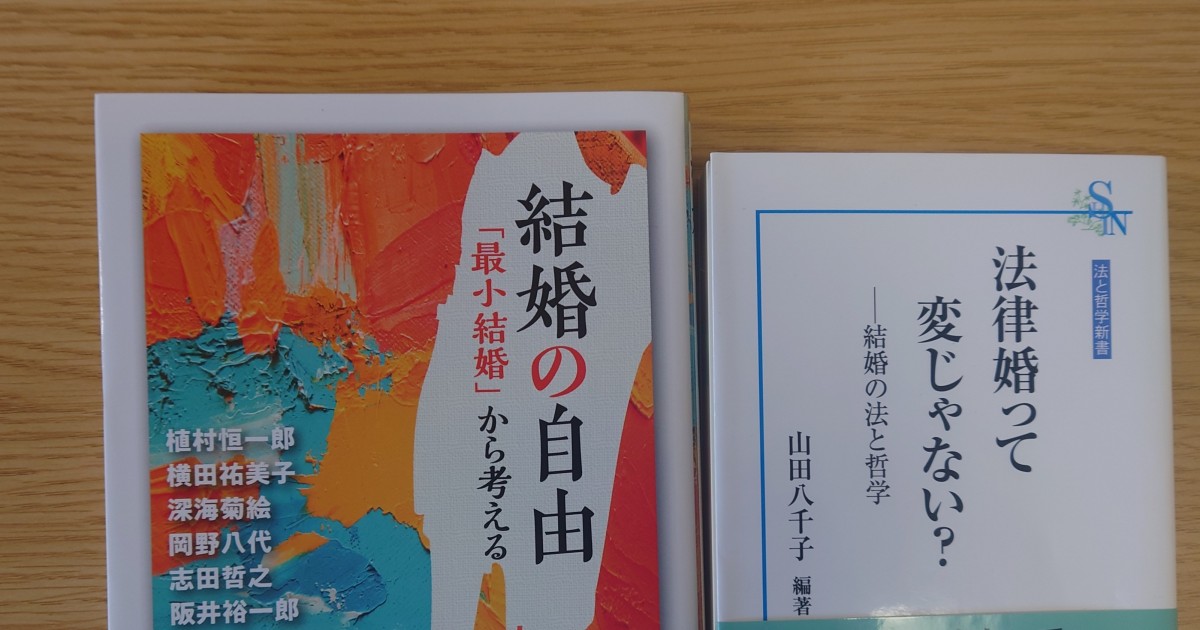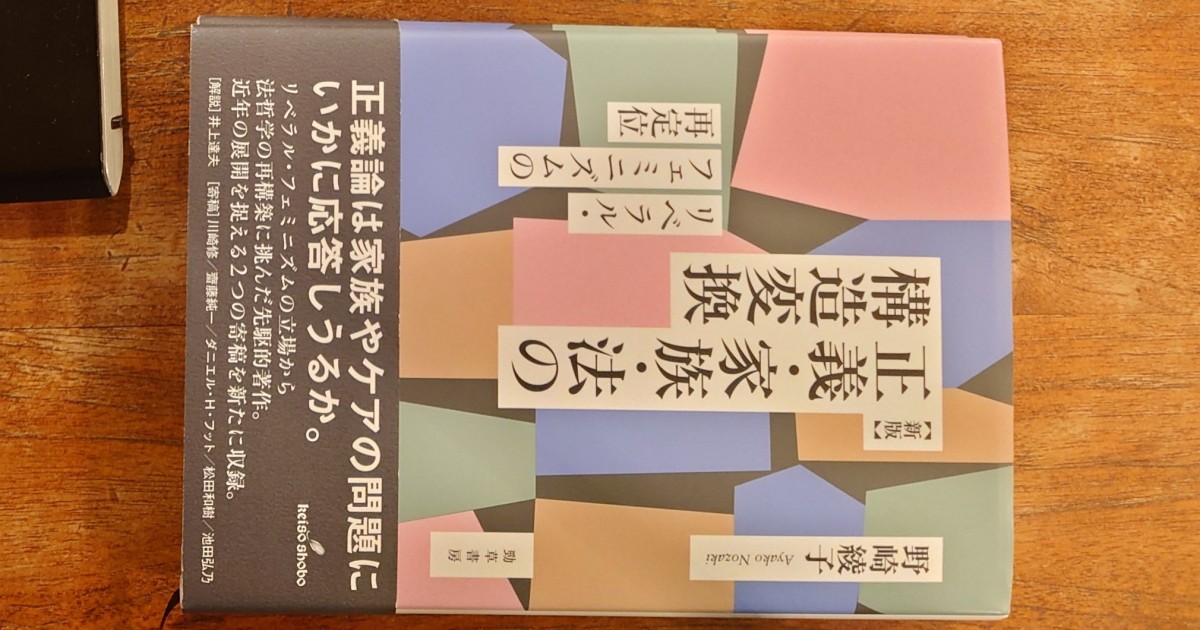民法学の第一人者は、なぜ離婚後共同親権「反対」に転じたのか(3)「判例」
<前回>

小論文
2021年8月、東京・永田町。
2020年から20年近くさかのぼり、水野先生の各種論稿に目を通していましたが、離婚後共同親権への"源流"をなかなか発見できなかった頃、ある小論文に行き当たりました。
<参照文献>
「日本家族法の特徴と民法改正案をめぐって」(所収:「家庭の未来」研究会編『家庭の未来』労働基準調査会)149-161頁(1998年)
※労働基準調査会・・・現労働調査会
座長には、法女性学(後にジェンダー法学に発展する)の草分け的存在である、金城清子津田塾大学教授(当時。東京家政大学や龍谷大学でも教授を歴任した)が務めていた研究会に寄稿したものです。
「子の養育義務や引渡請求において」と題された項において、水野先生は、こんなことを述べています。
子の養育義務を適切に果たせない親に対する公的介入においても、西欧法ははるかに整備されているが、子の引渡請求における西欧法の強力な義務付けも注目される。両親間における子の奪い合い紛争は、日本でも深刻化しているからである。西欧諸国の立法例は、裁判所が親権行使に対する様々な監督を実効的にするだけではなく、その監督と裁判所の判断を、強制執行(直接強制)はもちろん、最終的には法廷侮辱罪や遺棄罪や誘拐罪を適用して刑事罰まで発動することを準備して、法が強制する。日本法では、子の引渡請求に介入することに消極的であり、親権者からの引渡請求に直接強制を用いることにさえ消極説が強い。(※)
※執筆当時(1998年)は、学説上の対立があったが、現在、2020年の民事執行法改正により、子の引渡しに直接強制が可能となっている。
日本の家庭裁判所における手続については前述したが、特に親権者間の子の奪い合い紛争という場面で、この手続がどのように機能するだろうか。まず、後見的調整機能という側面では、当事者の非難合戦となる対審構造の手続の弊害は大きく、子の幸福のためには、両当事者が冷静な互譲の精神で話し合って結論を出す和解にまさるものはないから、家庭裁判所の手続がその長所を発揮できる。とりわけ調査官や医官による科学的心理学的治療的介入は有効である。しかし、迅速性の保障がなく審判の強制力が欠落していることは、致命的な欠陥である。この欠陥があるために、調停委員を交えた話し合いによる教育的効果に期待するばかりで、確信犯的に振る舞い自力救済的に子を奪ったり財産を処分したりする者がいると、守るべきその家族の権利を実効的に保護することができない。この無力さが子の引渡紛争における自力救済の悪循環を招いている。この種の自力救済による解決は、子にとっては、奪い合いの対象となる被害のほかに、予防的に片親に悪口を吹き込まれ洗脳される被害など、非常な弊害と危険をもたらすものである。
あっと思ったわけです。
現在、「片親洗脳」といった非難は、共同親権推進派から執拗に提起・指摘がされていますが、水野先生もかつて、同じことを思っていたわけです。
元に戻って、2020年の日仏会館で行われたセミナーレジュメを読み返す。
これか。この判例のことだったのか。
最判昭和61年7月18日
民集第40巻5号991頁。
人身保護法に関する最高裁判例です。
事案は決して著名ではないので、以下に概要を記しますが、11年以上にわたって、両親が子に会えなかった事案です。
【事案の概要】
両親甲・乙、子A、拘束者B1・B2
昭和49年 子A出生。
家計の都合で、異母弟のB1・B2夫妻に預ける。
昭和51年 甲乙から引渡請求。
B1・B2の懇願で、保育園入園までは、彼等の手元に置くことに。
昭和53年 いったん引渡しがなされるも、
B1・B2は誘拐されたと騒ぎ、空港で子Aを取り返す。
その後、引渡しに関して交渉・誓約書までが取り交わされるも、実施に至らず。
昭和56年 甲・乙、子の引渡しを求める訴訟提起。
一審・二審・上告審いずれも勝訴。
昭和60年 円満解決のため、長崎地裁で引渡しの和解成立。
しかし、B1・B2履行せず。
親権者でも何でもない人物が、11年以上も子を拘束していた、という事例です。
最高裁判所第二小法廷は、引渡しを認容する一方、事案について、次のような判断を示しました。
意思能力のない幼児の監護はそれ自体人身保護法及び同規則にいう拘束に当たると解すべきものであるが(昭和四二年(オ)第一四五五号同四三年七月四日第一小法廷判決・民集二二巻七号一四四一頁参照)、幼児に意思能力がある場合であつても、当該幼児が自由意思に基づいて監護者のもとにとどまつているとはいえない特段の事情のあるときには、右監護者の当該幼児に対する監護は、なお前記拘束に当たるものと解するのが相当である(人身保護規則五条参照)。そして、監護権を有しない者の監護養育のもとにある子が、一応意思能力を有すると認められる状況に達し、かつ、その監護に服することを受容するとともに、監護権を有する者の監護に服することに反対の意思を表示しているとしても、右監護養育が子の意思能力の全くない当時から引き続きされてきたものであり、その間、監護権を有しない者が、監護権を有する者に子を引き渡すことを拒絶するとともに、子において監護権を有する者に対する嫌悪と畏怖の念を抱かざるをえないように教え込んできた結果、子が前記のような意思を形成するに至つたといえるような場合には、当該子が自由意思に基づいて監護権を有しない者のもとにとどまつているとはいえない特段の事情があるものというべきである。
2020年2月、日仏文化会館でのシンポジウムにおいて、この判例をご紹介された水野先生によれば、B1・B2らは、子Aに対し、ハサミを持たせて実母から送られてきた服を切り刻む等、憎悪を煽るような工作をしていた事実もご紹介され、その後公刊された研究誌「日仏文化」において、「それで当事者が救われたわけではなかったろう。」という感想を述べられています。
<参照文献>
「民法・家族法学からみた離婚後共同親権」日仏文化90号89頁
このシンポジウムでは、もう1つ、最高裁判例をご紹介されています。
最判昭和46年7月23日
民集第25巻5号805頁。
判例百選18事件ですね。
一般的には、 離婚による慰籍料と財産分与との関係に関する判例として知られ、財産分与で慰藉されない精神的損害について、別途慰謝料を請求することが可能である、と判示したものですが、この事案は、元夫のDVと、いわゆる追い出し婚事案でした。
これも、原審の判決文によれば、元夫からのDVで元妻が負傷し、実家に帰ったが、その後、子どもに会わせてくれなくなった事案であり、何と、民事訴訟で親権も元夫が取得(この人物は前に2回短期間で別の女性と婚姻が破綻していたが)している、という事案です。
元妻が会おうとすると、「手も足も叩き折る」「出ていけ」等の暴言があったほか、極めて低額な財産分与しかなされていません。
昭和40年代のきわめて差別的な裁判官の傾向がうかがえますが、前回ニュースレターでご紹介した通り、水野先生は、裁判官の裁量に強い不信感があるのは、こうした判例をご存知だったからだと思われます。
そして、契機になったのは、次の2つの判例と推測されます。
最判平成5年10月19日/最判平成6年4月25日
民集47巻8号5099頁/民集48巻3号992頁。
この2つの判例は、離婚の法律問題にご関心のある方、専門家の皆さんにはポピュラーな判例かと思いますが、人身保護法に基づく子の引渡請求に関する最高裁判例で、同法に基づく子の引渡請求に厳格な要件を課したものです。
一般の方には拙文で恐縮ですがこちらの記事をご覧ください。
水野先生は、次の小論の中で、次のようにこれらの判例を評価されています。
<参照文献>
「子の奪い合いの法的解決をめざして」家族〈社会と法〉18号37-42頁(2002年)
子の奪い合い紛争については、長らく、家庭裁判所と人身保護法による地方裁判所の「消極的権限争い」ともいうべき歴史があった。かつての迅速性も強制力も欠きがちだった家庭裁判所の手続きでは、当事者が人身保護法に訴えるのもいわば当然のなりゆきであったが、人身保護法という手段は、事実上の強制力はあっても他の点で問題が山積する手段であった。最高裁平成5年10月19日民集47巻8号5099頁をはじめとする一連の最高裁判決によって、子の奪い合いという争いにおける人身保護手続と家庭裁判所の手段の使い分けという問題に対する最高裁の態度は、かなりはっきりしたといえよう。親権者同士である夫婦間の奪い合いにおいては、親権濫用にあたるような例外をのぞいては、まず家庭裁判所に管轄させるものとして直接的な人身保護請求は認めないが、家庭裁判所の判断が出ていれば、その判断の一種の強制履行の手段として人身保護請求を認めるという態度である。これは、人身保護手続と家庭裁判所の手続の併存状態について批判的であった多くの学説の主張を容れた判例変更であったといえる。たしかに手続の従来の併存状態は大きな問題を抱えていた。しかしだからといって、人身保護法の適用を否定して、家庭裁判所にすべての手続を集中することだけによって問題が解決するとは、とても思われない。
そして、最後にご紹介するのが、離婚問題の超有名判例です。
最大判昭和62年9月2日
民集41巻6号1423頁。
いわゆる有責配偶者からの離婚請求です。
この判例では、子の奪い合いといった事情は生じていません。が、長期間離婚が成立しなかったために、妻側が経済的に弱く困窮していたという事案です。
<参照文献>
「有責配偶者からの離婚請求」法学教室193号52-58頁(1996年)
水野先生は、次のようにこの裁判を評価し、離婚法の問題点を指摘しています。
消極的破綻主義は、破綻主義離婚法を立法した諸外国より強力な「離婚されない権利」を保障したものといえるかもしれない。この点では、婚姻の制度的・法的な効力を強く保障するものである。しかしわが国の家族法では、諸外国と比較すると、婚姻は一般的には、制度としてむしろ非常に弱いものとなっている。たとえば夫婦財産制や離婚給付では他人官の同居生活とほぼ変わりないような財産請求権しか認められず、一方配偶者の処分に抗して婚姻住居を確保する手立てもなく、婚姻費用分担請求や扶養請求の確実な履行確保手段もない。配偶者相続権を除けば、法的に離婚されないという一点のみ、配偶者の権利が保障される。妻は無職無資産で貧しく、夫は会社社長として裕福に生活しながら、全くの没交渉で三六年間の別居生活を送っていたという昭和62年大法廷判決の事案が、典型的にこのような婚姻法の特徴を表していたように思われる。
常に視線は弱者救済だったが
前回ご紹介した水野論文と合わせて読むと、水野先生には、一貫した姿勢があります。
家庭内の弱者、とりわけ子の救済を念頭に置いていたのです。
昭和50年~60年代の離婚紛争は、子や経済的に弱い女性に非常に不利でした。
長引く訴訟。有責性を巡る不毛な争いと不明朗な慰謝料算定基準。ミソジニーが蔓延る裁判官の判断傾向。。。
長引く紛争で、傷ついていく子どもたちを救済し、迅速な離婚裁定と、必要な経済的保障を確保する。そうした離婚法全体の改革の必要性を、水野先生は認識していたものと思われます。
しかし、そこにはある種のバイアス(偏見)のようなものが残されました。
冒頭にご紹介した"同居親の洗脳"といったものですね。
これには大きな事情が2つあると、私は考えていまます。
1つは時代性。
水野先生が念頭に置いていた判例は、追い出し婚など、今では少数派となった紛争形態も含まれています。それは、水野先生の研究期間が、社会の大きな変化の時期と重なっていることと無縁ではありません。
DVや児童虐待といった、新たに可視化されるようになった家庭病理だけではなく、従前から問題視されていた追い出し婚といった事案にも、水野先生は目配りの必要性を感じていた、ということだと思われます。
また、この時期はインターネットの普及より若干前の時期であり、2021年に暮らす私たちには想像が難しくなってきましたが、80年~90年代に離婚紛争を調査する方法は、今よりずっと限られていました。
ググればいっぱしの法律解説のHPがヒットする、という時代ではないのです。
そうした中で、水野先生が、主要な最高裁判例の事実関係の分析に、主眼を置くというのは、当時としてはスタンダードな研究アプローチであり、それでバイアスを取得したとしても、責められる事情とは言い難いのです。
もう1つ、なぜ水野先生が、子の奪い合い紛争で同居親の擁護に距離を置いていたのか。
それは後日の連載で明らかにしたく存じます。
次回は、こうした判例分析を通して、水野先生が、離婚後共同親権の導入を「着想」するに至った経緯と、ある研究会の活動をご紹介したいと思います。
<次回>

【連載一覧】
すでに登録済みの方は こちら